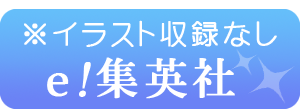身代わり乙女は王の腕 に囚われる
あまおう紅 イラスト/蔀シャロン
いつものように顔を見せたグレンは、ひどく疲れた顔をしていた。
事情を訊くと、閣議が何日も紛糾し続け、寝る間を惜しんで調整を続けているものの、解決の糸口が見つからないのだという。
ヨゼーファはその時、彼をいつものテーブルではなく、三人掛けのソファに誘った。
そして片端に腰を下ろすと、少し離れたところに座ったグレンに向けて、自分のひざを軽くたたいて言ったのである。
「ここに頭をのせて、寝て?」
「…………」
よかれと思って申し出たというのに、彼は言葉もなく硬直したきりだった。
その顔は、控えめに見ても混乱の際に達しているようだ。いつも鋭く輝いている青灰色の瞳が、焦点を探してさまよう。
ややあって彼は鈍い反応を見せた。
「……は?」
ヨゼーファはふたたび自分の膝を軽くたたく。
それは昔、何かいやなことがあって落ち込むヨゼーファを甘やかすときに、姉がしてくれたことだった。
姉の膝に頭を預けて横になると、人の体温と優しさに包まれるようで、安心して眠ることができた。
よってヨゼーファは、思いやりを込めて彼を見つめる。
「今日はわたしとおしゃべりしなくていいわ。ここにいる間だけでも横になって休んで」
「その…気持ちはありがたいが…」
「クッションがないから、わたしのひざを提供するわ。婚約しているんだもの。そのくらい問題ないでしょう?」
「…いや、だいぶ問題だ。やめておく」
その返答は予想外だった。
「待って…っ」
ソファから腰を上げようとした彼の腕を、ヨゼーファはあわててつかむ。
「あきれた? 馴れ馴れしくするつもりはなかったの。ただ、あなたのために何かしたかっただけで…っ」
しかしグレンは、頑なにドアに目を向けて言った。
「今日は帰る」
「グレン…っ」
「放してくれ。俺は、…なんていうか…疲れていると逆に我慢できなくなるたちで…」
言っていることの意味がよく分からない。
だが自分が彼を不快にさせたことだけは、まちがいなさそうだ。
どうすれば機嫌を直してくれるのか必死に考えている間にも、グレンは「放してくれ」と言いながら、ヨゼーファの手を自分で振り払う。
こんなふうに拒絶されるのは初めてだった。
「ごめんなさい、グレン…!」
振り払われたヨゼーファは、ドアへと向かいかけた彼の背中に、思わず腕をまわしてしがみつく。
後ろから抱きしめるようにして、ぴったりとくっつく。
「悪気はなかったの。あなたのことが好きだから、役に立ちたくて…っ」
頬を押しつけた彼の背中から、ごくりとツバを飲みこむ音が聞こえてきた。
「…放せ」
「許すって言って。お願い――」
「許す! 許すから…っ」
ヨゼーファの懇願に、グレンはひどく動揺した声音で応じた。そして自分を抱きしめる両手をつかみ、力まかせに引きはがす。
自分を落ち着かせるように息をついた彼は、やがてヨゼーファをふり向き――そのとたん、ぎょっとしたように目を見開いた。
「なっ、なぜ泣く?」
「泣いてないわ」
「だが…」
グレンは、ゆっくりとソファの前にひざをつき、こちらの顔をのぞきこんでくる。
そしてヨゼーファの目尻に浮かんだ涙を、長い指でぬぐってくる。
「泣いてないわ。ただ…グレンが怒ったのかと思って、ちょっと心配になっただけ」
「怒るわけないだろう。こんなことで」
「本当?」
うるんだ目で彼を見つめ、ヨゼーファは「よかった…」とほほ笑んだ。
そのくちびるに――ふらふらと、吸い寄せられるようにグレンが口づけてくる。
「……っ」
くちびるに感じた優しい感触に、ヨゼーファは目を瞠った。
その間にも、二回、三回と、くり返し押し当てられてくる。
(…キスしてる…)
ずっと好きだった人と、口づけを交わしている。その感動に頭が沸いてしまう。
と、彼はハッと我に返ったように顔を離した。
「す、すまない! つい…っ」
謝罪に、ヨゼーファは大きく首を横に振る。
「どうして謝るの? うれしかったのに…」
グレンは、信じられないというようにヨゼーファをじっと見つめた後、かすれた声で訊ねてきた。
「……本当か?」
「えぇ」
はっきりとうなずく――や否や、いっそう強くくちびるが重ねられてくる。
それは、はじめのうちは様子を探るように慎重な動きだった。しかしヨゼーファが逃げないでいるうちに、次第に熱を帯びていく。
くちびるをこすり合わせ、食み合っていたものが、やがて隙間から舌が押し込まれてくるに至って、思わぬ感触にくぐもったうめき声がもれる。
「…ん…ぅ…っ」
気がつけば彼は、ソファの背もたれにヨゼーファの頭を押しつけ、貪るようにして口づけに夢中になっていた。
ヨゼーファはといえば、受けとめるだけで精一杯である。されるがままになりながら、身体の中までまさぐられるような、ひどく淫蕩な感覚に、頭の中がいっぱいいっぱいになる。
これまで保護者然とした態度をくずさなかったグレンが、急に男という別の生き物になってしまったかのようだ。それでも相手がグレンだと思えば、いやとは感じなかった。
否、むしろヨゼーファの胸までも愛欲の期待に高まってしまう。
無垢でありながら成熟しつつある身体が、淫らな口づけのもたらす愉悦に、ぞくぞくとふるえてしまう。
「…はぁっ、グレン…っ」
キスの合間に切なく名前を呼ぶと、彼はなぜか眉間に皺を寄せて応じた。
「そんな…蕩けた顔で見るな――止まらなくなる」
「グレン、好きよ…」
後から後から湧き出す気持ちを抑えきれずに伝えると、くちびるがふたたび情熱的にふさがれる。
ヨゼーファに負けず劣らず、迸る気持ちをそのまま注ぎ込んでくるかのような、夢中に舌を絡め、舐り尽くした末に吸い上げる濃密な交歓に、たちまち心まで蕩けて何も考えられなくなる。
その間にグレンの手は胸元へすべり、その部分をまさぐろうとした。
しかしそこには固いコルセットがあるのみ。
ややあって彼は顔を離し、その部分を見下ろした。
「これはどうすれば…」
「脱がすの? それなら背中のリボンをほどいてくれれば…」
「そ、そうか…」
身につけているドレスは、背中でリボンを編み上げることで上部を固定する形である。交差しているリボンをほどいてしまえば、ドレスの上半分は脱がせることができる。
グレンは、前から抱きかかえるようにして作業に取りかかった。
その間ヨゼーファは、いつにない密着具合に、彼の腕の中でずっとドキドキしっぱなしだった。
今の時点ですでに心臓が壊れそうなのに、さらに先に進むなど、どうなってしまうのだろう?
跳ねまわる鼓動にぎゅっと目をつぶったところで、ドレスが半分脱がされる。
肩と腕が剥き出しになる感覚にそっと目を開けたところ、グレンはコルセットを見下ろしていた。
「…外す?」
いちおう訊いてみると、彼は難しい顔でうめく。
「元に戻せる自信がない」
青灰色の目は、コルセットに押しつぶされ、まろやかに盛り上がるふくらみを、食い入るように見つめていた。
「…だいたい、気長にあれこれできるほど悠長な状態でもない」
そう言うや、彼はコルセットの上部で押し上げられている胸にくちびるを寄せてきた。白い双丘に恭しく口づけた後、引っ張り出して大きな手で包み込んでくる。
むっちりとした柔肉が彼の指の形にたわむ様は、我が事ながら、ひどく扇情的な眺めだった。無骨な手に押しまわされるたび、白い胸はやわらかく形を変えていく。
「――っ、…ぁ…っ」
こめかみで鼓動がどきどきと強く脈打つ。顔が熱く火照り、息が上がった。
彼の手にふれられていると考えるだけで、包み込まれた場所から、甘い感覚がさざめきのように広がっていく。優しい手つきで揉みしだかれることには、不思議な高揚感があった。
同時に手のひらにこすれた先端が、じんじんと疼き始める。
くすぐったいというよりも、ひどく悩ましい感覚に、ヨゼーファの肩がぴくんっと跳ねてしまう。
「…ぁ、…ぁ…っ」
甘い刺激に上体をひくつかせながら、涙目で見上げると、彼はふと手を止めた。
「痛いか? すまない。…やわらかすぎて、力の加減がわからない」
首を横にふる。
「痛くなんかないわ。…その逆で…」
グレンにさわられるとドキドキする。しかしながら先端の部分が、なぜかうずうずするのだ。
率直に伝えると、彼は「そ、そうか…」と照れたように頬を赤らめた。
そうしながらも、ぷっくりと勃ち上がったそこを指でつまんでくる。
くりくりと捏ねるようにいじられ、「んっ…」とうめいた。すると彼はふくらみを寄せ上げ、ぽっちりと尖った両方の粒を、親指の腹でうにうにと刺激してくる。
「ぁ、あぁ…っ」
じんじんと疼く場所への刺激に、思わずか細い声がこぼれる。
指が、円を描くように動くごとに身体の力が抜けていった。
「…やぁ…ぁっ…ぁ…っ」
上気した眦に官能の涙が浮かぶ。
「いいのか?」
かすれて艶めく彼の声にまで、腰のあたりがぞくぞくとわななく。
信じられないほどいやらしい感覚に包まれ、身体はどこまでも火照っていった。
「グレン、…グレン…っ」
事情を訊くと、閣議が何日も紛糾し続け、寝る間を惜しんで調整を続けているものの、解決の糸口が見つからないのだという。
ヨゼーファはその時、彼をいつものテーブルではなく、三人掛けのソファに誘った。
そして片端に腰を下ろすと、少し離れたところに座ったグレンに向けて、自分のひざを軽くたたいて言ったのである。
「ここに頭をのせて、寝て?」
「…………」
よかれと思って申し出たというのに、彼は言葉もなく硬直したきりだった。
その顔は、控えめに見ても混乱の際に達しているようだ。いつも鋭く輝いている青灰色の瞳が、焦点を探してさまよう。
ややあって彼は鈍い反応を見せた。
「……は?」
ヨゼーファはふたたび自分の膝を軽くたたく。
それは昔、何かいやなことがあって落ち込むヨゼーファを甘やかすときに、姉がしてくれたことだった。
姉の膝に頭を預けて横になると、人の体温と優しさに包まれるようで、安心して眠ることができた。
よってヨゼーファは、思いやりを込めて彼を見つめる。
「今日はわたしとおしゃべりしなくていいわ。ここにいる間だけでも横になって休んで」
「その…気持ちはありがたいが…」
「クッションがないから、わたしのひざを提供するわ。婚約しているんだもの。そのくらい問題ないでしょう?」
「…いや、だいぶ問題だ。やめておく」
その返答は予想外だった。
「待って…っ」
ソファから腰を上げようとした彼の腕を、ヨゼーファはあわててつかむ。
「あきれた? 馴れ馴れしくするつもりはなかったの。ただ、あなたのために何かしたかっただけで…っ」
しかしグレンは、頑なにドアに目を向けて言った。
「今日は帰る」
「グレン…っ」
「放してくれ。俺は、…なんていうか…疲れていると逆に我慢できなくなるたちで…」
言っていることの意味がよく分からない。
だが自分が彼を不快にさせたことだけは、まちがいなさそうだ。
どうすれば機嫌を直してくれるのか必死に考えている間にも、グレンは「放してくれ」と言いながら、ヨゼーファの手を自分で振り払う。
こんなふうに拒絶されるのは初めてだった。
「ごめんなさい、グレン…!」
振り払われたヨゼーファは、ドアへと向かいかけた彼の背中に、思わず腕をまわしてしがみつく。
後ろから抱きしめるようにして、ぴったりとくっつく。
「悪気はなかったの。あなたのことが好きだから、役に立ちたくて…っ」
頬を押しつけた彼の背中から、ごくりとツバを飲みこむ音が聞こえてきた。
「…放せ」
「許すって言って。お願い――」
「許す! 許すから…っ」
ヨゼーファの懇願に、グレンはひどく動揺した声音で応じた。そして自分を抱きしめる両手をつかみ、力まかせに引きはがす。
自分を落ち着かせるように息をついた彼は、やがてヨゼーファをふり向き――そのとたん、ぎょっとしたように目を見開いた。
「なっ、なぜ泣く?」
「泣いてないわ」
「だが…」
グレンは、ゆっくりとソファの前にひざをつき、こちらの顔をのぞきこんでくる。
そしてヨゼーファの目尻に浮かんだ涙を、長い指でぬぐってくる。
「泣いてないわ。ただ…グレンが怒ったのかと思って、ちょっと心配になっただけ」
「怒るわけないだろう。こんなことで」
「本当?」
うるんだ目で彼を見つめ、ヨゼーファは「よかった…」とほほ笑んだ。
そのくちびるに――ふらふらと、吸い寄せられるようにグレンが口づけてくる。
「……っ」
くちびるに感じた優しい感触に、ヨゼーファは目を瞠った。
その間にも、二回、三回と、くり返し押し当てられてくる。
(…キスしてる…)
ずっと好きだった人と、口づけを交わしている。その感動に頭が沸いてしまう。
と、彼はハッと我に返ったように顔を離した。
「す、すまない! つい…っ」
謝罪に、ヨゼーファは大きく首を横に振る。
「どうして謝るの? うれしかったのに…」
グレンは、信じられないというようにヨゼーファをじっと見つめた後、かすれた声で訊ねてきた。
「……本当か?」
「えぇ」
はっきりとうなずく――や否や、いっそう強くくちびるが重ねられてくる。
それは、はじめのうちは様子を探るように慎重な動きだった。しかしヨゼーファが逃げないでいるうちに、次第に熱を帯びていく。
くちびるをこすり合わせ、食み合っていたものが、やがて隙間から舌が押し込まれてくるに至って、思わぬ感触にくぐもったうめき声がもれる。
「…ん…ぅ…っ」
気がつけば彼は、ソファの背もたれにヨゼーファの頭を押しつけ、貪るようにして口づけに夢中になっていた。
ヨゼーファはといえば、受けとめるだけで精一杯である。されるがままになりながら、身体の中までまさぐられるような、ひどく淫蕩な感覚に、頭の中がいっぱいいっぱいになる。
これまで保護者然とした態度をくずさなかったグレンが、急に男という別の生き物になってしまったかのようだ。それでも相手がグレンだと思えば、いやとは感じなかった。
否、むしろヨゼーファの胸までも愛欲の期待に高まってしまう。
無垢でありながら成熟しつつある身体が、淫らな口づけのもたらす愉悦に、ぞくぞくとふるえてしまう。
「…はぁっ、グレン…っ」
キスの合間に切なく名前を呼ぶと、彼はなぜか眉間に皺を寄せて応じた。
「そんな…蕩けた顔で見るな――止まらなくなる」
「グレン、好きよ…」
後から後から湧き出す気持ちを抑えきれずに伝えると、くちびるがふたたび情熱的にふさがれる。
ヨゼーファに負けず劣らず、迸る気持ちをそのまま注ぎ込んでくるかのような、夢中に舌を絡め、舐り尽くした末に吸い上げる濃密な交歓に、たちまち心まで蕩けて何も考えられなくなる。
その間にグレンの手は胸元へすべり、その部分をまさぐろうとした。
しかしそこには固いコルセットがあるのみ。
ややあって彼は顔を離し、その部分を見下ろした。
「これはどうすれば…」
「脱がすの? それなら背中のリボンをほどいてくれれば…」
「そ、そうか…」
身につけているドレスは、背中でリボンを編み上げることで上部を固定する形である。交差しているリボンをほどいてしまえば、ドレスの上半分は脱がせることができる。
グレンは、前から抱きかかえるようにして作業に取りかかった。
その間ヨゼーファは、いつにない密着具合に、彼の腕の中でずっとドキドキしっぱなしだった。
今の時点ですでに心臓が壊れそうなのに、さらに先に進むなど、どうなってしまうのだろう?
跳ねまわる鼓動にぎゅっと目をつぶったところで、ドレスが半分脱がされる。
肩と腕が剥き出しになる感覚にそっと目を開けたところ、グレンはコルセットを見下ろしていた。
「…外す?」
いちおう訊いてみると、彼は難しい顔でうめく。
「元に戻せる自信がない」
青灰色の目は、コルセットに押しつぶされ、まろやかに盛り上がるふくらみを、食い入るように見つめていた。
「…だいたい、気長にあれこれできるほど悠長な状態でもない」
そう言うや、彼はコルセットの上部で押し上げられている胸にくちびるを寄せてきた。白い双丘に恭しく口づけた後、引っ張り出して大きな手で包み込んでくる。
むっちりとした柔肉が彼の指の形にたわむ様は、我が事ながら、ひどく扇情的な眺めだった。無骨な手に押しまわされるたび、白い胸はやわらかく形を変えていく。
「――っ、…ぁ…っ」
こめかみで鼓動がどきどきと強く脈打つ。顔が熱く火照り、息が上がった。
彼の手にふれられていると考えるだけで、包み込まれた場所から、甘い感覚がさざめきのように広がっていく。優しい手つきで揉みしだかれることには、不思議な高揚感があった。
同時に手のひらにこすれた先端が、じんじんと疼き始める。
くすぐったいというよりも、ひどく悩ましい感覚に、ヨゼーファの肩がぴくんっと跳ねてしまう。
「…ぁ、…ぁ…っ」
甘い刺激に上体をひくつかせながら、涙目で見上げると、彼はふと手を止めた。
「痛いか? すまない。…やわらかすぎて、力の加減がわからない」
首を横にふる。
「痛くなんかないわ。…その逆で…」
グレンにさわられるとドキドキする。しかしながら先端の部分が、なぜかうずうずするのだ。
率直に伝えると、彼は「そ、そうか…」と照れたように頬を赤らめた。
そうしながらも、ぷっくりと勃ち上がったそこを指でつまんでくる。
くりくりと捏ねるようにいじられ、「んっ…」とうめいた。すると彼はふくらみを寄せ上げ、ぽっちりと尖った両方の粒を、親指の腹でうにうにと刺激してくる。
「ぁ、あぁ…っ」
じんじんと疼く場所への刺激に、思わずか細い声がこぼれる。
指が、円を描くように動くごとに身体の力が抜けていった。
「…やぁ…ぁっ…ぁ…っ」
上気した眦に官能の涙が浮かぶ。
「いいのか?」
かすれて艶めく彼の声にまで、腰のあたりがぞくぞくとわななく。
信じられないほどいやらしい感覚に包まれ、身体はどこまでも火照っていった。
「グレン、…グレン…っ」