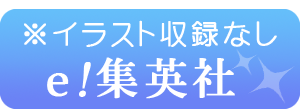後宮禁愛
寵姫は秘密の愛に蕩ける
京極れな イラスト/綺羅かぼす
「ああ、もう……この身体は、私のものだ……」
火照った身体をかき抱き、遼宇がくるおしげにつぶやく。
「でも……遼宇さま……、常寿帝が……」
莉瑛は息苦しいほどの抱擁の中でつぶやく。
――常寿帝がそれを許さない。
「いいのです。……ほかの男のことなど……忘れてしまえ……」
剛直を呑み込ませながら告げる。父帝などとうに凌駕したような、それでいてどこか苛立ちの滲んだやるせない声音で。
彼にもやはり理性が戻っているのだろうか、よくわからない。
「はぁ、はぁぅ、はぁっ、ンっ、あぁ……っ」
硬く張りつめたものが出入りするたびに、ずちゅ、ずちゅと蜜音がたつ。
気持ちよすぎて、息が苦しい。愛し合うということは、こうも苦しいものなのだろうか。素肌に残された花びらのような痕が、罪の烙印のように思えてつらくなってくる。
それでも背中合わせにある快楽が、ふたりの行為をさらに危うく、濃密にしてゆく。
「はっ、あ、あ……っ、ああっ、あぁっ、ああ……っ」
何度も突きあげられ、そのうちにまた絶頂の波が訪れた。
「あ、あ、あぁ……またなの……」
莉瑛が遼宇にしがみつくようにして短く告げると、遼宇はそれを促すかのように、わざといいところを狙って穿ってくる。
「私もだ……」
熱い声が耳朶をうつ。身体がひとつに蕩けてしまうような心地よい錯覚に陥る。そして、
「あっ、あっ、ああぁっ」
甘い囁きと巧みな性技に誘われ、ほどなく莉瑛は絶頂にうちあげられた。
同時に彼がどくどくと莉瑛の中で果てるのがわかった。
いったい何度、頂に達するというのだろう。それでも身体はじりじりと疼き続けたままだ。
「香のせいだわ……」
莉瑛はとめどない淫欲に、めまいをおぼえながらつぶやく。
「ええ……」
遼宇のほうもそれはおなじようで、抜かずに、そのままふたたびゆっくりと腰を遣いはじめる。
「あ」
吐精して威勢を失いかけたはずのものが、また硬く勃起していて、莉瑛は目をみはった。
「欲望が尽きないな……、何度でも……あなたが欲しくてたまらない……」
耳元で呻くようにつぶやかれたと思うと、そのまま唇を奪われた。
「ふ……」
唇を割って濡れた舌が入ってきて、さらなる情欲を訴えてくる。
「ン……ぅ……」
陽根を挿入された状態で唇を貪られていると、達して間もない莉瑛の身体もたちまち熱く濡れてきた。
(ほんとうに……また……)
硬くなった陰茎が、濡れた隘路をゆるやかに行き来している。
達したばかりで敏感な媚壁には、そのくらいの動きのほうが気持ちよい。
汗ばみはじめた互いの身体から、香の匂いに混じって官能的な香りがたちのぼる。
「ん……ぁ……」
上からも下からも甘く攻められて、身体が芯から蕩けて崩れてしまいそうだ。
「ああ……気持ちいい……、もっと好きにしていいですか……?」
口づけの角度を変えながら、吐息混じりの甘い声で問われる。
「まだまだあなたを抱き足らない……もっと激しくしたい……」
「いいの。……して。たくさん抱いて……」
口づけの合間に、莉瑛もせがんだ。求められれば求められるほどに官能が湧いて、身体が熱く反応してしまう。
だしぬけに、遼宇が莉瑛の身体を腹ばいにさせた。
「や……なにを……」
莉瑛が我に返って目を丸くしていると、背後から腰を摑まれ、臀部の割れ目に勃起した彼のものが押しあてられた。
「あ……こんな体勢……」
まるで獣同士の交尾のような。
莉瑛の中に、以前、貴妃に仕える宮女から貰った春画がよみがえった。あの絵のふたりは、こんな姿で交わっていなかったか――。
けれども熱い男根がうしろから花びらのあたり到達すると、甘い感覚が生じてすぐにその気にさせられた。
「はぁ……ン……」
怒張で濡れそぼった蜜口をなぞられて、痺れるような快感がせりあがってくる。
「こんな体勢は嫌ですか?」
遼宇は後方から伸ばした手で、濡れた花芯のふくらみを愛撫しだす。
「あ……んっ……、そこは……」
まだ感度が高まったままだ。
「これを弄られるのが好きなのでしょう……?」
遼宇は陰核の莢を払ってぐりぐりと押しまわす。
「ン、あ、あっ……、あンっ、これ、だめ……」
官能を引き出す巧みな指遣いに、あらたな愛液が溢れてくる。
まだ挿入はされない。だから内奥がじりじりと焦れてくる。
「私を欲しがっているのは……ここでしたか……?」
遼宇は花芯への愛撫はそのままに、花びらに沿って、ゆっくりと陰茎を行き来させる。
「ん……、あ……」
亀頭のくびれが、敏感になっている柔襞にぬるい快感をもたらす。
「あ、ン……焦らさ……ないで……」
莉瑛ははやく奥まで来てほしくて、下肢をふるわせる。うしろからなんてはじめてで、未知の快感に背筋までがぞくぞくしてくる。
「いやらしく尻を突き出して、そんなに私が欲しいのですね……」
遼宇が身を屈め、耳元で煽ってくる。
「ン……欲しい……、はやく、挿れて……」
莉瑛はもはや、欲望を抑える気はなくて、思いのままに彼を求めてしまう。
「そんな甘い声でねだって……、たまらないな……」
遼宇は昂りを抑えられなくなり、剛直を背後からゆっくりと埋めてきた。
「ん……」
莉瑛は敷布を握りしめた。
「あ、ン……奥……まで、きて……」
さきほどまでとは異なる体位なので、抵抗が強い。けれど背中に密着した逞しい胸筋を感じていると、身体はふたたび熱くほどけてゆく。
「……色っぽい眺めだ。……あなたのなめらかな臀部の奥に、私のものが沈んでゆくさまが見える……」
遼宇が愛撫を花芯から臀部に移しながら、後方から囁いてくる。
そして腰を摑まれ、ぐっと後方から最奥までを貫かれた。
「あぁっ……」
硬く太いものに隘路を満たされ、思わず深い溜め息がこぼれた。
そこからは、遼宇のしたいままに貪られた。
半身を起こして腰を抱え、後方からずぷずぷと勢いよく突きこんでくる。
「はぁ、あっ、あぁっ、あぅ、あンっ……」
あの春画を見たときは野蛮だと思ったけれど、愛しい男に好き放題にされるのは、なぜか心地よくて、みるみる性感が高まってくる。
「はっ、はぁっ、はぅ、あっ、あぁっ、遼宇、さま……、激し……」
荒々しい腰遣いに煽られて、莉瑛も背をのけぞらせて喘ぐ。
どこまでも、どれだけでも感じてしまう。身体がおかしくなるほどに。
遼宇がふたたび身を屈め、背後から回した手で、ぎゅうと乳房を摑んできた。
「あなたは……父上の女なのだな……」
苦々しい声が耳朶をうつ。
ようやく遼宇も、そこまで意識が清澄になったのか。
「そうよ……、あなたは……皇帝の寵妃を抱いている……、何度も……」
莉瑛も乱れた息を吐きながら返す。
会うことを禁じられたはずのふたりなのに、なんと罪深いことだろう。
自分が常寿帝の寵妃などではなければよかったのに。
遼宇に見初められた、ただの女官だったらよかったのに。
火照った身体をかき抱き、遼宇がくるおしげにつぶやく。
「でも……遼宇さま……、常寿帝が……」
莉瑛は息苦しいほどの抱擁の中でつぶやく。
――常寿帝がそれを許さない。
「いいのです。……ほかの男のことなど……忘れてしまえ……」
剛直を呑み込ませながら告げる。父帝などとうに凌駕したような、それでいてどこか苛立ちの滲んだやるせない声音で。
彼にもやはり理性が戻っているのだろうか、よくわからない。
「はぁ、はぁぅ、はぁっ、ンっ、あぁ……っ」
硬く張りつめたものが出入りするたびに、ずちゅ、ずちゅと蜜音がたつ。
気持ちよすぎて、息が苦しい。愛し合うということは、こうも苦しいものなのだろうか。素肌に残された花びらのような痕が、罪の烙印のように思えてつらくなってくる。
それでも背中合わせにある快楽が、ふたりの行為をさらに危うく、濃密にしてゆく。
「はっ、あ、あ……っ、ああっ、あぁっ、ああ……っ」
何度も突きあげられ、そのうちにまた絶頂の波が訪れた。
「あ、あ、あぁ……またなの……」
莉瑛が遼宇にしがみつくようにして短く告げると、遼宇はそれを促すかのように、わざといいところを狙って穿ってくる。
「私もだ……」
熱い声が耳朶をうつ。身体がひとつに蕩けてしまうような心地よい錯覚に陥る。そして、
「あっ、あっ、ああぁっ」
甘い囁きと巧みな性技に誘われ、ほどなく莉瑛は絶頂にうちあげられた。
同時に彼がどくどくと莉瑛の中で果てるのがわかった。
いったい何度、頂に達するというのだろう。それでも身体はじりじりと疼き続けたままだ。
「香のせいだわ……」
莉瑛はとめどない淫欲に、めまいをおぼえながらつぶやく。
「ええ……」
遼宇のほうもそれはおなじようで、抜かずに、そのままふたたびゆっくりと腰を遣いはじめる。
「あ」
吐精して威勢を失いかけたはずのものが、また硬く勃起していて、莉瑛は目をみはった。
「欲望が尽きないな……、何度でも……あなたが欲しくてたまらない……」
耳元で呻くようにつぶやかれたと思うと、そのまま唇を奪われた。
「ふ……」
唇を割って濡れた舌が入ってきて、さらなる情欲を訴えてくる。
「ン……ぅ……」
陽根を挿入された状態で唇を貪られていると、達して間もない莉瑛の身体もたちまち熱く濡れてきた。
(ほんとうに……また……)
硬くなった陰茎が、濡れた隘路をゆるやかに行き来している。
達したばかりで敏感な媚壁には、そのくらいの動きのほうが気持ちよい。
汗ばみはじめた互いの身体から、香の匂いに混じって官能的な香りがたちのぼる。
「ん……ぁ……」
上からも下からも甘く攻められて、身体が芯から蕩けて崩れてしまいそうだ。
「ああ……気持ちいい……、もっと好きにしていいですか……?」
口づけの角度を変えながら、吐息混じりの甘い声で問われる。
「まだまだあなたを抱き足らない……もっと激しくしたい……」
「いいの。……して。たくさん抱いて……」
口づけの合間に、莉瑛もせがんだ。求められれば求められるほどに官能が湧いて、身体が熱く反応してしまう。
だしぬけに、遼宇が莉瑛の身体を腹ばいにさせた。
「や……なにを……」
莉瑛が我に返って目を丸くしていると、背後から腰を摑まれ、臀部の割れ目に勃起した彼のものが押しあてられた。
「あ……こんな体勢……」
まるで獣同士の交尾のような。
莉瑛の中に、以前、貴妃に仕える宮女から貰った春画がよみがえった。あの絵のふたりは、こんな姿で交わっていなかったか――。
けれども熱い男根がうしろから花びらのあたり到達すると、甘い感覚が生じてすぐにその気にさせられた。
「はぁ……ン……」
怒張で濡れそぼった蜜口をなぞられて、痺れるような快感がせりあがってくる。
「こんな体勢は嫌ですか?」
遼宇は後方から伸ばした手で、濡れた花芯のふくらみを愛撫しだす。
「あ……んっ……、そこは……」
まだ感度が高まったままだ。
「これを弄られるのが好きなのでしょう……?」
遼宇は陰核の莢を払ってぐりぐりと押しまわす。
「ン、あ、あっ……、あンっ、これ、だめ……」
官能を引き出す巧みな指遣いに、あらたな愛液が溢れてくる。
まだ挿入はされない。だから内奥がじりじりと焦れてくる。
「私を欲しがっているのは……ここでしたか……?」
遼宇は花芯への愛撫はそのままに、花びらに沿って、ゆっくりと陰茎を行き来させる。
「ん……、あ……」
亀頭のくびれが、敏感になっている柔襞にぬるい快感をもたらす。
「あ、ン……焦らさ……ないで……」
莉瑛ははやく奥まで来てほしくて、下肢をふるわせる。うしろからなんてはじめてで、未知の快感に背筋までがぞくぞくしてくる。
「いやらしく尻を突き出して、そんなに私が欲しいのですね……」
遼宇が身を屈め、耳元で煽ってくる。
「ン……欲しい……、はやく、挿れて……」
莉瑛はもはや、欲望を抑える気はなくて、思いのままに彼を求めてしまう。
「そんな甘い声でねだって……、たまらないな……」
遼宇は昂りを抑えられなくなり、剛直を背後からゆっくりと埋めてきた。
「ん……」
莉瑛は敷布を握りしめた。
「あ、ン……奥……まで、きて……」
さきほどまでとは異なる体位なので、抵抗が強い。けれど背中に密着した逞しい胸筋を感じていると、身体はふたたび熱くほどけてゆく。
「……色っぽい眺めだ。……あなたのなめらかな臀部の奥に、私のものが沈んでゆくさまが見える……」
遼宇が愛撫を花芯から臀部に移しながら、後方から囁いてくる。
そして腰を摑まれ、ぐっと後方から最奥までを貫かれた。
「あぁっ……」
硬く太いものに隘路を満たされ、思わず深い溜め息がこぼれた。
そこからは、遼宇のしたいままに貪られた。
半身を起こして腰を抱え、後方からずぷずぷと勢いよく突きこんでくる。
「はぁ、あっ、あぁっ、あぅ、あンっ……」
あの春画を見たときは野蛮だと思ったけれど、愛しい男に好き放題にされるのは、なぜか心地よくて、みるみる性感が高まってくる。
「はっ、はぁっ、はぅ、あっ、あぁっ、遼宇、さま……、激し……」
荒々しい腰遣いに煽られて、莉瑛も背をのけぞらせて喘ぐ。
どこまでも、どれだけでも感じてしまう。身体がおかしくなるほどに。
遼宇がふたたび身を屈め、背後から回した手で、ぎゅうと乳房を摑んできた。
「あなたは……父上の女なのだな……」
苦々しい声が耳朶をうつ。
ようやく遼宇も、そこまで意識が清澄になったのか。
「そうよ……、あなたは……皇帝の寵妃を抱いている……、何度も……」
莉瑛も乱れた息を吐きながら返す。
会うことを禁じられたはずのふたりなのに、なんと罪深いことだろう。
自分が常寿帝の寵妃などではなければよかったのに。
遼宇に見初められた、ただの女官だったらよかったのに。