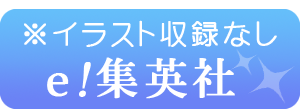黒伯爵のティーメイド
とろとろりんごを召し上がれ
依田ザクロ イラスト/三浦ひらく
うららかな初春のころ、ノワール伯爵邸の庭園には、まるで地平線まで絨毯を敷き詰めたように花が咲き乱れていた。
中央に堂々と備わる噴水は白い大理石製。水面には太陽のきらめきが照り映え、天高く噴き上げる水は空の青さと溶け合っている。
噴水を眺めるようにして真っ白なクロスの敷かれたティーテーブルがある。
ここでミレイユは、屋敷の主であるアルフォンスにティーメイドとしてアフタヌーンティーを提供していたはずだった。
なのに、どうしてこんなことに?
今、ミレイユは椅子ではなく、テーブルへ座らされている。しかも、ただ座っているだけではない。サーモンピンクのエプロンドレスの裾を大きくまくり上げ、ドロワーズを取り去り、両腿を大きく開いていた。
つまり、正面の椅子に座るアルフォンスの眼前へ秘部をさらした状態である。
ミレイユが後ろ手をつくテーブルの上には、色とりどりのお菓子がのっていた。薔薇色のゼリー、ピスタチオのシャーベット、いちじくのペースト、ショコラ味のキャンディ、ガラスの器に盛られたダークチェリーのキルシュ漬け……、それらに交じって座っていると、自分までお菓子の仲間入りをした気分になってしまう。
「こんなの……いや、です」
羞恥に消え入る声で訴えるが、アルフォンスはそっけない声で言う。
「いや? では約束を反故にするのか」
約束――それは、おいしい紅茶の淹れ方、茶葉の選び方、ブレンドの仕方などを紅茶商の彼から直々に指導してもらう代わり、失敗したらおしおきを受けるというもの。
ティーメイドとして、紅茶は上手に淹れなければならない。いや、義務以上にミレイユ自身がうまくなりたいのだ。
得意のお菓子作りに加えて、紅茶に関する知識や淹れる技術を身につけたい。だから、どんなことでも受け入れると決めた。
ついさっきミレイユは、アルフォンスが遥か遠い東洋の大国から苦労して仕入れてきたキーマンの茶葉を、台無しにしたところだった。黒っぽい茶葉の色に気をとられて、水色を濃く出し過ぎた。そのせいで、蘭のごとく上品なスモーキーフレーバーがどんよりとした味になってしまったのだ。
おまけに彼は、仕事でたいへん忙しい中、ミレイユに付き合ってくれている。指導だけ受けておしおきは拒むなんて、わがままが過ぎるだろう。
「いいえ、ごめんなさい。約束は、そのままにしてください」
「続けるぞ」
アルフォンスは未使用のティーポットを手に取った。
自ら茶を淹れ、手本を見せてくれるつもりか――と思ったのもつかの間。
「……ひゃっ」
注ぎ口の先端で乙女の花園へふれてきた。
陶器のなめらかな感触と冷たさにぶるりと体を震わせる。
「なにを……、なさる、の……、ぁ……」
彼は花の開き具合を確かめるように、花弁をつついてくる。
はじめは違和感しかなかった。けれど、緩慢な動作で恥丘を押し上げられていくうち、そこが妙な熱を持ち始める。
「水音がしないか? おかしいな、ティーポットは空のはずなのに」
「やぁ……っ」
陶器がふれるたび、くちゅ、くちゅと立つ淫らな音は、ティーポットに注がれたお湯が立てるものではない。官能の泉から生まれた蜜液がなせるわざだった。
「なるほど、この湿り気はおまえのものか」
白々しく指摘される。
ミレイユはかあっと頬を染めた。
恥ずかしい。こんなのへんよ。
蜜口が疼いて、じっとしていられない。
もどかしさに腰を動かしたくなってしまう。
「んっ、あ、ああ……っ」
閉じてはいけないと己を戒めつつ膝を震わせ、花びらをひくつかせる。
ミレイユに与えられているのはおしおきだ。
彼がこんなことをするのは、めまいがするほどの恥ずかしさを身に刻ませて、次は失敗をしないようにさせるためである。
だから、これは屈辱的な行為のはず。
なのに、体は嫌がるどころか、まるで歓迎しているみたいに蜜をこぼす。
「ふ……、ぅう……、ん……」
快感の萌芽を認めまいと、唇をかみしめる。
けれども次の瞬間、偶然かわざとか、陶器が無防備な花芽をかすめた。
大きな戦慄が脳天へと駆け上がる。
「あぁあぁぁんっ」
自分のものとは思えない甘ったるい声が鼻へ抜ける。
「どうした」
「んあ……っ、そこ、は、……っ! あぁ……っ」
アルフォンスは陰核をぐいぐいと押してくる。
鮮烈な淫悦が弾けた。
さっきまではにじむ程度だった蜜があふれ出す。辺りに響く粘着質な音は聞くに堪えないほど大きい。
陶器の先端は蜜のぬめりを借りて花芽の上を滑る。喜悦が大きくなっていくとともに、そこは赤く膨らんで育っていった。
甘苦しい熱に浮かされ、頭がぼんやりとしてくる。
そのうち、注ぎ口の穴がぴたりと突起にはまった。
「……っ!?」
あまりの刺激に、喉の奥が詰まって声が出ない。
アルフォンスの手はゆっくりと円を描く。
注ぎ口にすっぽり入った花芽はぐりぐりと押しつぶされ、引きつれるふうに花弁がこねまわされた。
信じられないほどの歓喜の渦が襲ってくる。
「きゃぁ……ああんっ、あ、あ、だめ、やぁ……っ、止めて、手、止めてくださ……ぁいっ」
呼吸を乱して懇願する。
けれども彼は止まらない。冷静な口調でさっきと同じ質問を繰り返す。
「では約束を反故にするのか」
「それは……っ」
「おまえは俺のティーメイドで、上手な紅茶の淹れ方が知りたい。教えてやる代わりに、失敗したらおしおきを受けるはずだろう」
「そうです、どんな、おしおきでも……」
確かに約束した。
絶対に守ると誓ったのだ。だから、いやだなんて言ったらいけない。
「だったら、受け入れろ。ほら、体は素直に従っている。おしおきなのに気持ちよくなっているんだろう? こんなに蜜を垂らしているのだから」
気持ちがいい……?
そんなわけ、ないわ。
だけど、体が熱い。
追い詰められる。
「快楽に身をゆだねてしまえ。楽になれる」
静かなささやきは、まるで悪魔の誘惑だ。
ミレイユは喜悦の涙が浮かぶ瞳でアルフォンスを見つめた。
ストレートの短い黒髪に、全身黒衣で固めた彼は、普段は大人びているのに、今は違った顔を見せていた。
抑え込んでいる野性がにじみ出て、荒々しさが感じられる。
その左手が伸びてくる。
花芯をティーポットで刺激しつつ、素手で花弁にふれてきた。ほんのちょっと表面をなでられただけなのに、全身の毛穴が開くような感覚に襲われた。
「あ……っ、や……っぁ」
初めは慎重だった彼のふれ方は、徐々に大胆になってくる。
「あぁ……、や、ああ……っ、だめ、ぐちゃぐちゃに、なっちゃう……っ」
空気を含ませて花弁をかき回すから、聞くに堪えない淫靡な音がひっきりなしに生まれてしまう。
わざと音を立てているのだろうか。
「本当だな。赤く膨らんで、どんどん蜜を吐き出している。テーブルクロスが大変なことになっているぞ」
後孔までぐっしょり濡れているのが自分でもわかる。尻の下に敷かれたテーブルクロスは湯をこぼしたように染みができているだろう。
「あ、あっ、恥ずかしい……っ」
両手で顔を覆う。
視界が遮られると、秘処で行われる淫戯がいっそう直截的に感じられた。
男性らしい指先が花弁を淫らにこね、蜜をさらにかき出している。そのすぐ上の快感の源は無機質な陶器の先端で無情にこねくり回されている。
極限なく膨らんでいく淫熱が、出口を求めて暴れている。
なすすべなく身をくねらせ、ミレイユは嬌声を上げ続けた。
「あああんっ、あ……んっ、あ……っく、うぅ……っ。だめ、……止まらないのっ、止めたいのに……」
このままでは壊れてしまうんじゃないかと不安になるほど、とめどなく蜜が流れる。
ダークチェリーのようなアルフォンスの赤い瞳が妖しくきらめいた。
「止めたいのか。ならば、蓋をしてやろう」
蓋?
訝しく思ってまぶたを開く。
彼はミレイユの花芯をいじり続けていたティーポットを握り直し、その先端を蜜口へ当ててきた。
「え……、ぁ……、ぃや……ぁっ」
中央に堂々と備わる噴水は白い大理石製。水面には太陽のきらめきが照り映え、天高く噴き上げる水は空の青さと溶け合っている。
噴水を眺めるようにして真っ白なクロスの敷かれたティーテーブルがある。
ここでミレイユは、屋敷の主であるアルフォンスにティーメイドとしてアフタヌーンティーを提供していたはずだった。
なのに、どうしてこんなことに?
今、ミレイユは椅子ではなく、テーブルへ座らされている。しかも、ただ座っているだけではない。サーモンピンクのエプロンドレスの裾を大きくまくり上げ、ドロワーズを取り去り、両腿を大きく開いていた。
つまり、正面の椅子に座るアルフォンスの眼前へ秘部をさらした状態である。
ミレイユが後ろ手をつくテーブルの上には、色とりどりのお菓子がのっていた。薔薇色のゼリー、ピスタチオのシャーベット、いちじくのペースト、ショコラ味のキャンディ、ガラスの器に盛られたダークチェリーのキルシュ漬け……、それらに交じって座っていると、自分までお菓子の仲間入りをした気分になってしまう。
「こんなの……いや、です」
羞恥に消え入る声で訴えるが、アルフォンスはそっけない声で言う。
「いや? では約束を反故にするのか」
約束――それは、おいしい紅茶の淹れ方、茶葉の選び方、ブレンドの仕方などを紅茶商の彼から直々に指導してもらう代わり、失敗したらおしおきを受けるというもの。
ティーメイドとして、紅茶は上手に淹れなければならない。いや、義務以上にミレイユ自身がうまくなりたいのだ。
得意のお菓子作りに加えて、紅茶に関する知識や淹れる技術を身につけたい。だから、どんなことでも受け入れると決めた。
ついさっきミレイユは、アルフォンスが遥か遠い東洋の大国から苦労して仕入れてきたキーマンの茶葉を、台無しにしたところだった。黒っぽい茶葉の色に気をとられて、水色を濃く出し過ぎた。そのせいで、蘭のごとく上品なスモーキーフレーバーがどんよりとした味になってしまったのだ。
おまけに彼は、仕事でたいへん忙しい中、ミレイユに付き合ってくれている。指導だけ受けておしおきは拒むなんて、わがままが過ぎるだろう。
「いいえ、ごめんなさい。約束は、そのままにしてください」
「続けるぞ」
アルフォンスは未使用のティーポットを手に取った。
自ら茶を淹れ、手本を見せてくれるつもりか――と思ったのもつかの間。
「……ひゃっ」
注ぎ口の先端で乙女の花園へふれてきた。
陶器のなめらかな感触と冷たさにぶるりと体を震わせる。
「なにを……、なさる、の……、ぁ……」
彼は花の開き具合を確かめるように、花弁をつついてくる。
はじめは違和感しかなかった。けれど、緩慢な動作で恥丘を押し上げられていくうち、そこが妙な熱を持ち始める。
「水音がしないか? おかしいな、ティーポットは空のはずなのに」
「やぁ……っ」
陶器がふれるたび、くちゅ、くちゅと立つ淫らな音は、ティーポットに注がれたお湯が立てるものではない。官能の泉から生まれた蜜液がなせるわざだった。
「なるほど、この湿り気はおまえのものか」
白々しく指摘される。
ミレイユはかあっと頬を染めた。
恥ずかしい。こんなのへんよ。
蜜口が疼いて、じっとしていられない。
もどかしさに腰を動かしたくなってしまう。
「んっ、あ、ああ……っ」
閉じてはいけないと己を戒めつつ膝を震わせ、花びらをひくつかせる。
ミレイユに与えられているのはおしおきだ。
彼がこんなことをするのは、めまいがするほどの恥ずかしさを身に刻ませて、次は失敗をしないようにさせるためである。
だから、これは屈辱的な行為のはず。
なのに、体は嫌がるどころか、まるで歓迎しているみたいに蜜をこぼす。
「ふ……、ぅう……、ん……」
快感の萌芽を認めまいと、唇をかみしめる。
けれども次の瞬間、偶然かわざとか、陶器が無防備な花芽をかすめた。
大きな戦慄が脳天へと駆け上がる。
「あぁあぁぁんっ」
自分のものとは思えない甘ったるい声が鼻へ抜ける。
「どうした」
「んあ……っ、そこ、は、……っ! あぁ……っ」
アルフォンスは陰核をぐいぐいと押してくる。
鮮烈な淫悦が弾けた。
さっきまではにじむ程度だった蜜があふれ出す。辺りに響く粘着質な音は聞くに堪えないほど大きい。
陶器の先端は蜜のぬめりを借りて花芽の上を滑る。喜悦が大きくなっていくとともに、そこは赤く膨らんで育っていった。
甘苦しい熱に浮かされ、頭がぼんやりとしてくる。
そのうち、注ぎ口の穴がぴたりと突起にはまった。
「……っ!?」
あまりの刺激に、喉の奥が詰まって声が出ない。
アルフォンスの手はゆっくりと円を描く。
注ぎ口にすっぽり入った花芽はぐりぐりと押しつぶされ、引きつれるふうに花弁がこねまわされた。
信じられないほどの歓喜の渦が襲ってくる。
「きゃぁ……ああんっ、あ、あ、だめ、やぁ……っ、止めて、手、止めてくださ……ぁいっ」
呼吸を乱して懇願する。
けれども彼は止まらない。冷静な口調でさっきと同じ質問を繰り返す。
「では約束を反故にするのか」
「それは……っ」
「おまえは俺のティーメイドで、上手な紅茶の淹れ方が知りたい。教えてやる代わりに、失敗したらおしおきを受けるはずだろう」
「そうです、どんな、おしおきでも……」
確かに約束した。
絶対に守ると誓ったのだ。だから、いやだなんて言ったらいけない。
「だったら、受け入れろ。ほら、体は素直に従っている。おしおきなのに気持ちよくなっているんだろう? こんなに蜜を垂らしているのだから」
気持ちがいい……?
そんなわけ、ないわ。
だけど、体が熱い。
追い詰められる。
「快楽に身をゆだねてしまえ。楽になれる」
静かなささやきは、まるで悪魔の誘惑だ。
ミレイユは喜悦の涙が浮かぶ瞳でアルフォンスを見つめた。
ストレートの短い黒髪に、全身黒衣で固めた彼は、普段は大人びているのに、今は違った顔を見せていた。
抑え込んでいる野性がにじみ出て、荒々しさが感じられる。
その左手が伸びてくる。
花芯をティーポットで刺激しつつ、素手で花弁にふれてきた。ほんのちょっと表面をなでられただけなのに、全身の毛穴が開くような感覚に襲われた。
「あ……っ、や……っぁ」
初めは慎重だった彼のふれ方は、徐々に大胆になってくる。
「あぁ……、や、ああ……っ、だめ、ぐちゃぐちゃに、なっちゃう……っ」
空気を含ませて花弁をかき回すから、聞くに堪えない淫靡な音がひっきりなしに生まれてしまう。
わざと音を立てているのだろうか。
「本当だな。赤く膨らんで、どんどん蜜を吐き出している。テーブルクロスが大変なことになっているぞ」
後孔までぐっしょり濡れているのが自分でもわかる。尻の下に敷かれたテーブルクロスは湯をこぼしたように染みができているだろう。
「あ、あっ、恥ずかしい……っ」
両手で顔を覆う。
視界が遮られると、秘処で行われる淫戯がいっそう直截的に感じられた。
男性らしい指先が花弁を淫らにこね、蜜をさらにかき出している。そのすぐ上の快感の源は無機質な陶器の先端で無情にこねくり回されている。
極限なく膨らんでいく淫熱が、出口を求めて暴れている。
なすすべなく身をくねらせ、ミレイユは嬌声を上げ続けた。
「あああんっ、あ……んっ、あ……っく、うぅ……っ。だめ、……止まらないのっ、止めたいのに……」
このままでは壊れてしまうんじゃないかと不安になるほど、とめどなく蜜が流れる。
ダークチェリーのようなアルフォンスの赤い瞳が妖しくきらめいた。
「止めたいのか。ならば、蓋をしてやろう」
蓋?
訝しく思ってまぶたを開く。
彼はミレイユの花芯をいじり続けていたティーポットを握り直し、その先端を蜜口へ当ててきた。
「え……、ぁ……、ぃや……ぁっ」