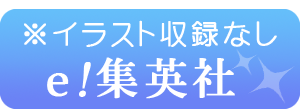溺愛の刑に処す
京極れな イラスト/八千代ハル
閉ざしていたはずの両脚からは、すっかりと力が抜けていた。
これが世に言う快楽に耽るということなのだろうか。自分の身体までもがこんなふうになってしまうなんて、リゼットは知らなかった。貞操を守らねばならないというのに、このままでは快感に身を委ねてしまいそうだ。
「も、もう……さわら、ないで……」
リゼットは掠れたかぼそい声で言う。五感が秘所にもっていかれ、言葉もまともに紡げなくなってゆく。
「あ……や……、やめ……、ン……」
リゼットはシャルルの指遣いに反応して、ぴくぴくと内腿を震わせる。
「感じてるね。だんだんここが硬くなってきたみたいだ、ほら、僕にさわってくれって訴えてるよ」
シャルルが言いながら、花芯を指の腹で小刻みに揺さぶる。
「あ、あ、あぁ、や、だめ……これ……ン、はぁ、はぁ……っ」
痺れるような快感がくりかえしせりあがってきて、下腹部に力が入ってしまう。
リゼットははぁはぁと熱い息をこぼしながら、ドレスを握りしめる。
「息が乱れてきたね、リゼット。……頬も薔薇のように染まって色っぽいな、キスしたい」
言うなり、シャルルが口づけてきた。
「ん……」
遠慮のない口づけだった。かさねあわせてすぐに、唇の隙間から、ぬっと舌を入れられた。
熱い塊に、口内をぐるりと蹂躙される。
いつもより荒々しく性急な感じで、そのことがリゼットを昂らせた。
「ン……ぅ……」
舌をとらえ、卑猥に絡めあわせてくる。そうされると、身体中が一段と熱くなった。
そして、これまで口づけのたびに疼いていたところが、どこであるのかようやくわかった。今、シャルルにふれられているところの、さらに奥なのだ。秘された官能の泉から、なにかが熱く溢れてくるような感じがする。
「ふ……ンぅ……」
口づけが卑猥で大胆になってきたので、体勢を保つため、リゼットはドレスを握りしめていた手を作業台のほうに移した。
その拍子に、絵付けしたイースターストーンをさわってしまい、それが床に転がり落ちた。
(あ)
石が床を打ちつける音を耳にして、口づけに気をとられていたリゼットは少し我に返った。
自分たちはイースターストーンの絵付けをしている最中だったのだ。そしてシャルルの悪ふざけが高じてこんな淫らな行為に及ぶ羽目になってしまって――。
けれど、口づけの虜になったリゼットは、いつのまにか抗うことを忘れていた。
「ん……」
この男の口づけは甘いのだ。こうしてキスされると身体の力が抜けて、うっとりとその感覚に酔いしれてしまう。
(キスされても、もう怖くない……)
処罰だと脅されて堪えているうちに、慣れてしまったのだろうか。こんなにも親密な行為なのに、いつからか、まるでそれをみずからが求めているかのようにすんなりと馴染んでしまうようになった。
(シャルル様……)
自分の中で、この男が特別なのは間違いないのだ。それが恋や愛などの言葉で括られるものかどうかいまいちよくわからないけれど――。
「指でされるの、気持ちいい? 中に挿れて、もっと気持ちよくしてもいい?」
口づけの合間に、シャルルが問いかけてくる。いつもよりもずっと色めいて熱い声色に、ぞくぞくとしてしまう。
「ん……ぅ……」
畳みかけるように、ふたたび唇を塞がれる。そして、彼の指がドロワーズの中に忍び込んできた。
「ふ……」
その手の動きはなめらかで、リゼットの恥じらいと不安をうまく取り除いてくれる。そしてこれまで知らなかった官能を拓かせてゆく。
「ん……」
じかに下生えをなぞられ、敏感な花芯をさぐられると、びくりと腰がはねた。はじめての行為に、緊張が増してゆく。
リゼットが感じてしまって身じろぎするので、口づけはひとまず中断された。
「あ……っ、や……」
シャルルは硬くなった花芯を見つけ、軽く圧したり転がしたりする。布越しでされるよりも鮮明に感覚が伝わるから、リゼットの感度も一気に増した。
「いやらしいリゼットの身体は、じかにさわられるほうが好きみたいだね」
シャルルはにやにやしながら指攻めを続ける。リゼットが感じていることを見抜いているようだ。
「あ、あ、あぁ、はぁ、はぁっ……、んっ、あ……」
濡れた指先で小刻みに揺さぶられ、転がされるたびに、ますます感度が増してゆく。
下肢の奥がじりじりと甘く痺れるような快感が、何度もせりあがってくるのだ。
「あ、あ、あ、ンっ、シャルル様……っ、や、やめ……」
リゼットは焦って、彼の手を押さえようとする。
(これ以上は……だめ……)
自分の身体になにが起きているのかよくわからないし、この先、どうなるのかもわからない。肉体に起きる未知の変化についていけず、うろたえるばかりだ。
「気持ちいいんだろう? 吐息が色っぽくなってきたからよくわかるよ。こっちもそろそろ僕を欲しがってるんじゃないかな?」
シャルルが、指を下のほうに滑らせた。
「ん……ぁ……」
秘唇のあわいをなぞった彼の指が密口に到達すると、そこはぬるりと滑った。
「や……」
ふだんとは異なる状態に、リゼットはどきりとした。
「濡れてるね。……大丈夫だ。君のここが僕を求めている証だよ」
シャルルが濡れた指先を行き来させながら、うっすらと笑う。彼はなにもかもわかりきっているようだった。
「シャルル……様を……?」
意味がわからなくて、リゼットは戸惑う。
「そう、まずは指でたしかめてみよう」
言いながらシャルルが、蜜口をゆっくりとなぞる。
「あ……ン……」
そこは蜂蜜を塗ったかのように滑りがよく、敏感になっている。
彼が指でなぞるたびに、あらたな愛液がじわじわと溢れてくるのがわかる。
「ああ、リゼット……、こんなに濡らして……、このいやらしい蜜でほんとうに絵が描けてしまいそうだな」
シャルルは密口に指先を挿入しだす。
「あ、ゆ、指が……入って……」
「そう。大丈夫だよ。こんなにも濡れているんだ。もっと気持ちよくなれるだけだよ」
そう言って、シャルルはくちゅりと指先を沈めてくる。
「ん……ぁ……」
いくらかの抵抗があった。けれど、痛みではなかった。柔襞をゆっくりと行きつ戻りつをくりかえしながら、彼の指の関節がしだいに媚壁の深みへと引き込まれてゆく。
「ん、あ……」
ゆるやかに動かされる指。
それから快感が与えられ、リゼットはもっと気持ちよくなりたくて、彼の指戯につい身をゆだねてしまう。
「よく濡れてるよ、リゼット……、指がきみの中に入って……。ほら、わかるよね?」
シャルルはついに、指の付け根まで沈めてしまった。
そして沈めた指先で、恥骨の裏奥のあたりを圧し始める。指が濡れた柔襞を上向きに撫でまわし、リゼットにはよくわからない、どこかいいところをさぐりあてる。
「見つけた。ここだね」
ふと湯水が広がるような、あらたな快感が下腹部の奥に生じた。
「あ、あ、なに……」
あまりにも甘美なこの感覚、快感とともに浮遊するような心地よさにうっとりしてしまう。
「そう、いいだろう? いっぱいよくしてあげるよ」
「あ、あ、あ……ん……」
快感がいっそう深まって、リゼットは背をのけぞらせた。
シャルルはそこを狙って執拗に指を抜き差ししだす。
すると内奥が快感を求めるかのように彼の指を締めつけはじめる。
「またたくさん濡れてきたよ、リゼット。困ったな、きみの底なしの濡れっぷりには」
「あ、や……、ああ……あ……はぁ、はぁっ……ンっ……」
指の付け根には花芽をしごかれて、えもいわれぬ快感が込み上げた。そのまま愛液を攪拌するかのように激しく揺さぶられる。
クチュクチュといやらしい音がリゼットの耳にまで届き、はしたないことにその音にすら昂りをおぼえてしまう。
「ああ、締まってきたね……、このまま達してしまってもいいよ、リゼット?」
シャルルがなにか言っているけれど、リゼットにはろくに届かない。
「あっ、あっ、はぁ、はぁ、あ、あ……ン……」
隘路の快い圧が増すにつれ、リゼットの唇からはよがるような甘い声が迸る。
「男嫌いの上に信心深い君が、一度目からここまで艶やかに乱れるとは思わなかったな……、だめだよ、そんなに声を出したら、外に聞こえてしまうよ?」
シャルルが、快感に悶えるリゼットをしたり顔で凝視している。
そういえば、ここは宮殿の一角にあるアトリエなのだ。
今やドレスは乱れに乱れて、乳房と下肢をはしたなくさらけだしている。
白昼堂々、こんな淫らな行為にふけって悦んでしまうなんて。
けれども巧みな指遣いに翻弄され、官能の愉悦に呑まれてしまったリゼットの身体は、もはや行きつくところまで行くしかなかった。
「あ、あっ、ああぁ……、シャルル様……っ」
これが世に言う快楽に耽るということなのだろうか。自分の身体までもがこんなふうになってしまうなんて、リゼットは知らなかった。貞操を守らねばならないというのに、このままでは快感に身を委ねてしまいそうだ。
「も、もう……さわら、ないで……」
リゼットは掠れたかぼそい声で言う。五感が秘所にもっていかれ、言葉もまともに紡げなくなってゆく。
「あ……や……、やめ……、ン……」
リゼットはシャルルの指遣いに反応して、ぴくぴくと内腿を震わせる。
「感じてるね。だんだんここが硬くなってきたみたいだ、ほら、僕にさわってくれって訴えてるよ」
シャルルが言いながら、花芯を指の腹で小刻みに揺さぶる。
「あ、あ、あぁ、や、だめ……これ……ン、はぁ、はぁ……っ」
痺れるような快感がくりかえしせりあがってきて、下腹部に力が入ってしまう。
リゼットははぁはぁと熱い息をこぼしながら、ドレスを握りしめる。
「息が乱れてきたね、リゼット。……頬も薔薇のように染まって色っぽいな、キスしたい」
言うなり、シャルルが口づけてきた。
「ん……」
遠慮のない口づけだった。かさねあわせてすぐに、唇の隙間から、ぬっと舌を入れられた。
熱い塊に、口内をぐるりと蹂躙される。
いつもより荒々しく性急な感じで、そのことがリゼットを昂らせた。
「ン……ぅ……」
舌をとらえ、卑猥に絡めあわせてくる。そうされると、身体中が一段と熱くなった。
そして、これまで口づけのたびに疼いていたところが、どこであるのかようやくわかった。今、シャルルにふれられているところの、さらに奥なのだ。秘された官能の泉から、なにかが熱く溢れてくるような感じがする。
「ふ……ンぅ……」
口づけが卑猥で大胆になってきたので、体勢を保つため、リゼットはドレスを握りしめていた手を作業台のほうに移した。
その拍子に、絵付けしたイースターストーンをさわってしまい、それが床に転がり落ちた。
(あ)
石が床を打ちつける音を耳にして、口づけに気をとられていたリゼットは少し我に返った。
自分たちはイースターストーンの絵付けをしている最中だったのだ。そしてシャルルの悪ふざけが高じてこんな淫らな行為に及ぶ羽目になってしまって――。
けれど、口づけの虜になったリゼットは、いつのまにか抗うことを忘れていた。
「ん……」
この男の口づけは甘いのだ。こうしてキスされると身体の力が抜けて、うっとりとその感覚に酔いしれてしまう。
(キスされても、もう怖くない……)
処罰だと脅されて堪えているうちに、慣れてしまったのだろうか。こんなにも親密な行為なのに、いつからか、まるでそれをみずからが求めているかのようにすんなりと馴染んでしまうようになった。
(シャルル様……)
自分の中で、この男が特別なのは間違いないのだ。それが恋や愛などの言葉で括られるものかどうかいまいちよくわからないけれど――。
「指でされるの、気持ちいい? 中に挿れて、もっと気持ちよくしてもいい?」
口づけの合間に、シャルルが問いかけてくる。いつもよりもずっと色めいて熱い声色に、ぞくぞくとしてしまう。
「ん……ぅ……」
畳みかけるように、ふたたび唇を塞がれる。そして、彼の指がドロワーズの中に忍び込んできた。
「ふ……」
その手の動きはなめらかで、リゼットの恥じらいと不安をうまく取り除いてくれる。そしてこれまで知らなかった官能を拓かせてゆく。
「ん……」
じかに下生えをなぞられ、敏感な花芯をさぐられると、びくりと腰がはねた。はじめての行為に、緊張が増してゆく。
リゼットが感じてしまって身じろぎするので、口づけはひとまず中断された。
「あ……っ、や……」
シャルルは硬くなった花芯を見つけ、軽く圧したり転がしたりする。布越しでされるよりも鮮明に感覚が伝わるから、リゼットの感度も一気に増した。
「いやらしいリゼットの身体は、じかにさわられるほうが好きみたいだね」
シャルルはにやにやしながら指攻めを続ける。リゼットが感じていることを見抜いているようだ。
「あ、あ、あぁ、はぁ、はぁっ……、んっ、あ……」
濡れた指先で小刻みに揺さぶられ、転がされるたびに、ますます感度が増してゆく。
下肢の奥がじりじりと甘く痺れるような快感が、何度もせりあがってくるのだ。
「あ、あ、あ、ンっ、シャルル様……っ、や、やめ……」
リゼットは焦って、彼の手を押さえようとする。
(これ以上は……だめ……)
自分の身体になにが起きているのかよくわからないし、この先、どうなるのかもわからない。肉体に起きる未知の変化についていけず、うろたえるばかりだ。
「気持ちいいんだろう? 吐息が色っぽくなってきたからよくわかるよ。こっちもそろそろ僕を欲しがってるんじゃないかな?」
シャルルが、指を下のほうに滑らせた。
「ん……ぁ……」
秘唇のあわいをなぞった彼の指が密口に到達すると、そこはぬるりと滑った。
「や……」
ふだんとは異なる状態に、リゼットはどきりとした。
「濡れてるね。……大丈夫だ。君のここが僕を求めている証だよ」
シャルルが濡れた指先を行き来させながら、うっすらと笑う。彼はなにもかもわかりきっているようだった。
「シャルル……様を……?」
意味がわからなくて、リゼットは戸惑う。
「そう、まずは指でたしかめてみよう」
言いながらシャルルが、蜜口をゆっくりとなぞる。
「あ……ン……」
そこは蜂蜜を塗ったかのように滑りがよく、敏感になっている。
彼が指でなぞるたびに、あらたな愛液がじわじわと溢れてくるのがわかる。
「ああ、リゼット……、こんなに濡らして……、このいやらしい蜜でほんとうに絵が描けてしまいそうだな」
シャルルは密口に指先を挿入しだす。
「あ、ゆ、指が……入って……」
「そう。大丈夫だよ。こんなにも濡れているんだ。もっと気持ちよくなれるだけだよ」
そう言って、シャルルはくちゅりと指先を沈めてくる。
「ん……ぁ……」
いくらかの抵抗があった。けれど、痛みではなかった。柔襞をゆっくりと行きつ戻りつをくりかえしながら、彼の指の関節がしだいに媚壁の深みへと引き込まれてゆく。
「ん、あ……」
ゆるやかに動かされる指。
それから快感が与えられ、リゼットはもっと気持ちよくなりたくて、彼の指戯につい身をゆだねてしまう。
「よく濡れてるよ、リゼット……、指がきみの中に入って……。ほら、わかるよね?」
シャルルはついに、指の付け根まで沈めてしまった。
そして沈めた指先で、恥骨の裏奥のあたりを圧し始める。指が濡れた柔襞を上向きに撫でまわし、リゼットにはよくわからない、どこかいいところをさぐりあてる。
「見つけた。ここだね」
ふと湯水が広がるような、あらたな快感が下腹部の奥に生じた。
「あ、あ、なに……」
あまりにも甘美なこの感覚、快感とともに浮遊するような心地よさにうっとりしてしまう。
「そう、いいだろう? いっぱいよくしてあげるよ」
「あ、あ、あ……ん……」
快感がいっそう深まって、リゼットは背をのけぞらせた。
シャルルはそこを狙って執拗に指を抜き差ししだす。
すると内奥が快感を求めるかのように彼の指を締めつけはじめる。
「またたくさん濡れてきたよ、リゼット。困ったな、きみの底なしの濡れっぷりには」
「あ、や……、ああ……あ……はぁ、はぁっ……ンっ……」
指の付け根には花芽をしごかれて、えもいわれぬ快感が込み上げた。そのまま愛液を攪拌するかのように激しく揺さぶられる。
クチュクチュといやらしい音がリゼットの耳にまで届き、はしたないことにその音にすら昂りをおぼえてしまう。
「ああ、締まってきたね……、このまま達してしまってもいいよ、リゼット?」
シャルルがなにか言っているけれど、リゼットにはろくに届かない。
「あっ、あっ、はぁ、はぁ、あ、あ……ン……」
隘路の快い圧が増すにつれ、リゼットの唇からはよがるような甘い声が迸る。
「男嫌いの上に信心深い君が、一度目からここまで艶やかに乱れるとは思わなかったな……、だめだよ、そんなに声を出したら、外に聞こえてしまうよ?」
シャルルが、快感に悶えるリゼットをしたり顔で凝視している。
そういえば、ここは宮殿の一角にあるアトリエなのだ。
今やドレスは乱れに乱れて、乳房と下肢をはしたなくさらけだしている。
白昼堂々、こんな淫らな行為にふけって悦んでしまうなんて。
けれども巧みな指遣いに翻弄され、官能の愉悦に呑まれてしまったリゼットの身体は、もはや行きつくところまで行くしかなかった。
「あ、あっ、ああぁ……、シャルル様……っ」