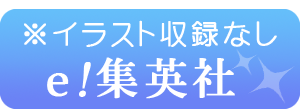宮廷艶話
公爵夫人がふしだらな小説を書く事情
あまおう紅 イラスト/Kujow
「リュ、リュシアン……っ」
官能小説を書いた際、色んな女性に取材をし、男女の性愛についてはひと通りわかったつもりになった。しかし、それがまちがいだったことを理解する。
(こんな……こんな、頭が沸騰したみたいに、どうすればいいのかわからなくなってしまうなんて……!)
知らず知らずにうるんでいた目に吸い寄せられるように、彼は首をのばしてエステルの目尻にキスをしてくる。
「僕たちは夫婦になったんだから、こんなふうにはしゃいでもいいんだ」
上気した頬に口づけた後、リュシアンは自分の頬をエステルの首筋に埋めた。
「僕はずっと前から、こうして君を思うさま抱きしめたいと思っていた……」
「リュシアン、わたし……」
「ふるえてるね。……いや?」
優しい声音で問われ、首を横に振る。
「とても緊張しているの。それに、恥ずかしくて……」
自分が彼の身体を余すところなく感じているように、彼もまた、エステルの身体を感じていることだろう。そう思うと、今すぐに逃げだしてしまいたいほどの羞恥に見舞われる。
「じゃあしばらくこうしていようよ。そうすればきっと慣れるはずだ」
エステルは小さくうなずいた。
ひどく恥ずかしくて、いたたまれなくて、湯がいたように顔が熱くなる。それでも。
「わたし、とても幸せよ……。あなたと結婚できて嬉しいの。嘘じゃないわ……」
「うん。女の人は初夜を恐がるものだって、色んな人から聞かされたから、わかってるつもり」
「そ――そんなことを聞いたの……?」
誰だか知らないものの、見すかされたことが恥ずかしく、真っ赤になった顔を彼の胸に押しつけるようにして隠す。
……と、リュシアンがうめいた。
「頼むからそんな可愛い真似しないで。我慢できなくなるから……」
「リュシアン……」
うるんだ瞳で見つめていたエステルに、彼はやわらかくキスをした。
互いにくちびるを合わせ、軽く吸い、甘い心地に耽溺する。
ここまでは、これまでにも経験してきたことだ。とうとうこの先に進むのだろうか――
蕩けそうな思考の片隅でそう考えた時、ふと彼が、キスの合間にささやいた。
「……だまっているのは卑怯だから、告白するよ」
リュシアンは熱っぽく輝く藍色の瞳を伏せる。そしてエステルと再会した後のことについて、ぽつぽつと話し始めた。
再会した直後はまだ一抹の疑いを抱いていた。エステルは本当は駆け落ちをしておきながら、相手とうまくいかなくて決裂し、修道院に入ったのではないか。そこにひょっこりリュシアンが現れたため、ヨリを戻そうとして嘘をついているのではないかと。
「そんなこと……!」
「僕としては、それでも一向にかまわなかったけど。でも……本当のことを知りたくて、君がいつ修道院にやってきたのかを院長に確かめた。結果、君の話が真実だったとわかったんだ」
「わたしの言葉を疑ったのね」
「ごめん。二度とそんなことはしないと約束するよ。だから許してほしい」
間近でささやく彼の額に、エステルは自分の額をくっつけた。
「……あんな状況ではしかたがないわ。まさか叔母夫婦が連絡を阻んでいたなんて、わたしも考えもしなかったもの……」
それに、と思う。リュシアンに対して後ろめたいことがあるのは、自分も同じ。
(夫婦になるんだもの、隠し事は良くないわよね……)
彼の告白を受けてそう決意し、エステルも顔を上げた。
「……リュシアン、わたしもひとつ、あなたに話さないとならないことがあるの」
「なに?」
「そのぅ……」
まっすぐな藍色の瞳に見つめられ、言葉尻がしぼんでしまう。
彼に軽蔑されたらどうしよう。そんな不安に見舞われた。けれど彼も勇気を出して告白してくれたのだ。
そう自分を叱咤し、思いきって口を開く。……が。
「わたしね……修道院で暮らしていた頃、…………を書いていたの」
肝心な部分の声が小さくなってしまった。
リュシアンが首を傾げる。
「え? なんだって?」
「か……官能小説を……」
「…………え?」
目を丸くする彼に、しどろもどろになりながら事の次第を説明した。
結果――大笑いされてしまう。
「そんなに笑わなくても……っ」
「だって君があんまり難しい顔をしているから、ものすごく深刻な問題なのかと思ったら…………っ」
リュシアンはなおも、クックッと声を殺して笑う。
その様子をエステルはまじまじと見つめてしまった。
「本当……? 何とも思っていない?」
「まぁね。誰に迷惑をかけるわけでもないし……」
そこまで言った時、彼はふと笑みを消す。
「……もしかしてこれからも書きたかったりする?」
「いいえ。お金に困ってるわけでもないし」
「よかった……。僕は気にしないけど、母にバレたら厄介そうだから……ちょっとね」
リュシアンの母親は夫亡き後、息子が帰国するまでひとりで公爵家を守り続けてきた女性である。
関係はまずまず良好だが、家のことが何にも増して勝る人だと聞いている。
リュシアンはこちらを気遣うように言い添えた。
「恋愛小説なら、これまで通り書いてくれてかまわないよ」
「……いいえ。平気よ。もう必要ないの」
エステルは彼の胸に頬を押し当てる。
「あれはわたしにとって、あなたを失った心の隙間を埋める行為だったから」
それを耳にしたリュシアンは「ふふふ……っ」とうれしそうに笑った。そしてエステルの背中を大きな手でゆっくりとなで下ろす。
「……ところで、どんな内容?」
「え?」
「君の書いた官能小説だよ」
「それは……リュシアンと、こんなふうに結ばれたかったっていう夢というか……」
「へぇ?」
リュシアン、ぺろりと舌舐めずり。
「それはぜひ、内容を詳しく訊きたいね」
「う……」
「その官能的な場面で、主人公達はどんなふうに結ばれるんだい?」
「口では……説明できないわ……っ」
「言わないとこうだよ――」
ささやきと共にくちびるが優しく塞がれた。
ついばむような感触は、柔らかくて、温かい。
「……はぁ……っ」
高まる期待に湿った吐息が混ざり合う。羽毛のような優しいキスは、角度を変えてくり返すうち、徐々にふれ合う時間が長くなっていく。
くちびるはとても敏感なものだと、キスをするようになって知った。
こうして擦り合わせているだけで天に昇るほど心地よい。
吐息にすら感じてしまうくちびるを舌先でくすぐられ、エステルは息を呑んだ。
ゆるんだくちびるの狭間を、すかさず舌先で割り開かれる。
「――――……っ」
生々しい感触に思わず身を引こうとしたところ、下からのびてきた彼の手に項を押さえられ、ぬるりと舌が入り込んできた。とろりとした熱いものに、口のなかをまさぐられ、茹でたように顔が熱くなる。
「んぅ、ん……っ!」
名前を呼ぶも、くぐもった声が出るばかり。
(あぁ……このキス、だめ……っ)
再会してから、リュシアンは時々この大人のキスを仕掛けてくるようになった。
互いの舌をからめる深いキスがあると、官能小説の取材中に聞いていたため驚きはなかった。だが――
彼の舌がエステルのものを捕らえ、吸い上げる。
「ふ……んっ、……ん……っ」
ねっとりとして熱い、あまりに卑猥な感触に、ビクッと背筋をひくつかせる。下腹の奥で、たまらなく淫蕩な熱が生まれた。
性的すぎるこのキスをすると、エステルの身体は悩ましく火照り、自分でもどうしていいのかわからない甘苦しい衝動を持てあますことになる。
そのため少し苦手だった。
項を押さえられながらも、わたわたと逃げを打っていると、やがてリュシアンはくるりと体勢を入れ替えてくる。
エステルはいつの間にか、彼の身体の下に組み敷かれていた。
エステルを寝具に押しつけるようにして、リュシアンは一層深くくちびるを重ねてくる。
「ん、ふ……ん……っ」
息継ぎの合間に、鼻にかかったような甘えた声が漏れる。
舌の根までヌルヌルと舐められ、ぶわりと噴き出した歓びに背筋をしならせた。口の中はひどく感じやすく、恥ずかしいほどはしたなく反応してしまう。
彼の身体を押しのけようとのばした両手は、まんまと彼の手につかまり、指をからめるようにして寝具に押さえつけられてしまった。
そうされると、エステルにはもう甘すぎる蹂躙に抗う術がない。
ちゅくちゅくと濡れた音と、淫らな息づかいが響く。心臓が強く脈打ち、頭がくらくらした。
熱い舌のもたらす淫悦の沼に引きずり込まれ、とろとろにふやけるまで浸される。
「……小説の中で、こういうキスは書いた?」
ややあってリュシアンが顔を離し、白皙の頬をうっすらと染めて訊ねてくる。
「……書いたわ……」
「いけない子だね。経験したこともないのに、そんな場面を書くなんて」
「でも……皆、そうするんだって……聞いたから……」
よって自分がリュシアンとそんなキスをした時のことを想像し、うんとドキドキしながら書いたのだ。
そう説明すると、リュシアンはしごく満足したように促してきた。
「じゃあキスの先は? どうなるの?」
「…………っ」
恥ずかしさに、エステルの顔がカァァッと熱くなる。
顔を横に向け、目を伏せてか細い声で応じる。
「ふ……服を脱がせ……」
「なるほど」
もっともらしくうなずきながら、彼はエステルの夜着の胸元を留めてたリボンを解き、前を大きく開きにかかった。肘のあたりまでゆっくりと押し下げられ、白い素肌と裸の胸が露わになる。
ふたつのふくらみを食い入るように見られ、恥ずかしくなる。
「あんまり見ないで……」
エステルは横を向いたまま儚く訴えたものの、苦笑交じりに一蹴されてしまった。
「それは無理な相談だよ。……それから?」
「恋人は……主人公の身体をまさぐって――」
「こんなふうに?」
のばされてきた手が、ふくらみをそぅっと包み込む。
直にふれられる感触に、びくりと肩が震えた。
「ぁ……っ」
官能小説を書いた際、色んな女性に取材をし、男女の性愛についてはひと通りわかったつもりになった。しかし、それがまちがいだったことを理解する。
(こんな……こんな、頭が沸騰したみたいに、どうすればいいのかわからなくなってしまうなんて……!)
知らず知らずにうるんでいた目に吸い寄せられるように、彼は首をのばしてエステルの目尻にキスをしてくる。
「僕たちは夫婦になったんだから、こんなふうにはしゃいでもいいんだ」
上気した頬に口づけた後、リュシアンは自分の頬をエステルの首筋に埋めた。
「僕はずっと前から、こうして君を思うさま抱きしめたいと思っていた……」
「リュシアン、わたし……」
「ふるえてるね。……いや?」
優しい声音で問われ、首を横に振る。
「とても緊張しているの。それに、恥ずかしくて……」
自分が彼の身体を余すところなく感じているように、彼もまた、エステルの身体を感じていることだろう。そう思うと、今すぐに逃げだしてしまいたいほどの羞恥に見舞われる。
「じゃあしばらくこうしていようよ。そうすればきっと慣れるはずだ」
エステルは小さくうなずいた。
ひどく恥ずかしくて、いたたまれなくて、湯がいたように顔が熱くなる。それでも。
「わたし、とても幸せよ……。あなたと結婚できて嬉しいの。嘘じゃないわ……」
「うん。女の人は初夜を恐がるものだって、色んな人から聞かされたから、わかってるつもり」
「そ――そんなことを聞いたの……?」
誰だか知らないものの、見すかされたことが恥ずかしく、真っ赤になった顔を彼の胸に押しつけるようにして隠す。
……と、リュシアンがうめいた。
「頼むからそんな可愛い真似しないで。我慢できなくなるから……」
「リュシアン……」
うるんだ瞳で見つめていたエステルに、彼はやわらかくキスをした。
互いにくちびるを合わせ、軽く吸い、甘い心地に耽溺する。
ここまでは、これまでにも経験してきたことだ。とうとうこの先に進むのだろうか――
蕩けそうな思考の片隅でそう考えた時、ふと彼が、キスの合間にささやいた。
「……だまっているのは卑怯だから、告白するよ」
リュシアンは熱っぽく輝く藍色の瞳を伏せる。そしてエステルと再会した後のことについて、ぽつぽつと話し始めた。
再会した直後はまだ一抹の疑いを抱いていた。エステルは本当は駆け落ちをしておきながら、相手とうまくいかなくて決裂し、修道院に入ったのではないか。そこにひょっこりリュシアンが現れたため、ヨリを戻そうとして嘘をついているのではないかと。
「そんなこと……!」
「僕としては、それでも一向にかまわなかったけど。でも……本当のことを知りたくて、君がいつ修道院にやってきたのかを院長に確かめた。結果、君の話が真実だったとわかったんだ」
「わたしの言葉を疑ったのね」
「ごめん。二度とそんなことはしないと約束するよ。だから許してほしい」
間近でささやく彼の額に、エステルは自分の額をくっつけた。
「……あんな状況ではしかたがないわ。まさか叔母夫婦が連絡を阻んでいたなんて、わたしも考えもしなかったもの……」
それに、と思う。リュシアンに対して後ろめたいことがあるのは、自分も同じ。
(夫婦になるんだもの、隠し事は良くないわよね……)
彼の告白を受けてそう決意し、エステルも顔を上げた。
「……リュシアン、わたしもひとつ、あなたに話さないとならないことがあるの」
「なに?」
「そのぅ……」
まっすぐな藍色の瞳に見つめられ、言葉尻がしぼんでしまう。
彼に軽蔑されたらどうしよう。そんな不安に見舞われた。けれど彼も勇気を出して告白してくれたのだ。
そう自分を叱咤し、思いきって口を開く。……が。
「わたしね……修道院で暮らしていた頃、…………を書いていたの」
肝心な部分の声が小さくなってしまった。
リュシアンが首を傾げる。
「え? なんだって?」
「か……官能小説を……」
「…………え?」
目を丸くする彼に、しどろもどろになりながら事の次第を説明した。
結果――大笑いされてしまう。
「そんなに笑わなくても……っ」
「だって君があんまり難しい顔をしているから、ものすごく深刻な問題なのかと思ったら…………っ」
リュシアンはなおも、クックッと声を殺して笑う。
その様子をエステルはまじまじと見つめてしまった。
「本当……? 何とも思っていない?」
「まぁね。誰に迷惑をかけるわけでもないし……」
そこまで言った時、彼はふと笑みを消す。
「……もしかしてこれからも書きたかったりする?」
「いいえ。お金に困ってるわけでもないし」
「よかった……。僕は気にしないけど、母にバレたら厄介そうだから……ちょっとね」
リュシアンの母親は夫亡き後、息子が帰国するまでひとりで公爵家を守り続けてきた女性である。
関係はまずまず良好だが、家のことが何にも増して勝る人だと聞いている。
リュシアンはこちらを気遣うように言い添えた。
「恋愛小説なら、これまで通り書いてくれてかまわないよ」
「……いいえ。平気よ。もう必要ないの」
エステルは彼の胸に頬を押し当てる。
「あれはわたしにとって、あなたを失った心の隙間を埋める行為だったから」
それを耳にしたリュシアンは「ふふふ……っ」とうれしそうに笑った。そしてエステルの背中を大きな手でゆっくりとなで下ろす。
「……ところで、どんな内容?」
「え?」
「君の書いた官能小説だよ」
「それは……リュシアンと、こんなふうに結ばれたかったっていう夢というか……」
「へぇ?」
リュシアン、ぺろりと舌舐めずり。
「それはぜひ、内容を詳しく訊きたいね」
「う……」
「その官能的な場面で、主人公達はどんなふうに結ばれるんだい?」
「口では……説明できないわ……っ」
「言わないとこうだよ――」
ささやきと共にくちびるが優しく塞がれた。
ついばむような感触は、柔らかくて、温かい。
「……はぁ……っ」
高まる期待に湿った吐息が混ざり合う。羽毛のような優しいキスは、角度を変えてくり返すうち、徐々にふれ合う時間が長くなっていく。
くちびるはとても敏感なものだと、キスをするようになって知った。
こうして擦り合わせているだけで天に昇るほど心地よい。
吐息にすら感じてしまうくちびるを舌先でくすぐられ、エステルは息を呑んだ。
ゆるんだくちびるの狭間を、すかさず舌先で割り開かれる。
「――――……っ」
生々しい感触に思わず身を引こうとしたところ、下からのびてきた彼の手に項を押さえられ、ぬるりと舌が入り込んできた。とろりとした熱いものに、口のなかをまさぐられ、茹でたように顔が熱くなる。
「んぅ、ん……っ!」
名前を呼ぶも、くぐもった声が出るばかり。
(あぁ……このキス、だめ……っ)
再会してから、リュシアンは時々この大人のキスを仕掛けてくるようになった。
互いの舌をからめる深いキスがあると、官能小説の取材中に聞いていたため驚きはなかった。だが――
彼の舌がエステルのものを捕らえ、吸い上げる。
「ふ……んっ、……ん……っ」
ねっとりとして熱い、あまりに卑猥な感触に、ビクッと背筋をひくつかせる。下腹の奥で、たまらなく淫蕩な熱が生まれた。
性的すぎるこのキスをすると、エステルの身体は悩ましく火照り、自分でもどうしていいのかわからない甘苦しい衝動を持てあますことになる。
そのため少し苦手だった。
項を押さえられながらも、わたわたと逃げを打っていると、やがてリュシアンはくるりと体勢を入れ替えてくる。
エステルはいつの間にか、彼の身体の下に組み敷かれていた。
エステルを寝具に押しつけるようにして、リュシアンは一層深くくちびるを重ねてくる。
「ん、ふ……ん……っ」
息継ぎの合間に、鼻にかかったような甘えた声が漏れる。
舌の根までヌルヌルと舐められ、ぶわりと噴き出した歓びに背筋をしならせた。口の中はひどく感じやすく、恥ずかしいほどはしたなく反応してしまう。
彼の身体を押しのけようとのばした両手は、まんまと彼の手につかまり、指をからめるようにして寝具に押さえつけられてしまった。
そうされると、エステルにはもう甘すぎる蹂躙に抗う術がない。
ちゅくちゅくと濡れた音と、淫らな息づかいが響く。心臓が強く脈打ち、頭がくらくらした。
熱い舌のもたらす淫悦の沼に引きずり込まれ、とろとろにふやけるまで浸される。
「……小説の中で、こういうキスは書いた?」
ややあってリュシアンが顔を離し、白皙の頬をうっすらと染めて訊ねてくる。
「……書いたわ……」
「いけない子だね。経験したこともないのに、そんな場面を書くなんて」
「でも……皆、そうするんだって……聞いたから……」
よって自分がリュシアンとそんなキスをした時のことを想像し、うんとドキドキしながら書いたのだ。
そう説明すると、リュシアンはしごく満足したように促してきた。
「じゃあキスの先は? どうなるの?」
「…………っ」
恥ずかしさに、エステルの顔がカァァッと熱くなる。
顔を横に向け、目を伏せてか細い声で応じる。
「ふ……服を脱がせ……」
「なるほど」
もっともらしくうなずきながら、彼はエステルの夜着の胸元を留めてたリボンを解き、前を大きく開きにかかった。肘のあたりまでゆっくりと押し下げられ、白い素肌と裸の胸が露わになる。
ふたつのふくらみを食い入るように見られ、恥ずかしくなる。
「あんまり見ないで……」
エステルは横を向いたまま儚く訴えたものの、苦笑交じりに一蹴されてしまった。
「それは無理な相談だよ。……それから?」
「恋人は……主人公の身体をまさぐって――」
「こんなふうに?」
のばされてきた手が、ふくらみをそぅっと包み込む。
直にふれられる感触に、びくりと肩が震えた。
「ぁ……っ」