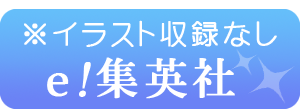少年王のお気に召すまま
京極れな イラスト/北沢きょう
「今夜はジェニーの大事なところを舐めたいな」
アレンがジェニーをベッドに組み敷きながらせがんできた。
「舐めるって……」
ジェニーはどきりとした。
もちろん心得ているものの、自分から誘う勇気がなくて避けていたのだ。
「あなたのここを味わうんだ」
アレンがジェニーの内腿を手で割って、ひらかせようとする。
「や……っ、ンっ、そんなことまで……教えた記憶は……」
ジェニーは腰がひけてしまう。
「愛の指南書で学んだんだよ。はやく試してみたくてたまらない」
「べ、勉強熱心でお利口ね」
「ほかに、あなた自身が実地で教えてくれることは? ……もっとたくさん知りたいな。ここを愛撫してほしいとか、あそこを激しく攻めてほしいとか……、もちろん女性側の欲求でかまわない。……僕はそれをあなたのために学んで取り入れるから」
「わ、私のためではなく、妻となる方のために学んでください」
「僕はジェニーのためにしか学ばないよ。あなたのことで頭がいっぱいで仕事さえ手につかず、今日は謁見を二、三人見送ったほどなんだ」
「こ、公務をさぼるのはいけないわ」
アレンは本気なのだろうか。
「ジェニー、ほら、脚をひらいてよ。ベッドで僕を指導するのがあなたの役目だろう?」
経験豊かな女だという点を疑っているのかもしれない。ここで逃げたら、素人だとばれてしまう。
ジェニーは仕方なく抵抗をやめ、彼に向けておずおずと両脚をひらいた。
燭台のにぶい明かりのもと、ジェニーの秘処があらわになる。
アレンの視線が痛いほどに注がれていて、ジェニーは恥ずかしくてたまらない。
「指導はまだ?」
なにもできないでいるジェニーに、彼が待ち遠しげに訊いてくる。
「こ、ここを……舐めて……」
かぼそい声でジェニーが言う。
「どこのこと? 指をさして教えてくれないと」
アレンはにやにやしている。恥じらうジェニーを楽しんでいるみたいだ。
「ここを……」
ジェニーは真っ赤になりながら、秘処のあわいに指先を這わせた。
慣れた女性はこんなことも平気でできるのだろうか。こんな大胆な姿で、相手を誘うようなことまでも――?
「色っぽい眺めだ。素敵だよ。濡らしてあげる」
言いながらアレンが美貌をよせ、花びらに口づけてきた。
「ぁっ」
熱い舌の感触に、ぴくんと腰がはねた。
「気持ちいい?」
アレンは舌先をゆっくりと動かし、柔襞のあわいを舐めだす。
「ん……」
指とは異なるまろやかな刺激に、ジェニーはうっとりしてしまう。
「ここはどう? この上の尖った部分は?」
アレンはちろりと花芽に舌先でつつく。
「あっ」
ジェニーは思わず腰をひいた。
アレンは、ふっと笑った。
「すごく敏感だね。たくさん舐めてあげるよ」
アレンがふたたび花芽に口づけ、舌攻めをはじめた。
「はぁっ、あっ、や、あぁ……」
濡れた舌先でぬるぬると花芽を圧し転がす。ときおり甘く吸いたてたりもして、なんとも卑猥な舌戯だ。ほんとうに指南書で覚えたのだろうか。
「あ、あぁっ、あっ、あん、あっ、舌……だめ……」
ジェニーは甘美な快感をもてあましてシーツを握りしめる。
「どうして? 僕はもっとたくさん味わいたいのに」
「恥ずかしいの……」
ジェニーは昂ってしまう自分が恥ずかしくて、上掛けで隠したくなる。
「恥じらうあなたも素敵だな。……でもだめだよ、僕は練習しなきゃいけないんだ。このまま中も舐めさせて?」
アレンは蜜洞に舌を差し入れるような卑猥な動きまでほどこしてくる。
「ここから蜜が溢れてくるんだ……。いやらしくて興奮する……」
ジェニーも、自分の身体がここまで如実に反応するなんて知らなかった。
「ン、あっ、ああっ……中、だめ、あ、はぁっ、あ……んっ」
物欲しげに疼く秘唇のあわいを、ぬるぬると絶え間なく舐めたおされる。
いつしか、彼の舌が指に変えられていた。
花芽を舌攻めにされ、蜜洞は指で攪拌するようにかきまぜられる。
「蜜だらけになってきたよ、ジェニー?」
「はぁっ、はぁっ、あ、あっ、だめ、ああ……っ、いきそうなの……」
指の腹で上向きのいいところをグチュグチュと擦られ、ジェニーはたまらなくなる。
「中、すごいよ……きつく締まって……」
「あ、あっ、ンっ、はあっ、ん、だめ……もう……」
脳髄がしびれるような快感に耐えられず、ついにジェニーは絶頂に達してしまった。
「あ……ンっ、あああっ」
熱くなった内奥がビクビクと収斂して、アレンの指をしめつける。
「達してしまったの? もっと激しい舌遣いを試してみたかったのに」
舌攻めをやめたアレンが名残惜しそうに言って、指をぬるりと引き抜いた。
そしておもむろにジェニーに上乗りになり、下肢をかさねてくる。
ジェニーが絶頂を迎えたからといって、情事がそこで終わるわけではなかった。一方的にジェニーが気持ちよくなっただけで、彼のほうの欲求はまだ解消されていない。
「ん……」
達したばかりの蜜口に、勃起した男根がふれた。
「次は僕と一緒に気持ちよくなって、ジェニー?」
アレンは、ジェニーに優しく口づけながら、下肢のものを挿入してきた。
「ふ……」
濡れに濡れていた蜜洞に、ぬちりと剛直が押し入ってくる。
敏感なままの媚壁が、ふたたび官能に湧いた。
「ん……、んっ、……んっ、はぁ、はぁ……あっ、……あぁ、あン……っ」
熱く張りつめたものに深く突き込まれ、ジェニーは甘い声を洩らす。
唇をほどいたアレンはゆっくりと挿入をくりかえしながら、快感を味わうジェニーをじっと見つめる。
「ジェニー、ほんとうの声を聞かせて。あなたは僕をどう思っているの?」
突然問われ、ジェニーは目をひらいた。
なぜあらためてこんな問いを投げかけてくるのだろう。不思議に思いながらも、
「……好きよ」
ジェニーはアレンの背中を抱きながら、素直に返す。言葉にすると、ますますその感情が深まってゆく感じがした。好きでなければきっと、こんなことはできない。
ところがアレンは、挿入を続けたままつっぱねた。
「違う、あなたにとっては仕事だろう? だから僕のために好ましい反応を見せているだけなんだ」
いつになく険しい声音だった。
「私が……お芝居でしていると思うの……?」
ジェニーは半ば官能にとらわれながらも問い返す。
「半分はそうだと思ってるよ。この濡れ具合を知ると、うっかり騙されそうになるけどね」
アレンは、わざといいところを狙って突き込んでくる。
「……っ、騙してなんか……いないわ……」
どうして急にこんなことを言い出すのだろう。ジェニーにはわからなくて混乱する。
「なら、言葉にしてほしいな。僕を愛してると言ってよ、ジェニー」
アレンは上体を密着させ、耳朶に口づけながらねだってくる。
「どうしたの、アレン様……」
いつもの甘え方ではなくて、もっと追いつめられたような。
「わからないの? ……あなたからは、決して僕を求めない。……いつも僕のいいなり。言われたとおりに行為をするだけなんだ。この愛され上手の嘘つきめ」
「嘘つきだなんて……」
やはり今夜はなんだか変だ。ノアイユ公爵とのことを誤解して、気にしているのだろうか。
それとも誰かに、なにか吹き込まれたのか――。
そこから先は、腰遣いもさらに猛々しくなった。
アレンは劣情にまかせて、獰猛なまでに激しく抜き差しをくりかえす。
それでもジェニーは感じてしまって、突き込まれるたびに甘く喘いでしまう。
「んっ、はぁ、あっ、あ……っ、あ……ん、もっと……きて……」
アレンは怒っているのかもしれない。でもそのぎりぎりの危うい状態がまたいっそう官能を昂らせるのだ。
「ああ……愛してるわ、アレン様……」
ジェニーは快感に揺らされながらも、アレンを安心させたくて告げる。
「だめだ。まだ足りない。……あなたはそう躾けられているから……だから僕の相手をしているだけだ。おねがいだ、僕を愛して、ジェニー……」
「はぁっ、あ、あぁっ……あっ、あンっ……」
怒張をくりかえしずちゅ、ずちゅと最奥まで突き込まれる。まるでお仕置きのように。
愉悦に酔っているようにも見えるし、苦悩しているようにも見える。
どうしてしまったの、アレン様……。
答えが見つけられないまま、ジェニーはただ、箍が外れたように求めてくるアレンを、深い愉悦に翻弄されながら受けとめることしかできなかった。
アレンがジェニーをベッドに組み敷きながらせがんできた。
「舐めるって……」
ジェニーはどきりとした。
もちろん心得ているものの、自分から誘う勇気がなくて避けていたのだ。
「あなたのここを味わうんだ」
アレンがジェニーの内腿を手で割って、ひらかせようとする。
「や……っ、ンっ、そんなことまで……教えた記憶は……」
ジェニーは腰がひけてしまう。
「愛の指南書で学んだんだよ。はやく試してみたくてたまらない」
「べ、勉強熱心でお利口ね」
「ほかに、あなた自身が実地で教えてくれることは? ……もっとたくさん知りたいな。ここを愛撫してほしいとか、あそこを激しく攻めてほしいとか……、もちろん女性側の欲求でかまわない。……僕はそれをあなたのために学んで取り入れるから」
「わ、私のためではなく、妻となる方のために学んでください」
「僕はジェニーのためにしか学ばないよ。あなたのことで頭がいっぱいで仕事さえ手につかず、今日は謁見を二、三人見送ったほどなんだ」
「こ、公務をさぼるのはいけないわ」
アレンは本気なのだろうか。
「ジェニー、ほら、脚をひらいてよ。ベッドで僕を指導するのがあなたの役目だろう?」
経験豊かな女だという点を疑っているのかもしれない。ここで逃げたら、素人だとばれてしまう。
ジェニーは仕方なく抵抗をやめ、彼に向けておずおずと両脚をひらいた。
燭台のにぶい明かりのもと、ジェニーの秘処があらわになる。
アレンの視線が痛いほどに注がれていて、ジェニーは恥ずかしくてたまらない。
「指導はまだ?」
なにもできないでいるジェニーに、彼が待ち遠しげに訊いてくる。
「こ、ここを……舐めて……」
かぼそい声でジェニーが言う。
「どこのこと? 指をさして教えてくれないと」
アレンはにやにやしている。恥じらうジェニーを楽しんでいるみたいだ。
「ここを……」
ジェニーは真っ赤になりながら、秘処のあわいに指先を這わせた。
慣れた女性はこんなことも平気でできるのだろうか。こんな大胆な姿で、相手を誘うようなことまでも――?
「色っぽい眺めだ。素敵だよ。濡らしてあげる」
言いながらアレンが美貌をよせ、花びらに口づけてきた。
「ぁっ」
熱い舌の感触に、ぴくんと腰がはねた。
「気持ちいい?」
アレンは舌先をゆっくりと動かし、柔襞のあわいを舐めだす。
「ん……」
指とは異なるまろやかな刺激に、ジェニーはうっとりしてしまう。
「ここはどう? この上の尖った部分は?」
アレンはちろりと花芽に舌先でつつく。
「あっ」
ジェニーは思わず腰をひいた。
アレンは、ふっと笑った。
「すごく敏感だね。たくさん舐めてあげるよ」
アレンがふたたび花芽に口づけ、舌攻めをはじめた。
「はぁっ、あっ、や、あぁ……」
濡れた舌先でぬるぬると花芽を圧し転がす。ときおり甘く吸いたてたりもして、なんとも卑猥な舌戯だ。ほんとうに指南書で覚えたのだろうか。
「あ、あぁっ、あっ、あん、あっ、舌……だめ……」
ジェニーは甘美な快感をもてあましてシーツを握りしめる。
「どうして? 僕はもっとたくさん味わいたいのに」
「恥ずかしいの……」
ジェニーは昂ってしまう自分が恥ずかしくて、上掛けで隠したくなる。
「恥じらうあなたも素敵だな。……でもだめだよ、僕は練習しなきゃいけないんだ。このまま中も舐めさせて?」
アレンは蜜洞に舌を差し入れるような卑猥な動きまでほどこしてくる。
「ここから蜜が溢れてくるんだ……。いやらしくて興奮する……」
ジェニーも、自分の身体がここまで如実に反応するなんて知らなかった。
「ン、あっ、ああっ……中、だめ、あ、はぁっ、あ……んっ」
物欲しげに疼く秘唇のあわいを、ぬるぬると絶え間なく舐めたおされる。
いつしか、彼の舌が指に変えられていた。
花芽を舌攻めにされ、蜜洞は指で攪拌するようにかきまぜられる。
「蜜だらけになってきたよ、ジェニー?」
「はぁっ、はぁっ、あ、あっ、だめ、ああ……っ、いきそうなの……」
指の腹で上向きのいいところをグチュグチュと擦られ、ジェニーはたまらなくなる。
「中、すごいよ……きつく締まって……」
「あ、あっ、ンっ、はあっ、ん、だめ……もう……」
脳髄がしびれるような快感に耐えられず、ついにジェニーは絶頂に達してしまった。
「あ……ンっ、あああっ」
熱くなった内奥がビクビクと収斂して、アレンの指をしめつける。
「達してしまったの? もっと激しい舌遣いを試してみたかったのに」
舌攻めをやめたアレンが名残惜しそうに言って、指をぬるりと引き抜いた。
そしておもむろにジェニーに上乗りになり、下肢をかさねてくる。
ジェニーが絶頂を迎えたからといって、情事がそこで終わるわけではなかった。一方的にジェニーが気持ちよくなっただけで、彼のほうの欲求はまだ解消されていない。
「ん……」
達したばかりの蜜口に、勃起した男根がふれた。
「次は僕と一緒に気持ちよくなって、ジェニー?」
アレンは、ジェニーに優しく口づけながら、下肢のものを挿入してきた。
「ふ……」
濡れに濡れていた蜜洞に、ぬちりと剛直が押し入ってくる。
敏感なままの媚壁が、ふたたび官能に湧いた。
「ん……、んっ、……んっ、はぁ、はぁ……あっ、……あぁ、あン……っ」
熱く張りつめたものに深く突き込まれ、ジェニーは甘い声を洩らす。
唇をほどいたアレンはゆっくりと挿入をくりかえしながら、快感を味わうジェニーをじっと見つめる。
「ジェニー、ほんとうの声を聞かせて。あなたは僕をどう思っているの?」
突然問われ、ジェニーは目をひらいた。
なぜあらためてこんな問いを投げかけてくるのだろう。不思議に思いながらも、
「……好きよ」
ジェニーはアレンの背中を抱きながら、素直に返す。言葉にすると、ますますその感情が深まってゆく感じがした。好きでなければきっと、こんなことはできない。
ところがアレンは、挿入を続けたままつっぱねた。
「違う、あなたにとっては仕事だろう? だから僕のために好ましい反応を見せているだけなんだ」
いつになく険しい声音だった。
「私が……お芝居でしていると思うの……?」
ジェニーは半ば官能にとらわれながらも問い返す。
「半分はそうだと思ってるよ。この濡れ具合を知ると、うっかり騙されそうになるけどね」
アレンは、わざといいところを狙って突き込んでくる。
「……っ、騙してなんか……いないわ……」
どうして急にこんなことを言い出すのだろう。ジェニーにはわからなくて混乱する。
「なら、言葉にしてほしいな。僕を愛してると言ってよ、ジェニー」
アレンは上体を密着させ、耳朶に口づけながらねだってくる。
「どうしたの、アレン様……」
いつもの甘え方ではなくて、もっと追いつめられたような。
「わからないの? ……あなたからは、決して僕を求めない。……いつも僕のいいなり。言われたとおりに行為をするだけなんだ。この愛され上手の嘘つきめ」
「嘘つきだなんて……」
やはり今夜はなんだか変だ。ノアイユ公爵とのことを誤解して、気にしているのだろうか。
それとも誰かに、なにか吹き込まれたのか――。
そこから先は、腰遣いもさらに猛々しくなった。
アレンは劣情にまかせて、獰猛なまでに激しく抜き差しをくりかえす。
それでもジェニーは感じてしまって、突き込まれるたびに甘く喘いでしまう。
「んっ、はぁ、あっ、あ……っ、あ……ん、もっと……きて……」
アレンは怒っているのかもしれない。でもそのぎりぎりの危うい状態がまたいっそう官能を昂らせるのだ。
「ああ……愛してるわ、アレン様……」
ジェニーは快感に揺らされながらも、アレンを安心させたくて告げる。
「だめだ。まだ足りない。……あなたはそう躾けられているから……だから僕の相手をしているだけだ。おねがいだ、僕を愛して、ジェニー……」
「はぁっ、あ、あぁっ……あっ、あンっ……」
怒張をくりかえしずちゅ、ずちゅと最奥まで突き込まれる。まるでお仕置きのように。
愉悦に酔っているようにも見えるし、苦悩しているようにも見える。
どうしてしまったの、アレン様……。
答えが見つけられないまま、ジェニーはただ、箍が外れたように求めてくるアレンを、深い愉悦に翻弄されながら受けとめることしかできなかった。