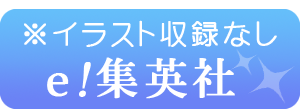3年ごしの初夜、完遂いたします! 限界糖度のジレ甘婚
葉月エリカ イラスト/風コトハ
「この熊に、リアナの代わりをしてもらおうと思って」
「代わり?」
「俺がリアナにしたいことを、こいつにするから。リアナはそれを見ながら、『いずれこういうことをされるんだ』って、イメージトレーニングしてみて」
「ええと……ちょっと、意味がよく」
「百聞は一見に如かずだよ。――ああ、可愛い。俺のリアナは世界一可愛いなぁ」
レナードは寝台に乗り上がると、ぬいぐるみを正面からぎゅっと抱きしめた。熊の額に額をくっつけ、甘く囁く声は真剣だ。
「きらきらしてつぶらな目だね。やっぱり兎みたいだよ」
(……熊だって言ったばかりですけど?)
「顔を背けないで。お願いだから俺の目を見て」
(……ぬいぐるみの首、自分で明後日の方向に向けてたわよね?)
最初こそ突っ込みたくて仕方がなかったが、リアナは次第に妙な心地になってきた。
レナードがぬいぐるみに語りかける声音や、触れる手つきはとても優しい。
それを受け止めているのが、どうして自分ではないのだろうと思うくらいに。
「すべすべした綺麗な肌だ。赤く染まって林檎みたいだ」
ふわふわした熊の顔を包んで、レナードは睦言を囁いた。
彼の目に映るのはぬいぐるみではなく、リアナ本人なのだと信じさせられてしまうような熱っぽさで。
「ここは、もっと赤くて美味しそうだね」
親指の先が、ステッチの入った口元をゆっくりとなぞった。背中に回された手に力がこもり、熊とレナードの顔が近づく。
「ねぇ、リアナ。――キスしていい?」
「だ……だめっ!」
リアナはとっさに声をあげていた。レナードがあの熊を自分に見立てているのだと思うと、とても平常心ではいられない。
レナードが横目でちらりとリアナを見た。
悪戯っぽい笑みを浮かべると、また熊に向き直った。
「今、何か聞こえた気がしたけど――君の本音は、こっちで確かめるよ」
レナードは顔の位置をずらし、ぬいぐるみの胸に耳を押し当てた。綿の詰まったぬいぐるみの胸は、すなわちリアナの胸だ。
「すごくどきどきしてる。……怖い?」
「っ……」
「怖いだけじゃないよね。俺のことを好きでいてくれるから、こうなるんだよね」
胸元から耳を離すと、レナードはとうとう熊の頤に手をかけた。
「――愛してるよ、リアナ」
レナードの唇ともこもこした口吻が、今にも重なり合おうとする刹那。
「やだっ……やめて―――!」
リアナは寝台に飛び乗ると、レナードの腕から熊をひったくって放り投げた。目を丸くした彼の前で、はぁはぁと肩で息をする。
「こんな……こんなの、ずるいわ……!」
「ずるい?」
「いくらぬいぐるみ相手でも、レナードがキスするところなんて見たくない。私がしたくてもできないことを、簡単にできちゃうこの熊が、ずるい……っ」
「それって焼きもち?」
レナードの声が喜色を帯びた。
「俺のこと、ぬいぐるみにも渡したくないくらい、独り占めしたいと思ってる?」
「そうよ……」
自分でも支離滅裂だと思いながら、リアナは認めた。
「面倒臭いし、鬱陶しい女だってわかってる……わかってるの。レナードが我慢してくれてることも、私が覚悟を決めればそれで済む話なんだってことも。私だって、普通の夫婦としてあなたと愛し合いたいわ。だけど、少しでもそういう感じの空気になったら、レナードに見つめられるたびに、本当に心臓が止まりそうで」
「要するに、俺と目が合うのが駄目なわけだ。――だったら、こういうのはどう?」
レナードがポケットから取り出したのは、糊のきいた大判のハンカチだった。それを斜めに折り畳み、両目を隠して頭の後ろで結ぶ。
「どう? これでも駄目なら、麻袋でもかぶるけど」
リアナは、おっかなびっくりレナードを見つめた。整った鼻梁や口元は見えているが、視線が合わないとわかっていると、いつもほどにはどきどきしない。
「大丈夫……みたい」
「じゃあ、こうしたら?」
レナードが腕を伸ばし、リアナの肩に触れた。手探りで首筋を遡り、柔らかな頬を押し包む。
触れられた場所はたちまち熱を持ったが、赤くなった顔を見られていない安心感が、リアナを踏み留まらせた。
「ぎ……ぎりぎり、なんとか」
「こうやって、少しずつ触れ合うことに慣れていこう。――これは?」
「ひゃうっ!?」
頬に柔らかいものが押し当てられ、飛び上がりそうになった。
「キ、キスなんて、そんな、いきなりっ」
「口にじゃないだろ? もう少しだけ頑張って」
レナードの唇が、ゆっくりとあちこちをさまよう。額に、目尻に、こめかみに――羽根で触れるような軽い感触ながら、リアナはいちいち翻弄された。
「あっ……だめ……レナード……」
「くすぐったい? それとも恥ずかしい?」
「ど……どっちも……あ、耳、いやっ……」
「本気で嫌? だったら俺を殴っていいよ」
「うう……っ……」
全身が茹だりそうな羞恥に、リアナは必死に耐えた。
レナードの吐息が次第に荒くなり、興奮の気配を帯びていく。★2
「リアナ――……ねぇ、駄目?」
「な、何が?」
「そろそろちゃんとしたキスがしたい。――ここに」
下唇をなぞられて、リアナはますます追い詰められた。
「嫌なら、また熊で我慢するけど」
「い……意地悪っ……!」
リアナが嫉妬すると知っていて、そんなことを言うのは卑怯だ。寝台の隅で横たわる熊を睨んでいると、レナードが新たな提案をした。
「なら、リアナからしてくれるっていうのは?」
「私……から?」
「俺にキスされると思うとプレッシャーなんでしょ。じゃあいっそ、逆転の発想で」
「断崖絶壁で背中を押されるか、自分から飛び込むか、どっちかに決めろって言われてる気がするんだけど!?」
海に落ちてしまえば、どのみち死ぬ。万にひとつ、自力で泳いで助かる可能性もないではなかろうが。
(――レナードの言うことも、一理あるかもしれない。自分が主導権を握ってのキスなら、少しは落ち着いていられるのかも……)
かくなる上は荒療治だと、リアナは腹をくくった。実際には泣きべそをかきながらだが、目隠し状態のレナードに向き直る。
わざわざ合図などすれば、勢いが削がれてしまうから。
大きく息を吸って、不意打ちのように身を乗り出して。
(えいっ……!)
接触時間は、きっかり一秒――それで離れるつもりだったのに。
「……っ!?」
出し抜けに体重をかけられ、リアナは寝台に倒れ込んだ。
状況が呑み込めないうちに、覆いかぶさってきたレナードにキスの続きを求められる。
「ごめん、やっぱり抑えられない。三年ぶりに……こんな……っ」
「なっ……ちょっと、待っ……んんんっ……!」
首を振って逃げようとしても、レナードは執拗に追いかけてくる。
唇を塞がれながら甘嚙みされて、口腔にぬるりとした感触を覚えた。
「ぁ、ん……ふぁ――っ……」
熱くて分厚い舌が、リアナのそれに絡みつく。さらに深く、もっと奥までと餓えるように潜り込み、歯列の裏までを舐め回された。
こんなにも濃密な口づけは、正真正銘初めてだ。
(キスって……ここまですごいものだったの――……?)
リアナは恍惚として身を震わせた。
ロマンス小説を読んで学んだつもりになっていたが、三百冊分の知識よりも、たった一度の実体験は遥かに衝撃的だった。
延々と続くキスはあまりに甘く、淫らに蠢く舌の感触に、頭が真っ白になる。
血液が沸騰したように全身が熱くて、体の中心が溶けそうだ。
「っ……レナー、ド……」
零れた声は鼻にかかっていて、自分でも当惑した。やめてと訴えるつもりで口にしたのに、これではもっとして欲しいと、おねだりしているかのようだ。
案の定、誤解したらしいレナードが、リアナの肩を押さえつけて上顎を舐る。混ざり合う唾液に嫌悪感を覚えるどころか、劣情がどんどん高まってしまう。
「駄目だ……これ、癖になる」
レナードがわずかに唇を離し、かすれる声で囁いた。
「キスだけで、こんなにいやらしい気分になるなんて……我慢がきかなくなりそうだ」
「代わり?」
「俺がリアナにしたいことを、こいつにするから。リアナはそれを見ながら、『いずれこういうことをされるんだ』って、イメージトレーニングしてみて」
「ええと……ちょっと、意味がよく」
「百聞は一見に如かずだよ。――ああ、可愛い。俺のリアナは世界一可愛いなぁ」
レナードは寝台に乗り上がると、ぬいぐるみを正面からぎゅっと抱きしめた。熊の額に額をくっつけ、甘く囁く声は真剣だ。
「きらきらしてつぶらな目だね。やっぱり兎みたいだよ」
(……熊だって言ったばかりですけど?)
「顔を背けないで。お願いだから俺の目を見て」
(……ぬいぐるみの首、自分で明後日の方向に向けてたわよね?)
最初こそ突っ込みたくて仕方がなかったが、リアナは次第に妙な心地になってきた。
レナードがぬいぐるみに語りかける声音や、触れる手つきはとても優しい。
それを受け止めているのが、どうして自分ではないのだろうと思うくらいに。
「すべすべした綺麗な肌だ。赤く染まって林檎みたいだ」
ふわふわした熊の顔を包んで、レナードは睦言を囁いた。
彼の目に映るのはぬいぐるみではなく、リアナ本人なのだと信じさせられてしまうような熱っぽさで。
「ここは、もっと赤くて美味しそうだね」
親指の先が、ステッチの入った口元をゆっくりとなぞった。背中に回された手に力がこもり、熊とレナードの顔が近づく。
「ねぇ、リアナ。――キスしていい?」
「だ……だめっ!」
リアナはとっさに声をあげていた。レナードがあの熊を自分に見立てているのだと思うと、とても平常心ではいられない。
レナードが横目でちらりとリアナを見た。
悪戯っぽい笑みを浮かべると、また熊に向き直った。
「今、何か聞こえた気がしたけど――君の本音は、こっちで確かめるよ」
レナードは顔の位置をずらし、ぬいぐるみの胸に耳を押し当てた。綿の詰まったぬいぐるみの胸は、すなわちリアナの胸だ。
「すごくどきどきしてる。……怖い?」
「っ……」
「怖いだけじゃないよね。俺のことを好きでいてくれるから、こうなるんだよね」
胸元から耳を離すと、レナードはとうとう熊の頤に手をかけた。
「――愛してるよ、リアナ」
レナードの唇ともこもこした口吻が、今にも重なり合おうとする刹那。
「やだっ……やめて―――!」
リアナは寝台に飛び乗ると、レナードの腕から熊をひったくって放り投げた。目を丸くした彼の前で、はぁはぁと肩で息をする。
「こんな……こんなの、ずるいわ……!」
「ずるい?」
「いくらぬいぐるみ相手でも、レナードがキスするところなんて見たくない。私がしたくてもできないことを、簡単にできちゃうこの熊が、ずるい……っ」
「それって焼きもち?」
レナードの声が喜色を帯びた。
「俺のこと、ぬいぐるみにも渡したくないくらい、独り占めしたいと思ってる?」
「そうよ……」
自分でも支離滅裂だと思いながら、リアナは認めた。
「面倒臭いし、鬱陶しい女だってわかってる……わかってるの。レナードが我慢してくれてることも、私が覚悟を決めればそれで済む話なんだってことも。私だって、普通の夫婦としてあなたと愛し合いたいわ。だけど、少しでもそういう感じの空気になったら、レナードに見つめられるたびに、本当に心臓が止まりそうで」
「要するに、俺と目が合うのが駄目なわけだ。――だったら、こういうのはどう?」
レナードがポケットから取り出したのは、糊のきいた大判のハンカチだった。それを斜めに折り畳み、両目を隠して頭の後ろで結ぶ。
「どう? これでも駄目なら、麻袋でもかぶるけど」
リアナは、おっかなびっくりレナードを見つめた。整った鼻梁や口元は見えているが、視線が合わないとわかっていると、いつもほどにはどきどきしない。
「大丈夫……みたい」
「じゃあ、こうしたら?」
レナードが腕を伸ばし、リアナの肩に触れた。手探りで首筋を遡り、柔らかな頬を押し包む。
触れられた場所はたちまち熱を持ったが、赤くなった顔を見られていない安心感が、リアナを踏み留まらせた。
「ぎ……ぎりぎり、なんとか」
「こうやって、少しずつ触れ合うことに慣れていこう。――これは?」
「ひゃうっ!?」
頬に柔らかいものが押し当てられ、飛び上がりそうになった。
「キ、キスなんて、そんな、いきなりっ」
「口にじゃないだろ? もう少しだけ頑張って」
レナードの唇が、ゆっくりとあちこちをさまよう。額に、目尻に、こめかみに――羽根で触れるような軽い感触ながら、リアナはいちいち翻弄された。
「あっ……だめ……レナード……」
「くすぐったい? それとも恥ずかしい?」
「ど……どっちも……あ、耳、いやっ……」
「本気で嫌? だったら俺を殴っていいよ」
「うう……っ……」
全身が茹だりそうな羞恥に、リアナは必死に耐えた。
レナードの吐息が次第に荒くなり、興奮の気配を帯びていく。★2
「リアナ――……ねぇ、駄目?」
「な、何が?」
「そろそろちゃんとしたキスがしたい。――ここに」
下唇をなぞられて、リアナはますます追い詰められた。
「嫌なら、また熊で我慢するけど」
「い……意地悪っ……!」
リアナが嫉妬すると知っていて、そんなことを言うのは卑怯だ。寝台の隅で横たわる熊を睨んでいると、レナードが新たな提案をした。
「なら、リアナからしてくれるっていうのは?」
「私……から?」
「俺にキスされると思うとプレッシャーなんでしょ。じゃあいっそ、逆転の発想で」
「断崖絶壁で背中を押されるか、自分から飛び込むか、どっちかに決めろって言われてる気がするんだけど!?」
海に落ちてしまえば、どのみち死ぬ。万にひとつ、自力で泳いで助かる可能性もないではなかろうが。
(――レナードの言うことも、一理あるかもしれない。自分が主導権を握ってのキスなら、少しは落ち着いていられるのかも……)
かくなる上は荒療治だと、リアナは腹をくくった。実際には泣きべそをかきながらだが、目隠し状態のレナードに向き直る。
わざわざ合図などすれば、勢いが削がれてしまうから。
大きく息を吸って、不意打ちのように身を乗り出して。
(えいっ……!)
接触時間は、きっかり一秒――それで離れるつもりだったのに。
「……っ!?」
出し抜けに体重をかけられ、リアナは寝台に倒れ込んだ。
状況が呑み込めないうちに、覆いかぶさってきたレナードにキスの続きを求められる。
「ごめん、やっぱり抑えられない。三年ぶりに……こんな……っ」
「なっ……ちょっと、待っ……んんんっ……!」
首を振って逃げようとしても、レナードは執拗に追いかけてくる。
唇を塞がれながら甘嚙みされて、口腔にぬるりとした感触を覚えた。
「ぁ、ん……ふぁ――っ……」
熱くて分厚い舌が、リアナのそれに絡みつく。さらに深く、もっと奥までと餓えるように潜り込み、歯列の裏までを舐め回された。
こんなにも濃密な口づけは、正真正銘初めてだ。
(キスって……ここまですごいものだったの――……?)
リアナは恍惚として身を震わせた。
ロマンス小説を読んで学んだつもりになっていたが、三百冊分の知識よりも、たった一度の実体験は遥かに衝撃的だった。
延々と続くキスはあまりに甘く、淫らに蠢く舌の感触に、頭が真っ白になる。
血液が沸騰したように全身が熱くて、体の中心が溶けそうだ。
「っ……レナー、ド……」
零れた声は鼻にかかっていて、自分でも当惑した。やめてと訴えるつもりで口にしたのに、これではもっとして欲しいと、おねだりしているかのようだ。
案の定、誤解したらしいレナードが、リアナの肩を押さえつけて上顎を舐る。混ざり合う唾液に嫌悪感を覚えるどころか、劣情がどんどん高まってしまう。
「駄目だ……これ、癖になる」
レナードがわずかに唇を離し、かすれる声で囁いた。
「キスだけで、こんなにいやらしい気分になるなんて……我慢がきかなくなりそうだ」