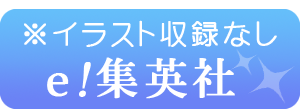巫女の初恋は異国の彼方より
あまおう紅 イラスト/カキネ
「ぅっ……ん、んぅ……!」
太ももがブルブルと震える。喉と背筋を大きく反らしたまま、ティテュスは何度目かわからない絶頂へと突き上げられた。
自らの指で、いったい幾度昇り詰めたことだろう。
そのたびに下肢をぬらす体液があふれて流れることに気付いた。いまやキトンが尻に貼りついて取れないほどに濡れている。
淫猥な行為にふけった証のようで恥ずかしい。にもかかわらず、身の内の疼きはいっこうに治まらなかった。押し寄せる快感にしばらくの間は陶酔するも、また欲求が頭をもたげるのだ。
「たすけて、アトレウス……」
充血した淫芯を自ら転がしながら、小さな声ですすり泣く。
何をしても満たされず、もうどうすればいいのかわからない。ただただ身体が熱い。
「たすけてぇ……」
途方に暮れて、ティテュスはかすかな嗚咽をこぼした。快楽の涙にぬれた眼差しを、篝火の向こうの闇へと向ける。
――と。
ふいに闇の動く気配がした。現れたキトンの裾から視線を上げていけば、文字通り夢にまで見た相手が自分を見下ろしている。
「アトレウス……」
彼はひどく難しい顔をしていた。悩みに悩んだ末にやってきたとでもいうかのような、ひどい渋面である。きれいな顔が深い苦悩に染まり、ますます魅力的だ。
ティテュスは安堵のあまり、ぽろぽろと新たな涙をこぼした。
「アトレウス、待ってた……。来てくれるって信じてた……」
「来るつもりはなかった。……来てはいけなかった」
癖の強い前髪の陰から、菫色の眼差しが苦しげにこちらを見下ろしている。ティテュスから視線をそらさないまま、彼はゆっくりと片膝をついた。
「二年前の君は賢かった。血迷った僕を、きちんと撥ねのけたのだから」
「ずっと後悔してた……」
そうつぶやいたくちびるを、彼の人さし指がそっと押さえる。
「君がきらいだ。ずっと疎ましかったんだ。メレアポリスを恨む僕の心を変えてしまうから……。僕はこの国を憎んでいたかった」
暗い声音でつぶやく相手を、ティテュスは涙にぬれた目で見上げた。
「わたしはあなたが大好きよ……」
一族の名を負って神殿の門をくぐった以上、勝手は許されない。ティテュスは巫女として立派に聖婚の務めを果たしていくつもりだ。彼への想いに殉じるわけにはいかない。
「でも最初の一度は、どうしてもあなたがよかったの――」
うっとりとそう打ち明けると、彼はつらそうに眉根の皺を深くした。
「本当に君は……思い知らせてやりたくなるね」
菫色の瞳が昏く見つめてくる。
汗ばんだティテュスの肌はぬめりを帯び、篝火を受けて真珠色に艶めいている。皮膚の内側は濃密な淫悦に満たされて、今にもはちきれんばかり。
「後悔しても知らないよ」
そんな言葉と共に、大きな手がティテュスの首にふれてきた。その、意外な冷たさにひゅっと息を呑む。手はそのまま、うなじ、そして鎖骨へと滑り下りてくる。
「ぁ……」
熱く張りつめた肌は、たったそれだけで悩ましい心地よさに震えた。吐息のひとつにも感じてしまうほど昂った身体に、彼は手とくちびるとでふれてくる。
言葉とは裏腹に、仕草はひどく恭しいものだった。
「ぁ……、は、……ぁン……」
丁重でありながらも大胆に動く手は、ただでさえ燃え立っていたティテュスの官能を、ますますかき立ててくる。柔らかく優しい口づけも同様だった。香で昂った身体の感度を試そうとでもしているのか。耳朶や首筋をはじめ、くすぐったい箇所にばかりキスを落としてくる。そのたびにティテュスはひくひくと身体をこわばらせた。
「っ……、はぁ……ぁ、……アトレウス……」
自分のものとも思えない甘ったるい声がもれる。心地がいい。いかにも大切そうにふれてくる彼の手つきには感動しか湧いてこない。おまけに反応のひとつひとつを、菫色の瞳がじっと見つめてくるのだ。
たまらない羞恥を感じるが、それも彼のもたらす愉悦の前に、またたくまにかき消されてしまう。
(熱い……っ)
優しい愛撫は、くり返し達した後でさらなる激しい渇望に喘ぐ身には、つらい仕打ちだった。
自慰で幾らか鎮まった淫欲が、ふたたび熱く深まっていく。じっとしていられず、ティテュスは頭を振りつつ絶え間なく身悶えた。焦れったさに追い詰められ、出口のない官能の迷宮の中で啼きあえぐ。
「つらいかもしれないけれど、それもまた女神への奉献だ」
壮絶に色めいた目で微笑まれ、やはり彼はアシタロテの神官なのだと感じる。こんな状態の相手を前にして、さらに歓びをもたらそうとするだなんて。
とぎれとぎれの嬌声の中でそう告げると、彼は小さな微笑みと共に返してきた。
「僕が君にふれられるのは、これ限りだろうからね。すべてを目に焼きつけておきたいんだ」
ひどく切なげな声に胸が疼く。まさにその時、アトレウスの手がすくい上げるようにして、ふっくらとした胸を包み込んできた。
「ここは二年前よりずいぶん大きくなった」
「そ、そう……っ?」
「でも感じやすさは変わらないようだね」
強すぎない力加減で、ゆったりと押しまわされる。大きな手だ。
「はぅ……んっ……」
こわれものを扱うかのような、優しい愛撫が恨めしくてたまらない。決して急かさない手つきは、なまめかしく官能的だった。身体ばかりが煽られて、肝心の刺激が足りずに煩悶が増すことになる。
「アトレウス……ぁ、あぁっ……」
はしたない懇願をしようとしたところで、硬くなった頂をくりっとひねられた。甘い痛みに身体の芯がかき鳴らされる。と、それに誘われたように、押し上げてこんもりとしたふくらみの先に、彼は端整な顔を近づけてきた。
真っ赤に充血した尖りに吸いつき、ねっとりと舌先をからめてくる。
「あぁぁン……っ」
あまりにも淫猥な心地よさに、一気に快楽の階を昇ってしまいそうになった。しかし――あと少しのところで届かない。揉む時と同じく、こちらもやんわりと弄ぶ舐め方のせいか。敏感な先端は甘く痺れるばかりで、快楽の喫水はなかなか決壊しない。
手が届きそうなところにある高みに達したくて、ティテュスは汗にまみれた身体をひくつかせてすすり泣く。
「やぁ、……もうダメ……っ、ぁっ、もう……おねがい……っ」
うわごとのように言いながら、気づけば自分で慰めようと右手を下肢にのばしていた。しかしもちろん、目的の場所にたどり着く前に、彼につかまれる。
「僕に任せて」
そう言うと手にキスをしてくる。ティテュスはぽろぽろと涙をこぼして訴えた。
「いじわるしないで……」
「……わかったよ」
しかたがないと言わんばかりの顔で、アトレウスは身を起こし、ティテュスの両のひざ頭をつかむ。そしてゆっくり左右に押し広げてきた。それだけで、ぬれそぼった花びらが、ちゅく……と音を立てる。
「……いや……っ」
恥ずかしさに顔が燃える。どろどろに濡れていることも、そんな場所をのぞき込まれていることも、両方耐えがたかった。なぜなら、そこには本来あるべきものがない。
アシタロテ神殿の巫女は皆、普段からくり返し蜜蝋と香油を使って全身の体毛を取り除いている。よってティテュスのそこも子供のようにつるつるである。
市井の人々と一線を画す、聖性を演出するためのしきたりであるものの、余すことなく見られてしまうかと思うと恥ずかしくてたまらなかった。それでなくても今はぽってりと赤く花開いて、しとどに濡れている。おまけに先ほどまでいじっていた雌しべは、ぴんと勃ってしまっている。
「まさか君のこんな姿が見られるだなんてね……」
目を細めて見下ろしていたアトレウスは、穏やかながら不穏な微笑みを浮かべた。
太ももがブルブルと震える。喉と背筋を大きく反らしたまま、ティテュスは何度目かわからない絶頂へと突き上げられた。
自らの指で、いったい幾度昇り詰めたことだろう。
そのたびに下肢をぬらす体液があふれて流れることに気付いた。いまやキトンが尻に貼りついて取れないほどに濡れている。
淫猥な行為にふけった証のようで恥ずかしい。にもかかわらず、身の内の疼きはいっこうに治まらなかった。押し寄せる快感にしばらくの間は陶酔するも、また欲求が頭をもたげるのだ。
「たすけて、アトレウス……」
充血した淫芯を自ら転がしながら、小さな声ですすり泣く。
何をしても満たされず、もうどうすればいいのかわからない。ただただ身体が熱い。
「たすけてぇ……」
途方に暮れて、ティテュスはかすかな嗚咽をこぼした。快楽の涙にぬれた眼差しを、篝火の向こうの闇へと向ける。
――と。
ふいに闇の動く気配がした。現れたキトンの裾から視線を上げていけば、文字通り夢にまで見た相手が自分を見下ろしている。
「アトレウス……」
彼はひどく難しい顔をしていた。悩みに悩んだ末にやってきたとでもいうかのような、ひどい渋面である。きれいな顔が深い苦悩に染まり、ますます魅力的だ。
ティテュスは安堵のあまり、ぽろぽろと新たな涙をこぼした。
「アトレウス、待ってた……。来てくれるって信じてた……」
「来るつもりはなかった。……来てはいけなかった」
癖の強い前髪の陰から、菫色の眼差しが苦しげにこちらを見下ろしている。ティテュスから視線をそらさないまま、彼はゆっくりと片膝をついた。
「二年前の君は賢かった。血迷った僕を、きちんと撥ねのけたのだから」
「ずっと後悔してた……」
そうつぶやいたくちびるを、彼の人さし指がそっと押さえる。
「君がきらいだ。ずっと疎ましかったんだ。メレアポリスを恨む僕の心を変えてしまうから……。僕はこの国を憎んでいたかった」
暗い声音でつぶやく相手を、ティテュスは涙にぬれた目で見上げた。
「わたしはあなたが大好きよ……」
一族の名を負って神殿の門をくぐった以上、勝手は許されない。ティテュスは巫女として立派に聖婚の務めを果たしていくつもりだ。彼への想いに殉じるわけにはいかない。
「でも最初の一度は、どうしてもあなたがよかったの――」
うっとりとそう打ち明けると、彼はつらそうに眉根の皺を深くした。
「本当に君は……思い知らせてやりたくなるね」
菫色の瞳が昏く見つめてくる。
汗ばんだティテュスの肌はぬめりを帯び、篝火を受けて真珠色に艶めいている。皮膚の内側は濃密な淫悦に満たされて、今にもはちきれんばかり。
「後悔しても知らないよ」
そんな言葉と共に、大きな手がティテュスの首にふれてきた。その、意外な冷たさにひゅっと息を呑む。手はそのまま、うなじ、そして鎖骨へと滑り下りてくる。
「ぁ……」
熱く張りつめた肌は、たったそれだけで悩ましい心地よさに震えた。吐息のひとつにも感じてしまうほど昂った身体に、彼は手とくちびるとでふれてくる。
言葉とは裏腹に、仕草はひどく恭しいものだった。
「ぁ……、は、……ぁン……」
丁重でありながらも大胆に動く手は、ただでさえ燃え立っていたティテュスの官能を、ますますかき立ててくる。柔らかく優しい口づけも同様だった。香で昂った身体の感度を試そうとでもしているのか。耳朶や首筋をはじめ、くすぐったい箇所にばかりキスを落としてくる。そのたびにティテュスはひくひくと身体をこわばらせた。
「っ……、はぁ……ぁ、……アトレウス……」
自分のものとも思えない甘ったるい声がもれる。心地がいい。いかにも大切そうにふれてくる彼の手つきには感動しか湧いてこない。おまけに反応のひとつひとつを、菫色の瞳がじっと見つめてくるのだ。
たまらない羞恥を感じるが、それも彼のもたらす愉悦の前に、またたくまにかき消されてしまう。
(熱い……っ)
優しい愛撫は、くり返し達した後でさらなる激しい渇望に喘ぐ身には、つらい仕打ちだった。
自慰で幾らか鎮まった淫欲が、ふたたび熱く深まっていく。じっとしていられず、ティテュスは頭を振りつつ絶え間なく身悶えた。焦れったさに追い詰められ、出口のない官能の迷宮の中で啼きあえぐ。
「つらいかもしれないけれど、それもまた女神への奉献だ」
壮絶に色めいた目で微笑まれ、やはり彼はアシタロテの神官なのだと感じる。こんな状態の相手を前にして、さらに歓びをもたらそうとするだなんて。
とぎれとぎれの嬌声の中でそう告げると、彼は小さな微笑みと共に返してきた。
「僕が君にふれられるのは、これ限りだろうからね。すべてを目に焼きつけておきたいんだ」
ひどく切なげな声に胸が疼く。まさにその時、アトレウスの手がすくい上げるようにして、ふっくらとした胸を包み込んできた。
「ここは二年前よりずいぶん大きくなった」
「そ、そう……っ?」
「でも感じやすさは変わらないようだね」
強すぎない力加減で、ゆったりと押しまわされる。大きな手だ。
「はぅ……んっ……」
こわれものを扱うかのような、優しい愛撫が恨めしくてたまらない。決して急かさない手つきは、なまめかしく官能的だった。身体ばかりが煽られて、肝心の刺激が足りずに煩悶が増すことになる。
「アトレウス……ぁ、あぁっ……」
はしたない懇願をしようとしたところで、硬くなった頂をくりっとひねられた。甘い痛みに身体の芯がかき鳴らされる。と、それに誘われたように、押し上げてこんもりとしたふくらみの先に、彼は端整な顔を近づけてきた。
真っ赤に充血した尖りに吸いつき、ねっとりと舌先をからめてくる。
「あぁぁン……っ」
あまりにも淫猥な心地よさに、一気に快楽の階を昇ってしまいそうになった。しかし――あと少しのところで届かない。揉む時と同じく、こちらもやんわりと弄ぶ舐め方のせいか。敏感な先端は甘く痺れるばかりで、快楽の喫水はなかなか決壊しない。
手が届きそうなところにある高みに達したくて、ティテュスは汗にまみれた身体をひくつかせてすすり泣く。
「やぁ、……もうダメ……っ、ぁっ、もう……おねがい……っ」
うわごとのように言いながら、気づけば自分で慰めようと右手を下肢にのばしていた。しかしもちろん、目的の場所にたどり着く前に、彼につかまれる。
「僕に任せて」
そう言うと手にキスをしてくる。ティテュスはぽろぽろと涙をこぼして訴えた。
「いじわるしないで……」
「……わかったよ」
しかたがないと言わんばかりの顔で、アトレウスは身を起こし、ティテュスの両のひざ頭をつかむ。そしてゆっくり左右に押し広げてきた。それだけで、ぬれそぼった花びらが、ちゅく……と音を立てる。
「……いや……っ」
恥ずかしさに顔が燃える。どろどろに濡れていることも、そんな場所をのぞき込まれていることも、両方耐えがたかった。なぜなら、そこには本来あるべきものがない。
アシタロテ神殿の巫女は皆、普段からくり返し蜜蝋と香油を使って全身の体毛を取り除いている。よってティテュスのそこも子供のようにつるつるである。
市井の人々と一線を画す、聖性を演出するためのしきたりであるものの、余すことなく見られてしまうかと思うと恥ずかしくてたまらなかった。それでなくても今はぽってりと赤く花開いて、しとどに濡れている。おまけに先ほどまでいじっていた雌しべは、ぴんと勃ってしまっている。
「まさか君のこんな姿が見られるだなんてね……」
目を細めて見下ろしていたアトレウスは、穏やかながら不穏な微笑みを浮かべた。