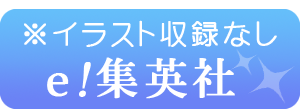偽りの蜜夜
将帥は高級娼婦の愛欲と背信に溺れ
あまおう紅 イラスト/蔀シャロン
「顔が赤いな」
からかい交じりに指摘してくる相手を、ルチアは軽くにらんだ。
「先ほどのお屋敷でも飲んだので、少し酔ってしまっていて……」
(いけない。子供のようなところを見透かされてはだめ。落ち着いて……)
意識して微笑みを浮かべながら自分に言い聞かせる。客に振り回されてはならない。常に余裕を忘れず、場の主導権をにぎらなければ。それが高級娼婦というものである。
シルヴィアたちの教えを思い返しながら、ルチアは誘うように小首をかしげた。
「賭けをしませんか?」
「賭け?」
「えぇ。ここから、あそこにある寝室の入口まで、何歩で到着するか。二人で予想して、実際の数に近かったほうが、相手に何かひとつ願いをかなえてもらうんです」
「いいだろう――」
アルセニオは興味を引かれたようだ。続き間になっている寝室の入口を見やる。
「途中にある椅子とテーブルを避けて……二十歩くらいか」
「わたしは三十歩だと思います」
「そんなにはないよ」
「では歩いてみてください、アル様。わたしを抱いて」
「……え」
彼に向けて両手を差し出したルチアを見下ろして、彼は苦笑した。
「なるほどな。してやられたよ」
そう言いながらも彼は、ルチア横抱きにして抱き上げる。
「高い……っ」
彼の首筋に腕をまわしてはしゃぐルチアを抱いたまま、アルセニオは歩き出した。が、足元が見えないためだろう。いつもより少し歩幅が小さくなる。数えたところ、寝室の入口までは二十五歩だった。
「……真ん中ですね」
「いや、ここは賢い君に勝ちを譲ろう」
寝室の中には、ダマスク織の華麗な天蓋を有した大きなベッドが据えられている。部屋に入っていった彼は、抱いていたルチアをその上にゆっくりと下ろした。
ルチアは逞しい首筋に腕をかけたまま、ブランデー色の瞳を振り仰いだ。
「お互いに願いをかなえ合うのはいかがでしょう?」
「いいね」
ルチアの両脇に手をついて覆いかぶさり、彼は楽しげに訊ねてくる。
「ではまず君の願いをきこう」
「なるべく、優しくしてください……」
初めての時は、そう言えば喜ばれると教えられたことを、内心どこまでも本気で言うと、アルセニオはくすりと笑う。
「元よりそのつもりだ」
必死に何でもないふうを装っていられたのは、そこまでだった。
慣れたしぐさで自分の服を脱いでいくアルセニオを前にして、ルチアも同じようにしようとするも、手がふるえてしまい、リボンの結び目ひとつうまく解けない。
「…………っ」
焦ったルチアが力まかせに引っ張ると、逆に結び目は固くなってしまった。
ますます緊張してしまったルチアの手に、アルセニオが微笑みながら手を置いてくる。
「貸してみろ」
彼は大きな手で器用にリボンを解き、ゆっくりとルチアのドレスを脱がせていった。その間、失態に真っ赤になりながら、ルチアは目の前にある上半身裸の身体をまじまじと見てしまう。
用事を言いつけられて、シルヴィアやモリーナの部屋を訪ねた時、異性の裸を目にしたことは何度かある。
アルセニオはその中のどれよりも鍛えられ、無駄な肉がひとつもないほど引き締まって見えた。がっしりとした首筋も、胸板も、割れた腹筋も逞しく、見るだけでドキドキしてしまう。ほどよく日に焼けてなめらかな肌は、燭台の火を受けてなまめかしい。
ルチアのコルセットのひもを緩めて外しながら、アルセニオが苦笑交じりに言った。
「日々鍛錬をしているので、見られて困ることもないが……。そこまでおもしろいものか?」
「え?」
声をかけられてハッとする。穴が開くほど、じっと眺めてしまっていたのだ。
「あ、いえ……っ、た――」
慌てるあまり裏返りそうになる声を、ルチアは何とか抑えた。
「逞しいので、見とれてしまいました……」
気がつけば身に着けていたものは、下着以外すべて脱がされている。少し落ち着いたルチアは、自分で下着をはだけながら、ふと訊ねた。
「ところで……アル様のお願いは?」
「終わるまでに考えておくよ」
一糸まとわぬ姿になったルチアを、今度は彼がじっと見つめてくる。
「きれいだ……」
ささやきながら、大きな手が太ももからわき腹までを撫で上げてくる。硬い皮膚の感触に肌が粟立った。
そのまま肌を滑った手は、胸のふくらみを包み込み、やんわりと押しまわしてくる。柔肉を押しつぶす手の動きに、緊張のあまり息が震えた。
「…………っ」
自分でふれても何ともない場所だというのに、彼にさわられていると思うと、恥ずかしくてたまらない。
はじめは様子を見るふうだった手の動きは、次第に大胆になっていった。手のひら全体でねっとりと柔肉を押しまわされ、余計に息が上がってしまう。たわんで形を変えるふくらみは、自分のものながら妙にいやらしい。
おまけにぐいぐいと手のひらで刺激された先端が、何やらむずむずし始め、全身がぞくりと震える。
「……ふ……っ」
何よりも恥ずかしいのは、未知の感覚に戸惑い、視線を揺らすルチアを、アルセニオが余すことなく見下ろしていることだ。
形を変えて硬くなった柔肉の先端を、糸をこよるようにつまんで転がしながら、褐色の眼差しはひと時もルチアから離れることがない。
「……ぁ」
くりくりといじられた部分が甘く痺れ、ルチアはぴくん、と背中を反らしてしまった。そんな姿まで見つめられ、ただでさえ真っ赤な頬が、さらに色づいてしまう。
「どうして……そんなに見るんですか?」
「言ったろう? 見極めているのさ」
「何を……」
絶え間なく動く指に、くにくにと転がされているうちに、そこはますます硬く尖っていく。まるで茱萸のようだ。
指で捏ねられるたび下腹がずくずくと疼き、焦れた身体が火照っていく。
「ん……っ」
「子供のように無垢な君が、本当に無垢なのか、それともふりが上手な凄腕なのかを見極めている」
つまりはルチアの物慣れない様子が、経験がないためか、それとも経験がないふうを装って彼を喜ばせようとしているためか、疑っているということか。
「わ、わたしは本当に……ぁ、ん……っ」
「別にどちらでもいい。初物をありがたがる趣味はないんでな」
きゅ、きゅ、と乳首をつぶしながら、彼は肩を竦めた。痛みと甘さの絶妙な加減は心地よく、ルチアは息を詰めて上体を震わせる。
「だが知ってて騙されるのと、知らずに騙されるのとの間には、大きな隔たりがある」
「わたしは……っ――ぁっ、……ぁ、ぁ……っ」
騙してなどいない。そう訴えたいものの、卑猥な指の動きに胸は甘く疼き、変な声が抑えきれない。
胸の先端をいじられただけで、ひくひくと身悶えるルチアを見つめながら、彼は重い身体を少し下にずらしていった。
「案じるな。高級娼婦との恋は、騙し騙されが楽しいんだ。嘘をつかれたからと怒るほど無粋ではない」
そう言うや、彼はルチアに見せつけるように舌を出し、色づいて尖った部分をねろりと舐め上げてくる。
「はぁンっ……」
熱く、ざらりとした舌が、敏感な部分に襲いかかってくる。想像以上に淫靡な感触に、ルチアの身体は大げさなほど震えてしまった。
アルセニオは反対側の胸をいじりながら、そんなルチアをおもしろそうに眺めてくる。
「だが簡単に騙されては、仮にも遊び人で鳴らしている男として立つ瀬がないからな」
逞しい腕でルチアの腰を抱え込み、押さえつけた上で、彼はそれまでいじりまわしていた乳首に本格的に吸いついてきた。凝りきった粒が熱く柔らかな口腔に包み込まれ、蛇のような舌に絡みつかれて、ねとねとと扱かれる。
「やぁっ、アル様、そんなに舐めては……ぁっ、ん、ん……っ」
(いや、何これ……っ)
熱くぬるついた口腔内で、柔肉ごと捏ねられるように舐めまわされるのは、思っていた以上にいやらしく、うっとりするほど気持ちがいい。
「ひぁ、ぁン……っ」
こういう時の反応は、初めは慎ましく、次第に大きく――そんな指導も吹き飛んでしまう。全身を駆けめぐる甘い疼きに、とてもじっとしていられない。
からかい交じりに指摘してくる相手を、ルチアは軽くにらんだ。
「先ほどのお屋敷でも飲んだので、少し酔ってしまっていて……」
(いけない。子供のようなところを見透かされてはだめ。落ち着いて……)
意識して微笑みを浮かべながら自分に言い聞かせる。客に振り回されてはならない。常に余裕を忘れず、場の主導権をにぎらなければ。それが高級娼婦というものである。
シルヴィアたちの教えを思い返しながら、ルチアは誘うように小首をかしげた。
「賭けをしませんか?」
「賭け?」
「えぇ。ここから、あそこにある寝室の入口まで、何歩で到着するか。二人で予想して、実際の数に近かったほうが、相手に何かひとつ願いをかなえてもらうんです」
「いいだろう――」
アルセニオは興味を引かれたようだ。続き間になっている寝室の入口を見やる。
「途中にある椅子とテーブルを避けて……二十歩くらいか」
「わたしは三十歩だと思います」
「そんなにはないよ」
「では歩いてみてください、アル様。わたしを抱いて」
「……え」
彼に向けて両手を差し出したルチアを見下ろして、彼は苦笑した。
「なるほどな。してやられたよ」
そう言いながらも彼は、ルチア横抱きにして抱き上げる。
「高い……っ」
彼の首筋に腕をまわしてはしゃぐルチアを抱いたまま、アルセニオは歩き出した。が、足元が見えないためだろう。いつもより少し歩幅が小さくなる。数えたところ、寝室の入口までは二十五歩だった。
「……真ん中ですね」
「いや、ここは賢い君に勝ちを譲ろう」
寝室の中には、ダマスク織の華麗な天蓋を有した大きなベッドが据えられている。部屋に入っていった彼は、抱いていたルチアをその上にゆっくりと下ろした。
ルチアは逞しい首筋に腕をかけたまま、ブランデー色の瞳を振り仰いだ。
「お互いに願いをかなえ合うのはいかがでしょう?」
「いいね」
ルチアの両脇に手をついて覆いかぶさり、彼は楽しげに訊ねてくる。
「ではまず君の願いをきこう」
「なるべく、優しくしてください……」
初めての時は、そう言えば喜ばれると教えられたことを、内心どこまでも本気で言うと、アルセニオはくすりと笑う。
「元よりそのつもりだ」
必死に何でもないふうを装っていられたのは、そこまでだった。
慣れたしぐさで自分の服を脱いでいくアルセニオを前にして、ルチアも同じようにしようとするも、手がふるえてしまい、リボンの結び目ひとつうまく解けない。
「…………っ」
焦ったルチアが力まかせに引っ張ると、逆に結び目は固くなってしまった。
ますます緊張してしまったルチアの手に、アルセニオが微笑みながら手を置いてくる。
「貸してみろ」
彼は大きな手で器用にリボンを解き、ゆっくりとルチアのドレスを脱がせていった。その間、失態に真っ赤になりながら、ルチアは目の前にある上半身裸の身体をまじまじと見てしまう。
用事を言いつけられて、シルヴィアやモリーナの部屋を訪ねた時、異性の裸を目にしたことは何度かある。
アルセニオはその中のどれよりも鍛えられ、無駄な肉がひとつもないほど引き締まって見えた。がっしりとした首筋も、胸板も、割れた腹筋も逞しく、見るだけでドキドキしてしまう。ほどよく日に焼けてなめらかな肌は、燭台の火を受けてなまめかしい。
ルチアのコルセットのひもを緩めて外しながら、アルセニオが苦笑交じりに言った。
「日々鍛錬をしているので、見られて困ることもないが……。そこまでおもしろいものか?」
「え?」
声をかけられてハッとする。穴が開くほど、じっと眺めてしまっていたのだ。
「あ、いえ……っ、た――」
慌てるあまり裏返りそうになる声を、ルチアは何とか抑えた。
「逞しいので、見とれてしまいました……」
気がつけば身に着けていたものは、下着以外すべて脱がされている。少し落ち着いたルチアは、自分で下着をはだけながら、ふと訊ねた。
「ところで……アル様のお願いは?」
「終わるまでに考えておくよ」
一糸まとわぬ姿になったルチアを、今度は彼がじっと見つめてくる。
「きれいだ……」
ささやきながら、大きな手が太ももからわき腹までを撫で上げてくる。硬い皮膚の感触に肌が粟立った。
そのまま肌を滑った手は、胸のふくらみを包み込み、やんわりと押しまわしてくる。柔肉を押しつぶす手の動きに、緊張のあまり息が震えた。
「…………っ」
自分でふれても何ともない場所だというのに、彼にさわられていると思うと、恥ずかしくてたまらない。
はじめは様子を見るふうだった手の動きは、次第に大胆になっていった。手のひら全体でねっとりと柔肉を押しまわされ、余計に息が上がってしまう。たわんで形を変えるふくらみは、自分のものながら妙にいやらしい。
おまけにぐいぐいと手のひらで刺激された先端が、何やらむずむずし始め、全身がぞくりと震える。
「……ふ……っ」
何よりも恥ずかしいのは、未知の感覚に戸惑い、視線を揺らすルチアを、アルセニオが余すことなく見下ろしていることだ。
形を変えて硬くなった柔肉の先端を、糸をこよるようにつまんで転がしながら、褐色の眼差しはひと時もルチアから離れることがない。
「……ぁ」
くりくりといじられた部分が甘く痺れ、ルチアはぴくん、と背中を反らしてしまった。そんな姿まで見つめられ、ただでさえ真っ赤な頬が、さらに色づいてしまう。
「どうして……そんなに見るんですか?」
「言ったろう? 見極めているのさ」
「何を……」
絶え間なく動く指に、くにくにと転がされているうちに、そこはますます硬く尖っていく。まるで茱萸のようだ。
指で捏ねられるたび下腹がずくずくと疼き、焦れた身体が火照っていく。
「ん……っ」
「子供のように無垢な君が、本当に無垢なのか、それともふりが上手な凄腕なのかを見極めている」
つまりはルチアの物慣れない様子が、経験がないためか、それとも経験がないふうを装って彼を喜ばせようとしているためか、疑っているということか。
「わ、わたしは本当に……ぁ、ん……っ」
「別にどちらでもいい。初物をありがたがる趣味はないんでな」
きゅ、きゅ、と乳首をつぶしながら、彼は肩を竦めた。痛みと甘さの絶妙な加減は心地よく、ルチアは息を詰めて上体を震わせる。
「だが知ってて騙されるのと、知らずに騙されるのとの間には、大きな隔たりがある」
「わたしは……っ――ぁっ、……ぁ、ぁ……っ」
騙してなどいない。そう訴えたいものの、卑猥な指の動きに胸は甘く疼き、変な声が抑えきれない。
胸の先端をいじられただけで、ひくひくと身悶えるルチアを見つめながら、彼は重い身体を少し下にずらしていった。
「案じるな。高級娼婦との恋は、騙し騙されが楽しいんだ。嘘をつかれたからと怒るほど無粋ではない」
そう言うや、彼はルチアに見せつけるように舌を出し、色づいて尖った部分をねろりと舐め上げてくる。
「はぁンっ……」
熱く、ざらりとした舌が、敏感な部分に襲いかかってくる。想像以上に淫靡な感触に、ルチアの身体は大げさなほど震えてしまった。
アルセニオは反対側の胸をいじりながら、そんなルチアをおもしろそうに眺めてくる。
「だが簡単に騙されては、仮にも遊び人で鳴らしている男として立つ瀬がないからな」
逞しい腕でルチアの腰を抱え込み、押さえつけた上で、彼はそれまでいじりまわしていた乳首に本格的に吸いついてきた。凝りきった粒が熱く柔らかな口腔に包み込まれ、蛇のような舌に絡みつかれて、ねとねとと扱かれる。
「やぁっ、アル様、そんなに舐めては……ぁっ、ん、ん……っ」
(いや、何これ……っ)
熱くぬるついた口腔内で、柔肉ごと捏ねられるように舐めまわされるのは、思っていた以上にいやらしく、うっとりするほど気持ちがいい。
「ひぁ、ぁン……っ」
こういう時の反応は、初めは慎ましく、次第に大きく――そんな指導も吹き飛んでしまう。全身を駆けめぐる甘い疼きに、とてもじっとしていられない。