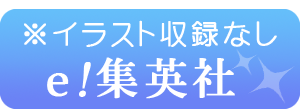王子様は淫魔の取り替えっ子でした
貞淑な令嬢をダメにするニョロの誘惑
あまおう紅 イラスト/のどさわ
「寝ちゃった?」
そぉっと声をかけると、ぱちりと目が開く。
「そんなはずないだろう?」
手をのばしてきた彼に囚われ、気がついた時には体勢が入れ替わっていた。
「あ……」
身体の下に組み敷かれていると気付き、ドキドキと見上げる。
「この時をどれだけ待ち焦がれていたか」
エセルはゆっくりと顔を傾け、レティシアにくちびるを重ねてきた。柔らかな感触にうっとりと目を閉じたところ、下唇を優しく嚙まれてドキドキする。
互いの息遣いを追いかけるうち、キスは次第に深いものになっていった。舌を絡めての濃厚な口づけはあまりにもはしたない淫惑に満ち、レティシアから慎みを奪っていく。
おまけに彼はいつものように、重ね合わせた舌から精気を吸ってくる。
「んんん……っ」
その瞬間、下腹の奥でぶわりと、えもいわれぬ熱が噴き出した。身体中がぞくぞくと甘い快感に痺れ、レティシアは身震いする。それは彼に吸われていく間にも淫らな余韻をまき散らし、肌という肌を粟立たせた。
「ん、ふ……っ」
身をよじるレティシアをベッドに押さえつけるようにして、彼はますます深くくちびるを奪ってくる。いつもは優しい彼の強引さに、悩ましい気分が昂られていく。
夢中で舌を絡め取られ、唾液ごと精気を吸われ、レティシアは熱く甘い快楽に溺れそうになった。
しかし必死にキスに応じるうち、自分の身体に起きた変化に、ふいに彼の身体を押しのけて顔を背ける。
「まっ……、まって、こんなのダメ……っ」
「どうして?」
はぁはぁと喘ぐ妻の真っ赤な頬に、彼はねだるように口づけてきた。さらに顎に、鎖骨にとキスをした後、上目づかいで訊ねてくる。
「どうしてダメなんだい?」
「……ぬれちゃうから……」
あまりにも本格的なキスのせいで、そこはすでにとろとろと蜜をこぼし始めていた。このままでは夜着に染みをつけてしまいかねない。
聞こえるか聞こえないかの、羞恥に染まった答えに、エセルはくしゃりと笑みくずれた。
「今日はたくさんぬらしていいんだよ」
そう言うと、薄い絹の夜着をするすると脱がしてくる。露になった胸は、キスのせいで大きく上下していた。仄暗い中、燭台の明かりに照らされたふくらみを見下ろして、彼は感動するようにうっとりとつぶやく。
「白い……、きれいだ……」
おずおずと片手で包み込むそぶりからは、初めて女性のそこにふれるためらいが伝わってくる。ふくらみにふれると、興味津々といった手つきでたぷたぷと揺らしてきた。
「柔らかい……」
欲望に染まったアイスブルーの瞳がちらりと見上げてくる。
「今まで、こんなにドキドキするものにさわったことがない」
まっすぐな報告に、レティシアの鼓動までうるさいほど高まっていった。
自分の肌に彼の指がわずかに埋まる様まで恥ずかしく、そっと目を逸らす。
「そういうこと、言わないで……」
「どうして?」
「おかしな気分になってしまうから……」
子供を作るという夫婦の大切な責務を、きちんと果たしたいと思う。しかしそれは理性を失いすぎない程度に、節度を持って行われるべきだ。あまりにも羽目を外しすぎては――
レティシアの真剣な苦言は、笑み交じりのエセルの口づけによって途切れた。
「寝室ではおかしくなっていいんだよ。だいたいこんなこと、羽目を外さずにできないじゃないか」
「でも……」
「それに、なるべく相手を感じさせたいというのが淫魔の本能だ。素直に歓んでほしい」
「そん――ん……っ」
異論を口にしかけたくちびるが、彼のくちびるに塞がれる。キスで反論を封じながら、彼はレティシアのふくらみの弾力を手のひら全体で堪能した。
はじめ力加減に迷うふうだった手つきも、ほどなく慣れたものになっていく。包み込むようにゆったりと揉んでいた大きな手に、ふいに色づいた部分を指でくすぐられ、身体がぴくんと震えてしまう。
「んっ……」
いつもは平らなそこが芯を持って勃ち上がってくると、指先は周囲を優しくなぞった。指がひらめくたびに上体がひくついてしまう。
身をよじって吐息をこぼす反応を受け、彼は尖ったそこを指先で軽くつまんだ。
「こんなに硬くなった……」
指の腹で捏ねるようにふにふにと転がした後、手で柔肉を寄せ上げて、ふくらみの上でピンと尖った先端をしげしげと見つめる。
レティシアは顔を両手で覆った。
「そんなふうに見ないで……っ」
「見るさ。君の恥ずかしがる顔を見られるなら、余計にね」
ぬけぬけと言うと、彼は真っ赤に色づいた頂に吸い寄せられるように、顔を寄せて口に含んでしまう。
「あぁ……っ」
硬く凝って疼く粒が、熱くぬれた感触に包み込まれ、レティシアは耐えきれずに身悶えた。
それを見ながらエセルはさらにねっとりと舌を絡みつけてくる。口の中でねとねとと転がされ、弾力を楽しむように舌で押しつぶされる。
「……んっ、……はぁっ、……ん……っ」
エセルの口腔内の愛撫はひどく卑猥で執拗だった。あまり感じてはならない、というレティシアの思いを試すかのようでもある。経験のない身にはひとたまりもなかった。
反応を引き出そうとするかのように絡みつく舌に扱かれれば、ぴくんぴくんと震えてしまう。
「んっ、……ふぁっ……」
快楽にあえいだ瞬間、疼く頂からじゅっと精気を吸われた。
キスの最中に吸われるのと同じ、熱く、甘苦しい愉悦が弾け、思わず腰が浮き上がる。
「あぁっ……!」
嚙みしめていた唇が開き、はしたない声がもれてしまう。
吸われた後は耐えがたいほど淫らに痺れるのだ。敏感な場所への責め苦に、眉を絞って左右に首を振った。
「だめっ、……だめ、それ……!」
淫らな感触を心地よく感じるものの、素直にそれに浸るにはまだためらいが残る――そんなレティシアの良識を、彼は淡く微笑んで嬲ってくる。
「でも今、びくってしたじゃないか。胸から吸われるの、気持ちいいかい?」
「う……っ」
「もっとしてあげる」
「だめ、だめぇ……っ」
頭を振ったものの、ふにゃふにゃの声が顧みられることはなかった。
興奮に尖った乳首をぬるついてザラザラした舌に舐めしゃぶられ、ちゅぅっと精気を吸われれば上体がなまめかしく跳ねてしまう。繊細な先端を包み込む、熱く濃厚な快感に頤を高く上げて身悶えずにいられない。
「ふぁぅ……っ、ぁ……っ」
「君の精気、頬が落ちそうなほど美味しいよ。性的な興奮を感じている精気は味が熟成していくようだ」
さんざんレティシアを啼かせた後、彼はぺろりとくちびるを舐めて顔を持ち上げた。
「君は? 気持ちいい?」
直截的な問いに、淫悦から逃れようと身体をくねらせていたレティシアはこくこくとうなずく。気持ちが良すぎておかしくなりそうだ。
と、
「じゃあたくさんぬれた? 下、さわってもいい?」
「…………っ」
あっけらかんとした要求に耳を疑い、涙がにじんだ。
そこはすでに自分でも信じられないほどぬれているのがわかる。そんな場所をさわるなんて――
(そんないやらしいことをするの……!?)
目をうるうるさせて見上げる妻を目にして、さすがにエセルは慌てたようだ。顔をのぞきこんでくる。
「泣かないで、レティシア。私は君にいやなことをしている?」
「いいえ……っ」
「じゃあなぜ泣きそうなんだい?」
「……は、……恥ずかしいから……っ」
今にも涙のこぼれそうな瞳で見上げて言うと、彼は眩暈でも感じたように目を閉じた。
そぉっと声をかけると、ぱちりと目が開く。
「そんなはずないだろう?」
手をのばしてきた彼に囚われ、気がついた時には体勢が入れ替わっていた。
「あ……」
身体の下に組み敷かれていると気付き、ドキドキと見上げる。
「この時をどれだけ待ち焦がれていたか」
エセルはゆっくりと顔を傾け、レティシアにくちびるを重ねてきた。柔らかな感触にうっとりと目を閉じたところ、下唇を優しく嚙まれてドキドキする。
互いの息遣いを追いかけるうち、キスは次第に深いものになっていった。舌を絡めての濃厚な口づけはあまりにもはしたない淫惑に満ち、レティシアから慎みを奪っていく。
おまけに彼はいつものように、重ね合わせた舌から精気を吸ってくる。
「んんん……っ」
その瞬間、下腹の奥でぶわりと、えもいわれぬ熱が噴き出した。身体中がぞくぞくと甘い快感に痺れ、レティシアは身震いする。それは彼に吸われていく間にも淫らな余韻をまき散らし、肌という肌を粟立たせた。
「ん、ふ……っ」
身をよじるレティシアをベッドに押さえつけるようにして、彼はますます深くくちびるを奪ってくる。いつもは優しい彼の強引さに、悩ましい気分が昂られていく。
夢中で舌を絡め取られ、唾液ごと精気を吸われ、レティシアは熱く甘い快楽に溺れそうになった。
しかし必死にキスに応じるうち、自分の身体に起きた変化に、ふいに彼の身体を押しのけて顔を背ける。
「まっ……、まって、こんなのダメ……っ」
「どうして?」
はぁはぁと喘ぐ妻の真っ赤な頬に、彼はねだるように口づけてきた。さらに顎に、鎖骨にとキスをした後、上目づかいで訊ねてくる。
「どうしてダメなんだい?」
「……ぬれちゃうから……」
あまりにも本格的なキスのせいで、そこはすでにとろとろと蜜をこぼし始めていた。このままでは夜着に染みをつけてしまいかねない。
聞こえるか聞こえないかの、羞恥に染まった答えに、エセルはくしゃりと笑みくずれた。
「今日はたくさんぬらしていいんだよ」
そう言うと、薄い絹の夜着をするすると脱がしてくる。露になった胸は、キスのせいで大きく上下していた。仄暗い中、燭台の明かりに照らされたふくらみを見下ろして、彼は感動するようにうっとりとつぶやく。
「白い……、きれいだ……」
おずおずと片手で包み込むそぶりからは、初めて女性のそこにふれるためらいが伝わってくる。ふくらみにふれると、興味津々といった手つきでたぷたぷと揺らしてきた。
「柔らかい……」
欲望に染まったアイスブルーの瞳がちらりと見上げてくる。
「今まで、こんなにドキドキするものにさわったことがない」
まっすぐな報告に、レティシアの鼓動までうるさいほど高まっていった。
自分の肌に彼の指がわずかに埋まる様まで恥ずかしく、そっと目を逸らす。
「そういうこと、言わないで……」
「どうして?」
「おかしな気分になってしまうから……」
子供を作るという夫婦の大切な責務を、きちんと果たしたいと思う。しかしそれは理性を失いすぎない程度に、節度を持って行われるべきだ。あまりにも羽目を外しすぎては――
レティシアの真剣な苦言は、笑み交じりのエセルの口づけによって途切れた。
「寝室ではおかしくなっていいんだよ。だいたいこんなこと、羽目を外さずにできないじゃないか」
「でも……」
「それに、なるべく相手を感じさせたいというのが淫魔の本能だ。素直に歓んでほしい」
「そん――ん……っ」
異論を口にしかけたくちびるが、彼のくちびるに塞がれる。キスで反論を封じながら、彼はレティシアのふくらみの弾力を手のひら全体で堪能した。
はじめ力加減に迷うふうだった手つきも、ほどなく慣れたものになっていく。包み込むようにゆったりと揉んでいた大きな手に、ふいに色づいた部分を指でくすぐられ、身体がぴくんと震えてしまう。
「んっ……」
いつもは平らなそこが芯を持って勃ち上がってくると、指先は周囲を優しくなぞった。指がひらめくたびに上体がひくついてしまう。
身をよじって吐息をこぼす反応を受け、彼は尖ったそこを指先で軽くつまんだ。
「こんなに硬くなった……」
指の腹で捏ねるようにふにふにと転がした後、手で柔肉を寄せ上げて、ふくらみの上でピンと尖った先端をしげしげと見つめる。
レティシアは顔を両手で覆った。
「そんなふうに見ないで……っ」
「見るさ。君の恥ずかしがる顔を見られるなら、余計にね」
ぬけぬけと言うと、彼は真っ赤に色づいた頂に吸い寄せられるように、顔を寄せて口に含んでしまう。
「あぁ……っ」
硬く凝って疼く粒が、熱くぬれた感触に包み込まれ、レティシアは耐えきれずに身悶えた。
それを見ながらエセルはさらにねっとりと舌を絡みつけてくる。口の中でねとねとと転がされ、弾力を楽しむように舌で押しつぶされる。
「……んっ、……はぁっ、……ん……っ」
エセルの口腔内の愛撫はひどく卑猥で執拗だった。あまり感じてはならない、というレティシアの思いを試すかのようでもある。経験のない身にはひとたまりもなかった。
反応を引き出そうとするかのように絡みつく舌に扱かれれば、ぴくんぴくんと震えてしまう。
「んっ、……ふぁっ……」
快楽にあえいだ瞬間、疼く頂からじゅっと精気を吸われた。
キスの最中に吸われるのと同じ、熱く、甘苦しい愉悦が弾け、思わず腰が浮き上がる。
「あぁっ……!」
嚙みしめていた唇が開き、はしたない声がもれてしまう。
吸われた後は耐えがたいほど淫らに痺れるのだ。敏感な場所への責め苦に、眉を絞って左右に首を振った。
「だめっ、……だめ、それ……!」
淫らな感触を心地よく感じるものの、素直にそれに浸るにはまだためらいが残る――そんなレティシアの良識を、彼は淡く微笑んで嬲ってくる。
「でも今、びくってしたじゃないか。胸から吸われるの、気持ちいいかい?」
「う……っ」
「もっとしてあげる」
「だめ、だめぇ……っ」
頭を振ったものの、ふにゃふにゃの声が顧みられることはなかった。
興奮に尖った乳首をぬるついてザラザラした舌に舐めしゃぶられ、ちゅぅっと精気を吸われれば上体がなまめかしく跳ねてしまう。繊細な先端を包み込む、熱く濃厚な快感に頤を高く上げて身悶えずにいられない。
「ふぁぅ……っ、ぁ……っ」
「君の精気、頬が落ちそうなほど美味しいよ。性的な興奮を感じている精気は味が熟成していくようだ」
さんざんレティシアを啼かせた後、彼はぺろりとくちびるを舐めて顔を持ち上げた。
「君は? 気持ちいい?」
直截的な問いに、淫悦から逃れようと身体をくねらせていたレティシアはこくこくとうなずく。気持ちが良すぎておかしくなりそうだ。
と、
「じゃあたくさんぬれた? 下、さわってもいい?」
「…………っ」
あっけらかんとした要求に耳を疑い、涙がにじんだ。
そこはすでに自分でも信じられないほどぬれているのがわかる。そんな場所をさわるなんて――
(そんないやらしいことをするの……!?)
目をうるうるさせて見上げる妻を目にして、さすがにエセルは慌てたようだ。顔をのぞきこんでくる。
「泣かないで、レティシア。私は君にいやなことをしている?」
「いいえ……っ」
「じゃあなぜ泣きそうなんだい?」
「……は、……恥ずかしいから……っ」
今にも涙のこぼれそうな瞳で見上げて言うと、彼は眩暈でも感じたように目を閉じた。