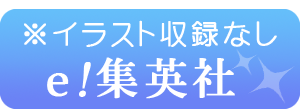後宮恋奏
太子が宮女と略奪婚にいたるまで 1
あまおう紅 イラスト/蓮えみこ
「ゆっくりと言ったのに、すまない。ここが気持ちよすぎて自制を失った…」
ここ、と言いながら、貴謳は屹立でぐじゅぐじゅと中をかきまわしてきた。
「ぁっ、ぁ、ぁン…っ」
悦いところを刺激され、びくびくと煩悶する。淫蕩な蜜路は、太くて硬いものにねだるように吸いついては奥へ奥へと引き込もうとする。
その感触を味わうように、彼は腰をゆるゆると前後させた。貫かれたまま奥を捏ねられ、背筋が弓なりに反りかえる。
「あっ! はぁ、ぁぁン…!」
彼は凛明の両膝を離し、左手で胸のふくらみをつかんだ。さらに右手で、大きく開かれた内股をなまめかしくなでまわす。達したばかりの敏感な身体は、そんな些細な愛撫にもひどく反応してしまう。
「ん…ぁ、ぁっ…」
下腹の奥がきゅんっと疼き、熱杭をうねうねと吸い上げた。
心地よさそうな彼の吐息が耳朶にふれる。
「凛明…。いくらしても足りない。一週間では、到底おまえを愛し尽くせない」
深い愉悦に陶然としながら、凛明もきれぎれに返した。
「もっと…たくさん、してください…っ。貴謳様、満足するまで…っ」
「そんなこと言われたら我慢がきかなくなる」
「かまいません…。できるだけ、思い出を――ぁあっ、あっ、はぁン!」
愛する人に貪られるのは嬉しい。そんな気持ちを伝えると、貴謳の雄茎がぐぐっと膨れて中を拡げる。それに喘ぐ間もなく、彼は情熱的な抽送を開始した。
「あぁっ、ひぁっ! ぁふっ、あっ、ぁあっ…!」
結合部でじゅぶぬぶと水音を立てながら、傲然と漲るものでくり返し責め立ててくる。力強く執拗な抽送は、楔の圧迫感に懊悩する凛明をさらに追い詰めてきた。
そうしながら、後ろから片手で荒々しく胸を揉みしだき、指先で先端を扱いてくびり出す。赤く尖った突起は、やや乱暴な指戯にもたまらない愉悦を発した。
「ふぁ…ぁ、ぁあっ…」
眉を絞ってよがる凛明をさらに啼かせようというのか、もう片方の手が指先でころころと淫芯を転がしてくる。とたん、鋭い快感が身の内を走り抜けた。
「やぁぁっ!」
根元まで剛直を呑み込んだ腰が、びくんびくんっと大きく跳ねる。
「こうされるの、好きだろう?」
「だめっ、いやあぁっ…、だめっ! だったらっ、それ…あっぁあっ…!」
たっぷりと蜜をまとった指で、敏感すぎる粒をくりゅくりゅ押しまわされ、夜空に向けて嬌声を迸らせる。
強すぎる快感から逃れようと、凛明は屹立を咥えたまま必死に腰を振った。しかし指はどこまでもついてきて、高みへ追い詰めてくる。
剛直にずんっずんっと突き上げながら、凛明は後ろに手をのばして、途方もない快感を送り込んでくる貴謳の頭を引き寄せた。そして首を反らし、肩越しにくちびるを重ねる。
自分ばかりが感じさせられるのは悔しいと、積極的に舌を絡めていくと、淫路を埋め尽くす彼のものがいっそう大きくなった。
「んん…っ」
内臓を押し上げる圧迫感に身震いする中、指で嬲られる淫芯から生じる歓喜がいよいよせっぱ詰まったものになり、凛明は髪を振り乱して、せり上がる恍惚の水位に身をまかせる。とたん。
「あぁっぁぁ…!」
身の内を貫く真っ白な快感によって頂の果てへ舞い上がる。不自由な態勢の身体をびくびくと痙攣させ、凛明は一人で昇り詰めた。
先ほど一度吐精したためか、貴謳はまだ余裕があるようだ。びきびきと昂る楔で硬直する凛明の淫路を揺さぶり、快楽の極みにある恋人をさらに啼かせる。
長い陶酔の後、硬いもので貫かれたまま、凛明は息も絶え絶えに背後の身体にもたれかかった。
薄紅色に上気した肩に、貴謳は何度も小さく口づけてくる。
「いつまでも続けていたい…」
悩ましい彼のささやきを鼓膜に注ぎ込まれ、ぞくぞくと背筋が粟立った。
「もっとしよう。な?」
ねだる声と共に、大きな手が胸の柔肉をねっとりと揉みまわし、達したばかりの繊細過ぎる尖りを指先で押しつぶしてくる。
「あぅっ、…まっ、まって、ぁっ、ぁ、はぁ…っ」
甘い痛みに身体の芯が痺れ、剛直を咥え込んだままの蜜洞が悩ましくうねる。そこをずんっと突き上げられ、甘苦しい衝撃に腰が砕けそうになった。
「やぁン…! まって、まってください…、はぁっ、ぁンっ…!」
「可愛い啼き声をもっと聞かせてくれ。旅先でそれを思い出して、独り寝を慰めるから」
冗談に模したささやきには、隠しようのないさみしさがにじんでいる。
喘ぎながら、凛明の胸はきゅっと締めつけられた。
何でもないふうを装っているものの、本当は異母兄である皇帝から無情な勅命を受けたことに、内心痛手を受けているのだろう。
(まるで死地に追いやるかのようなご下命だもの…)
快楽に霞む頭でふとそう考え、不安に心をつかまれる。
貴謳は兄に献身的に仕え、誠心誠意働くことによって、戦においても政務においても立派な結果を残してきた。しかしそのため、逆に皇帝から疎まれることになったという。
(なぜ陛下は、そんなに貴謳様を目の仇になさるのかしら…?)
現皇帝には目立った失点があるわけでもない。宮廷百官が認める游国の天子である。もっとどっしりと構え、得難い臣下として優秀な異母弟を受け入れればいいものを。
(貴謳様にもしものことがあれば、陛下だってお困りになるはずなのに…)
自分でひらめいた、縁起でもない思いつきを凛明はあわてて否定した。戦上手の貴謳に限って、もしものことなどあるはずがない。たとえ少ない兵数でも勝って帰ってくるだろう。
「…声を聞かせてくれ。いつでもはっきりと思い出せるように…」
切ない懇願に応じ、凛明はひときわ甘い声で啼いた。
「きお、さまぁ…ぁっ、ぁんっ、あぁン…!」
いつもより激しく身悶え、できる限り淫奔に腰を振る。
(こんなに好きになるなんて、思ってなかった…)
最初はひどい人だと思った。心の底から恨んだ。決して彼のものになどならないと信じていた。
しかし今は――。
(このことで、戦地に向かう貴謳様にわずかなりとも力を与えられるなら――)
凛明は、祈る気持ちで彼自身を最奥まで受け入れ、淫らに締めつけて、未熟ながら精いっぱいの快楽をもたらそうとする。
ほどなく貴謳は、凛明の腰を支えて速く重い律動を始めた。がつがつと突き上げ、凛明をどこまでも懊悩させ、やがてただでさえドロドロだった蜜壺の奥に精を迸らせる。
同時に達した二人の呼吸と喘ぎ声が交ざり合う中、彼は背後から両腕で強く抱きしめてきた。
「凛明…っ」
捕らえるように、あるいは縋るように、筋肉質な腕の中に囲われた凛明は、貴謳の肩に頭を預ける。
七夕の宵に披露する曲を練習しているのだろうか。宮殿のほうから古琴の音色が聞こえてくる。夜空を眺めれば、そこにはすでに、明日出会うはずの二つの星が輝いていた。
言い伝えによると織姫の星は、女の願いをかなえてくれるという。
(どうか…)
快楽の涙ににじむ月に向けて呼びかける。
どうか、皇帝による貴謳への冷遇が少しでも改まるように。兄を慕う貴謳の気持ちが報われるように。
そして何より――明日ここを発つ彼が、無事に帰ってきますように。
(どうか願いを聞き届けてください…)
抱きしめてくる腕に自分の手を重ね、凛明は思いを込めて、愛する相手との邂逅を果たそうとしている星を見つめ続けた。
ここ、と言いながら、貴謳は屹立でぐじゅぐじゅと中をかきまわしてきた。
「ぁっ、ぁ、ぁン…っ」
悦いところを刺激され、びくびくと煩悶する。淫蕩な蜜路は、太くて硬いものにねだるように吸いついては奥へ奥へと引き込もうとする。
その感触を味わうように、彼は腰をゆるゆると前後させた。貫かれたまま奥を捏ねられ、背筋が弓なりに反りかえる。
「あっ! はぁ、ぁぁン…!」
彼は凛明の両膝を離し、左手で胸のふくらみをつかんだ。さらに右手で、大きく開かれた内股をなまめかしくなでまわす。達したばかりの敏感な身体は、そんな些細な愛撫にもひどく反応してしまう。
「ん…ぁ、ぁっ…」
下腹の奥がきゅんっと疼き、熱杭をうねうねと吸い上げた。
心地よさそうな彼の吐息が耳朶にふれる。
「凛明…。いくらしても足りない。一週間では、到底おまえを愛し尽くせない」
深い愉悦に陶然としながら、凛明もきれぎれに返した。
「もっと…たくさん、してください…っ。貴謳様、満足するまで…っ」
「そんなこと言われたら我慢がきかなくなる」
「かまいません…。できるだけ、思い出を――ぁあっ、あっ、はぁン!」
愛する人に貪られるのは嬉しい。そんな気持ちを伝えると、貴謳の雄茎がぐぐっと膨れて中を拡げる。それに喘ぐ間もなく、彼は情熱的な抽送を開始した。
「あぁっ、ひぁっ! ぁふっ、あっ、ぁあっ…!」
結合部でじゅぶぬぶと水音を立てながら、傲然と漲るものでくり返し責め立ててくる。力強く執拗な抽送は、楔の圧迫感に懊悩する凛明をさらに追い詰めてきた。
そうしながら、後ろから片手で荒々しく胸を揉みしだき、指先で先端を扱いてくびり出す。赤く尖った突起は、やや乱暴な指戯にもたまらない愉悦を発した。
「ふぁ…ぁ、ぁあっ…」
眉を絞ってよがる凛明をさらに啼かせようというのか、もう片方の手が指先でころころと淫芯を転がしてくる。とたん、鋭い快感が身の内を走り抜けた。
「やぁぁっ!」
根元まで剛直を呑み込んだ腰が、びくんびくんっと大きく跳ねる。
「こうされるの、好きだろう?」
「だめっ、いやあぁっ…、だめっ! だったらっ、それ…あっぁあっ…!」
たっぷりと蜜をまとった指で、敏感すぎる粒をくりゅくりゅ押しまわされ、夜空に向けて嬌声を迸らせる。
強すぎる快感から逃れようと、凛明は屹立を咥えたまま必死に腰を振った。しかし指はどこまでもついてきて、高みへ追い詰めてくる。
剛直にずんっずんっと突き上げながら、凛明は後ろに手をのばして、途方もない快感を送り込んでくる貴謳の頭を引き寄せた。そして首を反らし、肩越しにくちびるを重ねる。
自分ばかりが感じさせられるのは悔しいと、積極的に舌を絡めていくと、淫路を埋め尽くす彼のものがいっそう大きくなった。
「んん…っ」
内臓を押し上げる圧迫感に身震いする中、指で嬲られる淫芯から生じる歓喜がいよいよせっぱ詰まったものになり、凛明は髪を振り乱して、せり上がる恍惚の水位に身をまかせる。とたん。
「あぁっぁぁ…!」
身の内を貫く真っ白な快感によって頂の果てへ舞い上がる。不自由な態勢の身体をびくびくと痙攣させ、凛明は一人で昇り詰めた。
先ほど一度吐精したためか、貴謳はまだ余裕があるようだ。びきびきと昂る楔で硬直する凛明の淫路を揺さぶり、快楽の極みにある恋人をさらに啼かせる。
長い陶酔の後、硬いもので貫かれたまま、凛明は息も絶え絶えに背後の身体にもたれかかった。
薄紅色に上気した肩に、貴謳は何度も小さく口づけてくる。
「いつまでも続けていたい…」
悩ましい彼のささやきを鼓膜に注ぎ込まれ、ぞくぞくと背筋が粟立った。
「もっとしよう。な?」
ねだる声と共に、大きな手が胸の柔肉をねっとりと揉みまわし、達したばかりの繊細過ぎる尖りを指先で押しつぶしてくる。
「あぅっ、…まっ、まって、ぁっ、ぁ、はぁ…っ」
甘い痛みに身体の芯が痺れ、剛直を咥え込んだままの蜜洞が悩ましくうねる。そこをずんっと突き上げられ、甘苦しい衝撃に腰が砕けそうになった。
「やぁン…! まって、まってください…、はぁっ、ぁンっ…!」
「可愛い啼き声をもっと聞かせてくれ。旅先でそれを思い出して、独り寝を慰めるから」
冗談に模したささやきには、隠しようのないさみしさがにじんでいる。
喘ぎながら、凛明の胸はきゅっと締めつけられた。
何でもないふうを装っているものの、本当は異母兄である皇帝から無情な勅命を受けたことに、内心痛手を受けているのだろう。
(まるで死地に追いやるかのようなご下命だもの…)
快楽に霞む頭でふとそう考え、不安に心をつかまれる。
貴謳は兄に献身的に仕え、誠心誠意働くことによって、戦においても政務においても立派な結果を残してきた。しかしそのため、逆に皇帝から疎まれることになったという。
(なぜ陛下は、そんなに貴謳様を目の仇になさるのかしら…?)
現皇帝には目立った失点があるわけでもない。宮廷百官が認める游国の天子である。もっとどっしりと構え、得難い臣下として優秀な異母弟を受け入れればいいものを。
(貴謳様にもしものことがあれば、陛下だってお困りになるはずなのに…)
自分でひらめいた、縁起でもない思いつきを凛明はあわてて否定した。戦上手の貴謳に限って、もしものことなどあるはずがない。たとえ少ない兵数でも勝って帰ってくるだろう。
「…声を聞かせてくれ。いつでもはっきりと思い出せるように…」
切ない懇願に応じ、凛明はひときわ甘い声で啼いた。
「きお、さまぁ…ぁっ、ぁんっ、あぁン…!」
いつもより激しく身悶え、できる限り淫奔に腰を振る。
(こんなに好きになるなんて、思ってなかった…)
最初はひどい人だと思った。心の底から恨んだ。決して彼のものになどならないと信じていた。
しかし今は――。
(このことで、戦地に向かう貴謳様にわずかなりとも力を与えられるなら――)
凛明は、祈る気持ちで彼自身を最奥まで受け入れ、淫らに締めつけて、未熟ながら精いっぱいの快楽をもたらそうとする。
ほどなく貴謳は、凛明の腰を支えて速く重い律動を始めた。がつがつと突き上げ、凛明をどこまでも懊悩させ、やがてただでさえドロドロだった蜜壺の奥に精を迸らせる。
同時に達した二人の呼吸と喘ぎ声が交ざり合う中、彼は背後から両腕で強く抱きしめてきた。
「凛明…っ」
捕らえるように、あるいは縋るように、筋肉質な腕の中に囲われた凛明は、貴謳の肩に頭を預ける。
七夕の宵に披露する曲を練習しているのだろうか。宮殿のほうから古琴の音色が聞こえてくる。夜空を眺めれば、そこにはすでに、明日出会うはずの二つの星が輝いていた。
言い伝えによると織姫の星は、女の願いをかなえてくれるという。
(どうか…)
快楽の涙ににじむ月に向けて呼びかける。
どうか、皇帝による貴謳への冷遇が少しでも改まるように。兄を慕う貴謳の気持ちが報われるように。
そして何より――明日ここを発つ彼が、無事に帰ってきますように。
(どうか願いを聞き届けてください…)
抱きしめてくる腕に自分の手を重ね、凛明は思いを込めて、愛する相手との邂逅を果たそうとしている星を見つめ続けた。