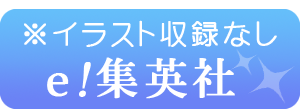後宮恋奏
太子が宮女と略奪婚にいたるまで 2
あまおう紅 イラスト/蓮えみこ
凛明の身体を蝕む媚薬の効果は深刻だった。彼女の話によると、即効性だという薬を二回も飲まされたという。
媚薬に関しては以前耳にしたことがあった。この国の薬学の歴史は古い。歴代皇帝が性欲を満たしてきた場所において、その類の研究がされていないはずがない。おそらく大変な効き目があるのだろう……と、噂を聞いた時には漠然と考えた。
その「効き目」を、まさに今、目の当たりにしている。
「よせ、凛明。服を脱ぐな……っ」
思わず制止してから、貴謳はハッとして周囲を見まわした。
馬車の窓には紗の、後ろの入口には厚手の垂れ幕がかかっているが、声が外に漏れないかひやひやしてしまう。
押さえつける貴謳の手の中で、凛明はなまめかしく身体をよじった。
「あつい……からだがあついの……っ」
「そんなにつらいのか……?」
「つらいです、きおうさま……。たすけて……」
真っ赤に上気した顔で、ハァハァと息を乱しながら、彼女は貴謳の手をつかみ、胸元の合わせの中に差し込もうとする。
「まっ、待て! それはマズい……!」
貴謳は慌てて彼女の服の中から手を引っこ抜いた。
こんな場所で胸の愛撫など始めれば、それだけで治まらなくなるのは目に見えている。何しろ彼女の胸はあまりにも柔らかく、頂を優しくつまんだだけで可愛い声を出すほど感じやすいのだ。
初夜の記憶を反芻して幸せな気分に浸っていると、凛明が子供のように声を上げてしくしくと泣きだした。
「どうした!?」
「きおうさま、さわって……。さわってぇ……!」
「がんばれ。清耀宮まであと少しだ」
「いやぁ……、あふぅ……」
突然、淫らな声を出し、彼女は今度、貴謳に自分の身体を擦りつけてくる。突然、柔らかい肢体の感触に包まれ、貴謳はあわてて相手の身体を自分から引きはがした。
「よせ! それもだめだ……っ」
馬車の中だというのに、己の中心が反応し始めるのを感じ、何とか冷静さを取り戻そうと目をつぶって精神統一を図る。その傍から凛明の「ぁン、はぁン、あぁンっ……」という甘い声が響き、統一は果たされる前に吹き飛んだ。
「凛明!」
目を開けると、なんと彼女は自分で自分を慰めようとしているではないか!
「くっ……」
彼女にそんなことをさせてたまるか。やるなら自分が……!
(じゃない、彼女はそんなことをするべきではない……!)
情交の末の遊戯としてであればまだしも、媚薬に犯され我を忘れた状態で自慰を覚えるなどあんまりだ。
貴謳は彼女の手をつかんで押さえつけ、抱きしめた。
「凛明、俺を見ろ――」
「きおうさま……」
舌足らずな彼女の、半開きになったくちびるに、自分のくちびるを押し当てる。
やわらかくくちびるを吸ってやると、その感触が気に入ったのか、彼女は積極的に応えてきた。様子をうかがいながら舌でくすぐると、いやがるどころか、鼻にかかったような色っぽい声を出して歓ぶ。
「――――んん……っ」
その瞬間、貴謳は我慢に我慢を重ねた欲望と情熱を迸らせた。
隙間なくくちびるを重ね合わせたまま、彼女の口腔内へ深く舌を挿し入れる。柔らかく小さな舌を捜し出して絡めたとたん、腕の中で肢体がびくっと震えた。
「んふぅ……っ」
甘えるような声を発し、彼女は続きを乞うように自ら舌を絡めてくる。しばらくくちゅくちゅと、蛇のように舌を重ね合い、頃合いを見て優しく吸ったところ、凛明はくぐもった声を上げてビクビクと身体を震わせた。
どうやら達してしまったようだ。
(これほどまでに感じやすくなっているのか……)
貴謳は感動した。キスだけで達してしまうなら、この後、身体中を愛撫したらどうなってしまうのか……。
甘やかな妄想にくれていた最中、ゴホンと遠慮がちな咳ばらいが聞こえ、御者が垂れ幕をめくって中をのぞきこんでくる。
「あのぅ、旦那様。到着しておりますが……」
「ご苦労……っ」
口づけにしておいてよかったと、貴謳は心の中で冷や汗をかいた。
「凛明。降りるぞ」
「いやぁ、もっとする……っ」
キスをねだって首筋にかじりついてくる凛明の可愛さに眩暈がする。今すぐに応えたい気持ちを、箍の外れかかった理性をかき集めて何とか押さえつけ、彼女を抱き上げると、ついでに仙寧宮から持ち出した、棒のような謎の器具もつかんで馬車を降りた。
状況から見て、凛明の体液と思われるものが付着していたのだ。置いてくるわけにはいかなかった。
貴謳は居合わせた家人への労いもそこそこに、足早に宮殿の臥室へ向かう。その途中、
「きおうさま、もうしたくないの……?」
しくしくと泣き出した凛明へ、こちらこそ泣きたい気分で答えた。
「したいとも。だから急いでいる!」
貴謳の部屋の前には、世話役の家人が二名、控えていた。すっかり蕩けた凛明の顔を見せないよう気をつけながら、貴謳は二人に声をかける。
「しばらく部屋に誰も近づけるな。食事もいらない。必要な時はこちらから声をかけるから放っておいてくれ」
充分厳めしい口調で言ったつもりだ。だが二人は目配せを交わし、訳知り顔で微笑んで去っていった。それを追及する余裕もない。
居間との間を仕切る珠簾を越え、臥室に直行した貴謳は、ひとまず凛明を臥牀の上に下ろして息をつく。
「もう脱いでもいいぞ」
そう言うと、凛明は待ちかねたように服をはぎとり始めた。
一緒に、いい加減我慢できなくなっている自分も脱ごうとして、貴謳はふと手にしていた器具の存在を思い出す。女の腕ほどの長さの細い棒だ。
近くにあった布で手早く拭き、しみじみと眺めた。
持ち手があり、その上に親指の先ほどの大きさの玉が連なるような凹凸がある。全体が朱色の漆で塗られているため、ひどく煽情的だ。
「何だこれは……?」
「きおうさま、しらないの……?」
しっとりと吐息の混ざった声に振り向けば、衝立越しに窓から差し込む光のなか、褥の上に座った凛明がまぶしいほど魅惑的な裸身をさらしていた。
絹のようになめらかな肌は上気して薄紅色に染まり、しっとりと艶めいている。ほっそりとした首や肩に反して、形の良い胸はそれなりに存在感がある。おまけに張りのあるふくらみの先端は、すでに苺のように赤く尖り、つんと上を向いていた。
「…………」
思わず見入っていると凛明が手をのばしてくる。
「こうしてつかうの……」
棒状の器具を渡したところ、彼女は臥牀の端に座り、すでにぬれて花開いた秘処に波打つ棒の側面を当ててゆっくりと引き上げた。
「あぁん……!」
淫らな凹凸が繊細な花弁を刺激したのだろう。彼女は心地よさそうな声を上げて身体を震わせ、陶酔している。
貴謳はごくりと音をたててつばを飲み込んだ。
「俺にもやらせろ」
貴謳は弓を受け取ると凛明を臥牀の上で四つん這いにさせた。
そして脚のはざまに差し入れた弓を、そぅっと割れ目に押し当て、力を入れないよう気をつけて擦り上げると、凛明の嬌声が甲高くなる。細く啼きながら、彼女は悩ましげに身震いした。
「じんじん、する……っ」
さらに二、三度弓を上下させると、クチュクチュという音が生じる。やがて凛明は細い肢体を痙攣させ、甘い声を張り上げて達した末に、くずれ落ちるようにして横向きに伏せてしまった。
絹の褥に側臥し、彼女は切なくすすり泣く。
「いやぁっ、もう……、もうおかしくなる……っ」
媚薬入りの茶を飲まされ、馬車のなかでさんざん焦らされたのだ。身体の中で欲求が煮えたぎっているのだろう。
「きおうさま、たすけて……!」
媚薬に関しては以前耳にしたことがあった。この国の薬学の歴史は古い。歴代皇帝が性欲を満たしてきた場所において、その類の研究がされていないはずがない。おそらく大変な効き目があるのだろう……と、噂を聞いた時には漠然と考えた。
その「効き目」を、まさに今、目の当たりにしている。
「よせ、凛明。服を脱ぐな……っ」
思わず制止してから、貴謳はハッとして周囲を見まわした。
馬車の窓には紗の、後ろの入口には厚手の垂れ幕がかかっているが、声が外に漏れないかひやひやしてしまう。
押さえつける貴謳の手の中で、凛明はなまめかしく身体をよじった。
「あつい……からだがあついの……っ」
「そんなにつらいのか……?」
「つらいです、きおうさま……。たすけて……」
真っ赤に上気した顔で、ハァハァと息を乱しながら、彼女は貴謳の手をつかみ、胸元の合わせの中に差し込もうとする。
「まっ、待て! それはマズい……!」
貴謳は慌てて彼女の服の中から手を引っこ抜いた。
こんな場所で胸の愛撫など始めれば、それだけで治まらなくなるのは目に見えている。何しろ彼女の胸はあまりにも柔らかく、頂を優しくつまんだだけで可愛い声を出すほど感じやすいのだ。
初夜の記憶を反芻して幸せな気分に浸っていると、凛明が子供のように声を上げてしくしくと泣きだした。
「どうした!?」
「きおうさま、さわって……。さわってぇ……!」
「がんばれ。清耀宮まであと少しだ」
「いやぁ……、あふぅ……」
突然、淫らな声を出し、彼女は今度、貴謳に自分の身体を擦りつけてくる。突然、柔らかい肢体の感触に包まれ、貴謳はあわてて相手の身体を自分から引きはがした。
「よせ! それもだめだ……っ」
馬車の中だというのに、己の中心が反応し始めるのを感じ、何とか冷静さを取り戻そうと目をつぶって精神統一を図る。その傍から凛明の「ぁン、はぁン、あぁンっ……」という甘い声が響き、統一は果たされる前に吹き飛んだ。
「凛明!」
目を開けると、なんと彼女は自分で自分を慰めようとしているではないか!
「くっ……」
彼女にそんなことをさせてたまるか。やるなら自分が……!
(じゃない、彼女はそんなことをするべきではない……!)
情交の末の遊戯としてであればまだしも、媚薬に犯され我を忘れた状態で自慰を覚えるなどあんまりだ。
貴謳は彼女の手をつかんで押さえつけ、抱きしめた。
「凛明、俺を見ろ――」
「きおうさま……」
舌足らずな彼女の、半開きになったくちびるに、自分のくちびるを押し当てる。
やわらかくくちびるを吸ってやると、その感触が気に入ったのか、彼女は積極的に応えてきた。様子をうかがいながら舌でくすぐると、いやがるどころか、鼻にかかったような色っぽい声を出して歓ぶ。
「――――んん……っ」
その瞬間、貴謳は我慢に我慢を重ねた欲望と情熱を迸らせた。
隙間なくくちびるを重ね合わせたまま、彼女の口腔内へ深く舌を挿し入れる。柔らかく小さな舌を捜し出して絡めたとたん、腕の中で肢体がびくっと震えた。
「んふぅ……っ」
甘えるような声を発し、彼女は続きを乞うように自ら舌を絡めてくる。しばらくくちゅくちゅと、蛇のように舌を重ね合い、頃合いを見て優しく吸ったところ、凛明はくぐもった声を上げてビクビクと身体を震わせた。
どうやら達してしまったようだ。
(これほどまでに感じやすくなっているのか……)
貴謳は感動した。キスだけで達してしまうなら、この後、身体中を愛撫したらどうなってしまうのか……。
甘やかな妄想にくれていた最中、ゴホンと遠慮がちな咳ばらいが聞こえ、御者が垂れ幕をめくって中をのぞきこんでくる。
「あのぅ、旦那様。到着しておりますが……」
「ご苦労……っ」
口づけにしておいてよかったと、貴謳は心の中で冷や汗をかいた。
「凛明。降りるぞ」
「いやぁ、もっとする……っ」
キスをねだって首筋にかじりついてくる凛明の可愛さに眩暈がする。今すぐに応えたい気持ちを、箍の外れかかった理性をかき集めて何とか押さえつけ、彼女を抱き上げると、ついでに仙寧宮から持ち出した、棒のような謎の器具もつかんで馬車を降りた。
状況から見て、凛明の体液と思われるものが付着していたのだ。置いてくるわけにはいかなかった。
貴謳は居合わせた家人への労いもそこそこに、足早に宮殿の臥室へ向かう。その途中、
「きおうさま、もうしたくないの……?」
しくしくと泣き出した凛明へ、こちらこそ泣きたい気分で答えた。
「したいとも。だから急いでいる!」
貴謳の部屋の前には、世話役の家人が二名、控えていた。すっかり蕩けた凛明の顔を見せないよう気をつけながら、貴謳は二人に声をかける。
「しばらく部屋に誰も近づけるな。食事もいらない。必要な時はこちらから声をかけるから放っておいてくれ」
充分厳めしい口調で言ったつもりだ。だが二人は目配せを交わし、訳知り顔で微笑んで去っていった。それを追及する余裕もない。
居間との間を仕切る珠簾を越え、臥室に直行した貴謳は、ひとまず凛明を臥牀の上に下ろして息をつく。
「もう脱いでもいいぞ」
そう言うと、凛明は待ちかねたように服をはぎとり始めた。
一緒に、いい加減我慢できなくなっている自分も脱ごうとして、貴謳はふと手にしていた器具の存在を思い出す。女の腕ほどの長さの細い棒だ。
近くにあった布で手早く拭き、しみじみと眺めた。
持ち手があり、その上に親指の先ほどの大きさの玉が連なるような凹凸がある。全体が朱色の漆で塗られているため、ひどく煽情的だ。
「何だこれは……?」
「きおうさま、しらないの……?」
しっとりと吐息の混ざった声に振り向けば、衝立越しに窓から差し込む光のなか、褥の上に座った凛明がまぶしいほど魅惑的な裸身をさらしていた。
絹のようになめらかな肌は上気して薄紅色に染まり、しっとりと艶めいている。ほっそりとした首や肩に反して、形の良い胸はそれなりに存在感がある。おまけに張りのあるふくらみの先端は、すでに苺のように赤く尖り、つんと上を向いていた。
「…………」
思わず見入っていると凛明が手をのばしてくる。
「こうしてつかうの……」
棒状の器具を渡したところ、彼女は臥牀の端に座り、すでにぬれて花開いた秘処に波打つ棒の側面を当ててゆっくりと引き上げた。
「あぁん……!」
淫らな凹凸が繊細な花弁を刺激したのだろう。彼女は心地よさそうな声を上げて身体を震わせ、陶酔している。
貴謳はごくりと音をたててつばを飲み込んだ。
「俺にもやらせろ」
貴謳は弓を受け取ると凛明を臥牀の上で四つん這いにさせた。
そして脚のはざまに差し入れた弓を、そぅっと割れ目に押し当て、力を入れないよう気をつけて擦り上げると、凛明の嬌声が甲高くなる。細く啼きながら、彼女は悩ましげに身震いした。
「じんじん、する……っ」
さらに二、三度弓を上下させると、クチュクチュという音が生じる。やがて凛明は細い肢体を痙攣させ、甘い声を張り上げて達した末に、くずれ落ちるようにして横向きに伏せてしまった。
絹の褥に側臥し、彼女は切なくすすり泣く。
「いやぁっ、もう……、もうおかしくなる……っ」
媚薬入りの茶を飲まされ、馬車のなかでさんざん焦らされたのだ。身体の中で欲求が煮えたぎっているのだろう。
「きおうさま、たすけて……!」