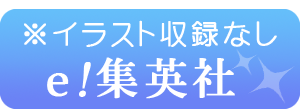悪役令嬢はハイスペ隠しキャラの蜜愛に惑う 3
依田ザクロ イラスト/塩瀬 透
「どうぞ、お召し上がりください」
ピックで刺して差し出す。
手渡しするつもりだったのだが、彼は顔を近づけてきて口を開けた。
(ええっ、まさかこれは噂の……『あーん』なの!?)
美麗すぎて破壊力の強いおねだり顔に迫られて、激しく動揺する。
「どうしました? くださるのではないのですか?」
彼は薄目を開けて挑発してくる。
プロポーズを受けた身で今さらかもしれないが、やはり恥ずかしいものは恥ずかしい。直視できず、視線を微妙に逸らした状態で、色めいた唇へ葡萄を突っ込んだ。
「んぐ……、もう少し優しく」
「ご、ごめんなさい」
「上手な食べさせ方のお手本を見せましょうか?」
「っ、遠慮します」
ダンスパーティーへ向かう馬車の中、キャンディを舌で淫らに差し入れられたのを忘れてはいない。
「つれないですね。……ん、おいしい!」
咀嚼した彼は開いた唇へ指を当てた。
「初めて食べる食感です。もちもちとみずみずしさが嚙み合って、不思議で甘くて面白い味がします」
「気に入ってもらえましたか?」
「もちろん」
「ではもっとどうぞ」
新しい菓子にチャレンジしてみてよかった。
交互に一粒ずつ摘まみ、ほほえみを交わしながら味わった。
最後の一粒はシトラスに譲る。
「食べさせて」
(……やっぱりこうなるわよね)
終わりくらいは、と観念してピックを彼の口もとへ差し出す。すると、違うとばかり手を摑まれ、ハニーフローラの顔の前へ押し戻された。
「そうではなくて、かわいい唇に咥えて食べさせて」
「っ!?」
「ほら……」
唇にぷちゅんと葡萄餅が押しつけられる。
「んむっ」
(これを咥えて、キスするって意味……?)
動揺のあまり歯を立ててしまった。口中で葡萄が弾けて果汁があふれだす。
(間違えて食べちゃった!)
まさか吐き出すわけにはいかず、もぐもぐと咀嚼する。
「こーら、俺にくださるはずだったでしょう。仕方ないから分けてもらいますよ」
彼の唇が迫ってきた。
(あ……もう、ほとんどないのに)
果実にかぶりつくような口づけが襲ってくる。肉厚の舌がひらめきながら口腔を侵してきた。ほのかに残る葡萄の汁は舐め尽くされる。
「んぅ……、ふ、ぁ……」
戯れのキスは、やがて愉悦を交換する深いものへと変わっていく。
「……このまま全部を奪ってもいいですか?」
口づけの合間に甘い懇願がこぼれた。
息が上がって答えられずにいると、彼がかすれ声でカウントダウンを始める。
「だめなら五秒以内に逃げてください。五、四……」
言いながら、角度を変えて唇を塞いでくる。吐息まで吸い尽くすキスをされて、声なんて出せるわけがなかった。
「三、二、一……はい、時間切れです」
優しく肩を押されてソファーへ仰向けにされる。
せわしない手つきでドレスの前身頃が開かれた。上向きになってもなお綺麗な輪郭を保つ双丘が露わになる。
「あ……や……」
「あなたの嫌は、本当は嫌ではないのですよね?」
悪魔のような笑顔を向けられる。なにを言ってももう彼の情熱は止まらないのだった。
骨ばった手がふくらみを包む。あたたかさに肌がじんと痺れた。
「あ……は、あぁ……」
右手は弱く、左手は強く、力加減を変えて左右のふくらみを不規則に捏ねてくる。ちぐはぐな刺激が卑猥さを助長して、芯が甘く勃ちあがった。
「もう硬くなってしまった?」
同時に二つの先端をきゅっと摘ままれる。
「ふぁぁぁ……っ!」
腰が浮きあがる快感に、頭をいやいやと振った。
「だめ、く、あ……、ん、ぁぁ……」
歯を食いしばって我慢しようとしても、聞くに堪えない嬌声が漏れてしまう。
「声、我慢しないで。滝の音で全部聞こえないから」
「あぁっあ……、こりこりしちゃだめぇ……!」
指のはらですりつぶすように乳首をいたぶられ、びくびくと下肢を震わせた。自然と背筋が反り、胸を突き出す格好になる。
「おいしそうなデザートですね」
指でくびり出された快感の源を、ぱくりと咥えられた。
「んくぁぁぁ……っ」
湧きたつ愉悦で頭の中が白くなる。口中で舌をひらめかせて、ちゅぷちゅぷといやらしく転がされると、下腹部がびりびりと痺れた。舌戯を続けながら、右手では乳房を捏ね、乳首を指のあいだに挟んで押し回してくる。
「は……、ぁっあっあぁ……、やぁ、ぃや……、だめ……っ」
痛いくらいの刺激が肌を灼く。
ソファーカバーにしがみついて強い快感に耐えた。
「恥ずかしがらなくていい。余計な力を抜いて、気持ちがいいことだけを考えて」
(そんなの……)
理性では無理だと思うのに、身体は素直に開いていく。
スカートがめくり上げられ、彼の手が膝から大腿を這った。脚のつけ根までのぼったところで、ぴたりと止まる。
「待ってください、なんですか、これ?」
上半身を愛撫していた顔をがばりと上げて、勢いよくハニーフローラの両膝を割って押し広げる。
「きゃぁぁっ」
ひっくり返った亀のごとく両手をばたつかせるが、脚を抱え込まれていて抵抗が意味をなさない。
「なんて格好をしているんですか」
卑猥な姿勢をさせているのは彼なのに、責められても。
「は、離してください……っ」
「離せない。こんなの、見てしまうに決まっている」
彼の熱い視線は秘部へ注がれている。そこで真実に気づいた。
(そうだわ、ショーツを穿いていたのだった)
フィット感の快適さに存在をすっかり忘れていた。
「あの……これは新しい下着で……、恥ずかしいから、見ないでください」
両手を股間へ当てて隠すが、すぐにやんわりと払いのけられる。
「見ないでなんて、無理だ」
指先でクロッチをつっと撫で上げてくる。
「んあ……っ」
すでに潤っていたせいか、絹のなめらかな生地が割れ目にくっついた。
「中、濡れていますね」
「やあ……っ、さわっちゃだめ……」
「布地が透けて、形がわかる」
蜜をもっと染み込ませ、指を動かすと、ぬちぬちという淫靡な音が立った。
「ぁ、は……、あぁ」
絹を押し込むふうに指先を秘裂へ押し当ててくる。指とは違うつるつるした感触に襲われて、花びらがわなないた。
「すごくいやらしい」
「やだぁ……っ」
「こんなの、俺を悦ばせるためとしか思えない」
彼の瞳は陶然としていた。どうやっても消せない情欲の火をつけてしまったのだった。
(ただ穿きやすい下着を穿いてきただけなのに……っ)
盛りあがる媚肉を撫でながら、あふれる蜜を内側へ塗り広げていく。
粘膜への間接的な刺激は、もどかしさをつのらせた。指の先端が蜜孔の縁を伝って割れ目につぷりと布ごと沈む。指と絹とで蜜が執拗に捏ねられて粘度を増し、クロッチと媚肌をべっとりと密着させた。
いよいよ花全体の形が露骨に浮き出て、彼の目を愉しませる。
「すごい。布の上からでも勃ってきたのがわかる」
淫芽が莢から顔を出しているのまで丸わかりだった。
「や……ぁっ、あ……」
そこは、次に来るであろう刺激を期待して、存在を主張するように震えた。彼の指は的確に突起を押しつぶしてきた。
「ひぁぁぁ……っ!」
まなうらで閃光がまたたいた。
彼は指先を鉤状に曲げ、何度も甘くひっかいてくる。
「あっ……あ、だめ、ぃや、それ、だめ……っ、くりくりしちゃ……いやぁ……っ」
大腿をうち震わせて悦に入った嬌声を上げる。つま先がぴんと伸び、下腹部に力がこもった。
雌しべの断続的な愛撫は、果てしない陶酔をもたらした。
羞恥ゆえの抵抗は薄れ、自然と腰を上下に揺らめかせる。その振動さえも快楽を助長して、愉悦が濃くなった。
いよいよ懊悩に耐え切れなくなり、腰をぐうっと押し上げる。反動で淫核がきつく扱きあげられた。
「んはぁぁぁ……っ!」
ピックで刺して差し出す。
手渡しするつもりだったのだが、彼は顔を近づけてきて口を開けた。
(ええっ、まさかこれは噂の……『あーん』なの!?)
美麗すぎて破壊力の強いおねだり顔に迫られて、激しく動揺する。
「どうしました? くださるのではないのですか?」
彼は薄目を開けて挑発してくる。
プロポーズを受けた身で今さらかもしれないが、やはり恥ずかしいものは恥ずかしい。直視できず、視線を微妙に逸らした状態で、色めいた唇へ葡萄を突っ込んだ。
「んぐ……、もう少し優しく」
「ご、ごめんなさい」
「上手な食べさせ方のお手本を見せましょうか?」
「っ、遠慮します」
ダンスパーティーへ向かう馬車の中、キャンディを舌で淫らに差し入れられたのを忘れてはいない。
「つれないですね。……ん、おいしい!」
咀嚼した彼は開いた唇へ指を当てた。
「初めて食べる食感です。もちもちとみずみずしさが嚙み合って、不思議で甘くて面白い味がします」
「気に入ってもらえましたか?」
「もちろん」
「ではもっとどうぞ」
新しい菓子にチャレンジしてみてよかった。
交互に一粒ずつ摘まみ、ほほえみを交わしながら味わった。
最後の一粒はシトラスに譲る。
「食べさせて」
(……やっぱりこうなるわよね)
終わりくらいは、と観念してピックを彼の口もとへ差し出す。すると、違うとばかり手を摑まれ、ハニーフローラの顔の前へ押し戻された。
「そうではなくて、かわいい唇に咥えて食べさせて」
「っ!?」
「ほら……」
唇にぷちゅんと葡萄餅が押しつけられる。
「んむっ」
(これを咥えて、キスするって意味……?)
動揺のあまり歯を立ててしまった。口中で葡萄が弾けて果汁があふれだす。
(間違えて食べちゃった!)
まさか吐き出すわけにはいかず、もぐもぐと咀嚼する。
「こーら、俺にくださるはずだったでしょう。仕方ないから分けてもらいますよ」
彼の唇が迫ってきた。
(あ……もう、ほとんどないのに)
果実にかぶりつくような口づけが襲ってくる。肉厚の舌がひらめきながら口腔を侵してきた。ほのかに残る葡萄の汁は舐め尽くされる。
「んぅ……、ふ、ぁ……」
戯れのキスは、やがて愉悦を交換する深いものへと変わっていく。
「……このまま全部を奪ってもいいですか?」
口づけの合間に甘い懇願がこぼれた。
息が上がって答えられずにいると、彼がかすれ声でカウントダウンを始める。
「だめなら五秒以内に逃げてください。五、四……」
言いながら、角度を変えて唇を塞いでくる。吐息まで吸い尽くすキスをされて、声なんて出せるわけがなかった。
「三、二、一……はい、時間切れです」
優しく肩を押されてソファーへ仰向けにされる。
せわしない手つきでドレスの前身頃が開かれた。上向きになってもなお綺麗な輪郭を保つ双丘が露わになる。
「あ……や……」
「あなたの嫌は、本当は嫌ではないのですよね?」
悪魔のような笑顔を向けられる。なにを言ってももう彼の情熱は止まらないのだった。
骨ばった手がふくらみを包む。あたたかさに肌がじんと痺れた。
「あ……は、あぁ……」
右手は弱く、左手は強く、力加減を変えて左右のふくらみを不規則に捏ねてくる。ちぐはぐな刺激が卑猥さを助長して、芯が甘く勃ちあがった。
「もう硬くなってしまった?」
同時に二つの先端をきゅっと摘ままれる。
「ふぁぁぁ……っ!」
腰が浮きあがる快感に、頭をいやいやと振った。
「だめ、く、あ……、ん、ぁぁ……」
歯を食いしばって我慢しようとしても、聞くに堪えない嬌声が漏れてしまう。
「声、我慢しないで。滝の音で全部聞こえないから」
「あぁっあ……、こりこりしちゃだめぇ……!」
指のはらですりつぶすように乳首をいたぶられ、びくびくと下肢を震わせた。自然と背筋が反り、胸を突き出す格好になる。
「おいしそうなデザートですね」
指でくびり出された快感の源を、ぱくりと咥えられた。
「んくぁぁぁ……っ」
湧きたつ愉悦で頭の中が白くなる。口中で舌をひらめかせて、ちゅぷちゅぷといやらしく転がされると、下腹部がびりびりと痺れた。舌戯を続けながら、右手では乳房を捏ね、乳首を指のあいだに挟んで押し回してくる。
「は……、ぁっあっあぁ……、やぁ、ぃや……、だめ……っ」
痛いくらいの刺激が肌を灼く。
ソファーカバーにしがみついて強い快感に耐えた。
「恥ずかしがらなくていい。余計な力を抜いて、気持ちがいいことだけを考えて」
(そんなの……)
理性では無理だと思うのに、身体は素直に開いていく。
スカートがめくり上げられ、彼の手が膝から大腿を這った。脚のつけ根までのぼったところで、ぴたりと止まる。
「待ってください、なんですか、これ?」
上半身を愛撫していた顔をがばりと上げて、勢いよくハニーフローラの両膝を割って押し広げる。
「きゃぁぁっ」
ひっくり返った亀のごとく両手をばたつかせるが、脚を抱え込まれていて抵抗が意味をなさない。
「なんて格好をしているんですか」
卑猥な姿勢をさせているのは彼なのに、責められても。
「は、離してください……っ」
「離せない。こんなの、見てしまうに決まっている」
彼の熱い視線は秘部へ注がれている。そこで真実に気づいた。
(そうだわ、ショーツを穿いていたのだった)
フィット感の快適さに存在をすっかり忘れていた。
「あの……これは新しい下着で……、恥ずかしいから、見ないでください」
両手を股間へ当てて隠すが、すぐにやんわりと払いのけられる。
「見ないでなんて、無理だ」
指先でクロッチをつっと撫で上げてくる。
「んあ……っ」
すでに潤っていたせいか、絹のなめらかな生地が割れ目にくっついた。
「中、濡れていますね」
「やあ……っ、さわっちゃだめ……」
「布地が透けて、形がわかる」
蜜をもっと染み込ませ、指を動かすと、ぬちぬちという淫靡な音が立った。
「ぁ、は……、あぁ」
絹を押し込むふうに指先を秘裂へ押し当ててくる。指とは違うつるつるした感触に襲われて、花びらがわなないた。
「すごくいやらしい」
「やだぁ……っ」
「こんなの、俺を悦ばせるためとしか思えない」
彼の瞳は陶然としていた。どうやっても消せない情欲の火をつけてしまったのだった。
(ただ穿きやすい下着を穿いてきただけなのに……っ)
盛りあがる媚肉を撫でながら、あふれる蜜を内側へ塗り広げていく。
粘膜への間接的な刺激は、もどかしさをつのらせた。指の先端が蜜孔の縁を伝って割れ目につぷりと布ごと沈む。指と絹とで蜜が執拗に捏ねられて粘度を増し、クロッチと媚肌をべっとりと密着させた。
いよいよ花全体の形が露骨に浮き出て、彼の目を愉しませる。
「すごい。布の上からでも勃ってきたのがわかる」
淫芽が莢から顔を出しているのまで丸わかりだった。
「や……ぁっ、あ……」
そこは、次に来るであろう刺激を期待して、存在を主張するように震えた。彼の指は的確に突起を押しつぶしてきた。
「ひぁぁぁ……っ!」
まなうらで閃光がまたたいた。
彼は指先を鉤状に曲げ、何度も甘くひっかいてくる。
「あっ……あ、だめ、ぃや、それ、だめ……っ、くりくりしちゃ……いやぁ……っ」
大腿をうち震わせて悦に入った嬌声を上げる。つま先がぴんと伸び、下腹部に力がこもった。
雌しべの断続的な愛撫は、果てしない陶酔をもたらした。
羞恥ゆえの抵抗は薄れ、自然と腰を上下に揺らめかせる。その振動さえも快楽を助長して、愉悦が濃くなった。
いよいよ懊悩に耐え切れなくなり、腰をぐうっと押し上げる。反動で淫核がきつく扱きあげられた。
「んはぁぁぁ……っ!」