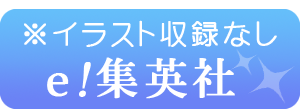月下に滴 る花雫
葉月エリカ イラスト/綺羅かぼす
「お前が俺に懇願するんだ。『どうか私を抱いて、あなたの妻にしてください』ってな」
「そんな……」
「自分の立場をよく考えろ」
そんなふうに言われてしまっては、もう逃げ道はなかった。
奥歯をぐっと噛み締め、藍蓮は震える唇を開く。
「どうか……」
(――物語よ。これは物語の台詞なの)
あるいはお芝居であってもいい。ここにいるのは藍蓮であって、藍蓮でない娘だ。
「私を……抱いて……」
藍蓮自身ではないのだから、この男に何をされようが、他人の身に起こったこととしてやりすごせるはず。怖くてつらい物語にも、いつかは終わりが来るはずだから。
「――あなたの妻に、してください」
「さすがは公主様だな。立派なもんだ」
彼の命じた通りにしたのに、瑛翔は面白くもなさそうに言って、藍蓮の夜着に手をかけた。胸元をいきなり大きく開かれ、搗きたての餅のような乳房がふるんっとまろび出る。
「やっ……!」
そんな場所を男性に見られたことなど初めてだ。
覚悟を決めたはずなのに、火をつけられたような羞恥はどうしようもなくて、藍蓮の頭にかあっと血がのぼる。
「は……ここも立派じゃないか」
瑛翔が口の端を歪め、笑った。決して上品な笑みではないのに、藍蓮はその表情からどうしてか目が離せなかった。
「何もかも俺のものにしてやる。この白い肌も、小さな蕾も――俺だけに触れられて、淫らに色を変えるように」
「っ……や、やだっ!」
唐突に瑛翔の両手が藍蓮の乳房を鷲掴み、根本から大きく揉み立てた。華奢な体つきに反し、そこだけ豊かな胸の実りが波立つように揺れてしまい、恥ずかしくてたまらない。
「嫌? ほんとにか?」
瑛翔が藍蓮の耳朶に、唇をかすめるようにして囁いた。
「誰にもこんなことをされたことはないんだろう? 好きになるか嫌いになるか、まだわからないんじゃないのか?」
「んっ……あ、あっ……」
きゅうっと両胸の頂を摘まれて、断続的な声が洩れる。
普段から剣を握っているせいなのか、瑛翔の指先は皮が厚くなってざらりとしていた。そんな指で敏感な突起を捉われ、くりくりと捩(よじ)るように弄られると、胸の奥からおかしなざわめきが込み上げる。
「やぁっ……触るの、やめて……やめて……」
「お前のここはそう言ってない。ほら、もうこんなに尖って……いやらしく勃ってきた」
いやらしいと言われて、藍蓮の頬に朱が集う。
確かにそこは、経験したこともないようなじくじくした疼きを帯びて、ぷっくりと上を向いていた。 本来は淡い桃色であるはずなのに、芽吹きを待つ紅梅のような赤に色づいているのが、ひどく浅ましい光景だ。
「はぁ……あ、あぁ……んっ……」
ぴんと引っ張っては押し込めて。螺子(ねじ)でも扱っているかのように、左右に軽く回して。
瑛翔の指先はひどく不埒に、藍蓮の乳首をいたぶり続ける。
そのたびに藍蓮の肩はびくびくと揺れ、臥牀に押しつけられた背中に汗が滲んだ。露にされた乳房は鳥肌立っているのに、薄い皮膚の下で未知の熱が渦を巻く。
「どんな感じだ? 藍蓮」
妃はいないはずなのに、こういったことに慣れているのか、瑛翔は藍蓮の反応をじっくりと眺めながら問いかけた。
息が弾み、鼓動が異常なほど昂る中、藍蓮は唇を噛み締める。
瑛翔に抱かれてしまうことは仕方がなくても、憎い男の手で心地よくさせられるだなんて、絶対に認めるわけにはいかないから。
「っ……気持ち、悪い……こんなの、ちっとも好きじゃない……!」
「へぇ……こうしてもか?」
意地を張る藍蓮に、瑛翔は首をすくめ、片方の乳首に吸いついた。
それだけでぞくっとした痺れが駆け抜け、濡れた舌で淫らな尖りを舐め転がされるにいたっては、声を殺しきることができなかった。
「ひっ……あぁあ……やぁんっ……!」
「いい声で啼けるじゃないか、藍蓮?」
片眉を跳ね上げた瑛翔が、藍蓮の胸の上で笑う。
「もっと聴かせろ――俺だけしか知らない、いやらしいお前を見たい」
「い……あぁ、はっ……ああぁ……っ」
普段の倍ほどにも大きくなった乳首は、吐息を浴びせられるだけでもひくついてしまう。
そんな場所を瑛翔ははくっと甘噛みし、乳を求める赤子のように吸い立てた。母親の体でもない藍蓮なのに、そんなふうにちゅうちゅうと啜られると、胸の先からとろりとした何かが噴き零れそうな気にさせられる。
「んんっ、だめ……もう、そんな、しないでぇ……」
「俺の舌を押し返してくるくらい、ここを硬くさせてるのに?」
悠々と言う瑛翔は、やはり武将なのだ。藍蓮という存在をすみずみから征服していくことに、本能的な喜びを感じているとしか思えない。
「どうせなら愉しめ。俺がお前を好くしてやる。男女の交合(まぐわい)の悦びってやつを、どれだけでも教えてやるよ」
「そんなの、結構です……っ」
「いちいち口の減らない女だな、お前は」
藍蓮は本気で拒絶しているのに、瑛翔はくっくっと喉を鳴らした。
そうしながら藍蓮の帯を片手で器用に解いてしまい、裾を掻き分けられた夜着から、下半身があえなく晒される。
「いやぁっ……!」
藍蓮は両脚をばたつかせて暴れたが、瑛翔に馬乗りになられてしまっては、なんの抵抗にもならなかった。
彼の長衣の裾もはだけて、筋肉の張りつめた両腿が、藍蓮の細い腰をがっちりと挟み込んでいる。血の気の多い男なのか、その肌は驚くほどに熱い。
「痛い目に遭いたくないなら、俺のすることを素直に受け入れろ。虎に食われる兎みたいに、がつがつ貪られたいなら別だがな」
不穏な喩えに藍蓮は息を呑んだ。
男を初めて迎え入れる破瓜の際、大抵の女性は相当な苦痛を味わうという。
本来なら、輿入れの予定もない高貴な娘がそんなことを教えられるはずもないのだが、そこは読書家の藍蓮だ。過激さが売りの艶情小説とまではいかずとも、描写の濃い恋愛小説を読んでいたせいで、男女のことについては漠然と知っている。
この漠然と――というのが曲者だった。いっそ微に入り細に入り知識を備えていれば肚が据わるのかもしれないが、中途半端な理解しかないせいで、余計に恐怖に拍車がかかる。
「い……痛いのは、嫌です……」
「そうだ。そうやってしおらしくしてれば、たっぷり可愛がってやる」
おずおずと訴えると、瑛翔は藍蓮の前髪を掻きあげ、額の際に唇を落とした。
予想外に優しい感触に驚き、まじまじと瑛翔を見つめれば、彼はふっと淡い笑みを浮かべ、再び接吻を仕掛けてきた。
「そんな……」
「自分の立場をよく考えろ」
そんなふうに言われてしまっては、もう逃げ道はなかった。
奥歯をぐっと噛み締め、藍蓮は震える唇を開く。
「どうか……」
(――物語よ。これは物語の台詞なの)
あるいはお芝居であってもいい。ここにいるのは藍蓮であって、藍蓮でない娘だ。
「私を……抱いて……」
藍蓮自身ではないのだから、この男に何をされようが、他人の身に起こったこととしてやりすごせるはず。怖くてつらい物語にも、いつかは終わりが来るはずだから。
「――あなたの妻に、してください」
「さすがは公主様だな。立派なもんだ」
彼の命じた通りにしたのに、瑛翔は面白くもなさそうに言って、藍蓮の夜着に手をかけた。胸元をいきなり大きく開かれ、搗きたての餅のような乳房がふるんっとまろび出る。
「やっ……!」
そんな場所を男性に見られたことなど初めてだ。
覚悟を決めたはずなのに、火をつけられたような羞恥はどうしようもなくて、藍蓮の頭にかあっと血がのぼる。
「は……ここも立派じゃないか」
瑛翔が口の端を歪め、笑った。決して上品な笑みではないのに、藍蓮はその表情からどうしてか目が離せなかった。
「何もかも俺のものにしてやる。この白い肌も、小さな蕾も――俺だけに触れられて、淫らに色を変えるように」
「っ……や、やだっ!」
唐突に瑛翔の両手が藍蓮の乳房を鷲掴み、根本から大きく揉み立てた。華奢な体つきに反し、そこだけ豊かな胸の実りが波立つように揺れてしまい、恥ずかしくてたまらない。
「嫌? ほんとにか?」
瑛翔が藍蓮の耳朶に、唇をかすめるようにして囁いた。
「誰にもこんなことをされたことはないんだろう? 好きになるか嫌いになるか、まだわからないんじゃないのか?」
「んっ……あ、あっ……」
きゅうっと両胸の頂を摘まれて、断続的な声が洩れる。
普段から剣を握っているせいなのか、瑛翔の指先は皮が厚くなってざらりとしていた。そんな指で敏感な突起を捉われ、くりくりと捩(よじ)るように弄られると、胸の奥からおかしなざわめきが込み上げる。
「やぁっ……触るの、やめて……やめて……」
「お前のここはそう言ってない。ほら、もうこんなに尖って……いやらしく勃ってきた」
いやらしいと言われて、藍蓮の頬に朱が集う。
確かにそこは、経験したこともないようなじくじくした疼きを帯びて、ぷっくりと上を向いていた。 本来は淡い桃色であるはずなのに、芽吹きを待つ紅梅のような赤に色づいているのが、ひどく浅ましい光景だ。
「はぁ……あ、あぁ……んっ……」
ぴんと引っ張っては押し込めて。螺子(ねじ)でも扱っているかのように、左右に軽く回して。
瑛翔の指先はひどく不埒に、藍蓮の乳首をいたぶり続ける。
そのたびに藍蓮の肩はびくびくと揺れ、臥牀に押しつけられた背中に汗が滲んだ。露にされた乳房は鳥肌立っているのに、薄い皮膚の下で未知の熱が渦を巻く。
「どんな感じだ? 藍蓮」
妃はいないはずなのに、こういったことに慣れているのか、瑛翔は藍蓮の反応をじっくりと眺めながら問いかけた。
息が弾み、鼓動が異常なほど昂る中、藍蓮は唇を噛み締める。
瑛翔に抱かれてしまうことは仕方がなくても、憎い男の手で心地よくさせられるだなんて、絶対に認めるわけにはいかないから。
「っ……気持ち、悪い……こんなの、ちっとも好きじゃない……!」
「へぇ……こうしてもか?」
意地を張る藍蓮に、瑛翔は首をすくめ、片方の乳首に吸いついた。
それだけでぞくっとした痺れが駆け抜け、濡れた舌で淫らな尖りを舐め転がされるにいたっては、声を殺しきることができなかった。
「ひっ……あぁあ……やぁんっ……!」
「いい声で啼けるじゃないか、藍蓮?」
片眉を跳ね上げた瑛翔が、藍蓮の胸の上で笑う。
「もっと聴かせろ――俺だけしか知らない、いやらしいお前を見たい」
「い……あぁ、はっ……ああぁ……っ」
普段の倍ほどにも大きくなった乳首は、吐息を浴びせられるだけでもひくついてしまう。
そんな場所を瑛翔ははくっと甘噛みし、乳を求める赤子のように吸い立てた。母親の体でもない藍蓮なのに、そんなふうにちゅうちゅうと啜られると、胸の先からとろりとした何かが噴き零れそうな気にさせられる。
「んんっ、だめ……もう、そんな、しないでぇ……」
「俺の舌を押し返してくるくらい、ここを硬くさせてるのに?」
悠々と言う瑛翔は、やはり武将なのだ。藍蓮という存在をすみずみから征服していくことに、本能的な喜びを感じているとしか思えない。
「どうせなら愉しめ。俺がお前を好くしてやる。男女の交合(まぐわい)の悦びってやつを、どれだけでも教えてやるよ」
「そんなの、結構です……っ」
「いちいち口の減らない女だな、お前は」
藍蓮は本気で拒絶しているのに、瑛翔はくっくっと喉を鳴らした。
そうしながら藍蓮の帯を片手で器用に解いてしまい、裾を掻き分けられた夜着から、下半身があえなく晒される。
「いやぁっ……!」
藍蓮は両脚をばたつかせて暴れたが、瑛翔に馬乗りになられてしまっては、なんの抵抗にもならなかった。
彼の長衣の裾もはだけて、筋肉の張りつめた両腿が、藍蓮の細い腰をがっちりと挟み込んでいる。血の気の多い男なのか、その肌は驚くほどに熱い。
「痛い目に遭いたくないなら、俺のすることを素直に受け入れろ。虎に食われる兎みたいに、がつがつ貪られたいなら別だがな」
不穏な喩えに藍蓮は息を呑んだ。
男を初めて迎え入れる破瓜の際、大抵の女性は相当な苦痛を味わうという。
本来なら、輿入れの予定もない高貴な娘がそんなことを教えられるはずもないのだが、そこは読書家の藍蓮だ。過激さが売りの艶情小説とまではいかずとも、描写の濃い恋愛小説を読んでいたせいで、男女のことについては漠然と知っている。
この漠然と――というのが曲者だった。いっそ微に入り細に入り知識を備えていれば肚が据わるのかもしれないが、中途半端な理解しかないせいで、余計に恐怖に拍車がかかる。
「い……痛いのは、嫌です……」
「そうだ。そうやってしおらしくしてれば、たっぷり可愛がってやる」
おずおずと訴えると、瑛翔は藍蓮の前髪を掻きあげ、額の際に唇を落とした。
予想外に優しい感触に驚き、まじまじと瑛翔を見つめれば、彼はふっと淡い笑みを浮かべ、再び接吻を仕掛けてきた。