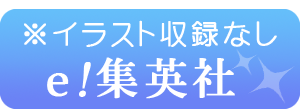エロティック ロイヤルジュエリー
溺愛系公爵の淫らな求婚計画
京極れな イラスト/駒田ハチ
「……で、首飾りの効果のほどは?」
この話題はおしまいとばかりに、レンがロッティの首元の首飾りに手を伸ばしてきた。
「あ」
彼の指先が素肌にふれて、ロッティはどきりとした。
「月が満ちるにつれて、性欲も増すというのは本当だった?」
鎖骨のあたりを思わせぶりになぞられ、身体が一気に熱く火照ってきた。
「やめて……」
ロッティは拒んだが、なぜか消え入るような、はかない声しか出なかった。素肌が妙に敏感になっていて、彼の指先の動きに意識を奪われるのだ。
「まさか、もう淫らな気持ちになったの? 僕が隣にいるだけなのに?」
「し、知らないわ」
否定はできなかった。たしかに妙な気分なのだ。距離を縮められたあたりからおかしくなっていた。
「キスしてみようよ、本当に首飾りに催淫の力があるのかどうか知りたい」
レンが囁きながら肩を抱いてくる。
「いや」
「僕を見て、ロッティ」
さらに美貌をよせてせがんでくる。いまにもキスしそうな距離で。
「いやよ。……やめて、レン。どきどきするからこっち見ないで」
ロッティは真っ赤になりながら、顔をそむける。こんなに胸が高鳴るのは絶対に首飾りのせいなのだ。
「かわいすぎてひくんだけど」
ふっと彼が笑った。
「……も、もう、帰りたいわ」
距離が近すぎるのだ。このままでは心臓が高鳴りすぎておかしくなってしまいそうだ。
「紅茶を一杯飲み終えるまでの約束だ。もちろん飲ませないけどね」
「え……」
「キスするから」
目をみはった瞬間だった。顎をすくわれ、レンに唇を塞がれた。
「………っ」
わかりきっていた。逃げたって強引に奪うと。目が獲物を見定めた狩人みたいに艶やかで、たぶんそれに魅せられていた。
「ん……」
互いの唇が密にかさなりあう。その慣れない感触におののきながらも、なぜか、身体の芯はじんと熱くなった。
レンはくりかえし唇をかさね合わせてくる。ロッティを逃さないように捕らえたまま、なにかを伝えるみたいに。
なにを……?
言葉にはできない、快いなにかだ。この男には、裏があるかもしれないというのに。
やがて考えるのさえも忘れ、ロッティは甘い口づけに酔いしれる。
「今どんな感じ?」
レンがいったん唇をはなし、うっとりと視線を絡めてきた。
ロッティは気恥ずかしくて目を逸らした。
「変な気持ちよ。もうしないで……」
つれなく返したつもりが、なぜか甘く掠れた声が出た。
本当にやめてほしかった。ただでさえ首飾りのせいで感情が高ぶりやすいのだから。
「いやだ。きみが欲しいから」
言うなりまたキスされ、続けざまに舌まで入れられた。
「ふ……」
ぬっと押し入ってきたものに、ロッティは一瞬、目をむいた。はじめ、なにかわからなかった。彼の舌だと理解したとたん、じんと身体の芯が熱くなった。
「んぅ……」
レンは退こうとしないから、受け入れるしかない。淫らな動きで口内を蹂躙され、未知の感覚を次々に呼び覚まされる。
ずっと昔から知っている相手と、こんな淫らな口づけをかわしているのが信じられなかった。
でも、決して不快ではなかった。むしろ、快くて夢中にさせられた。
(首飾りのせい……?)
わからない。あまりにも自然に導かれるから――。
「興奮するね」
口づけの合間に、甘い声でつぶやかれる。
「……レンがそうさせているのでしょ」
首飾りのせいか、理性や貞操観念が確実に薄らいでいる。いつもの自分ならとっくに拒んで押し返しているのに、今日はできない。彼にされるがままなのだ。
逆らわないのをいいことに、今度は胸元に手を這わせてきた。
「や……」
ロッティは思わずその手を押さえて咎めた。
「なにするの?」
「キスの続きだけど?」
続きがあるらしい。
「やめて。今はお茶の時間よ」
「ロッティは僕が嫌いなの?」
ふと彼が真顔になった。
「き……嫌いってわけじゃないわ。でもこんなことをするほど好きでもなかったわ」
実に正直な答えだった。自分でも深く納得してしまうほどに。
するとレンがくすっと笑った。
「でも頬は真っ赤だよ? 今のキスの反応といい、僕に気があるとしか思えないんだけどな?」
「く、首飾りのせいにすぎないのよ」
ロッティはますます赤くなりながら返す。
「べつにそれでかまわないよ。きみにどれだけ嫌われようが、僕の気持ちは変わらない。きみを妻にして、愛したいだけ愛するつもりだ」
「……そんなにわたしと結婚したい理由はなんなの?」
毎度、疑問はここに行きつく。
「知りたい? どうして僕が急にきみを口説きだしたのか」
レンのほうも、今の態度に疑問を抱かれるのは心得ているふうだ。
「知りたいわ」
「きっと驚くよ。僕もかなり驚いたからね」
含みのある笑みを浮かべて言う。
その笑みを見て、ロッティは急に不安になった。
「……やっぱり聞きたくない」
世の中には知らないほうがよかったことというのが存在する。レンの意味深な笑みはそれを暗示しているような気がした。
「あっ……」
レンがふたたび乳房を愛撫しだした。
ロッティが恥じらいに頬を染めてうろたえているうちに、彼は飾りリボンを避け、ホックをはずしてしまう。その手際のいいこと。
「レン……、やめて……。だれかに見られたらどうするの……?」
こんなはしたない姿をどう言い訳しろというのだ。
「だれも来ないし、見られないよ。ローレンの命令は絶対だから」
ロッティはレンの申し出に安易に応じた兄を恨んだ。
彼はコルセットも緩めてしまうと、肌着の上からおもむろに乳房に手を這わせてきた。
「や……」
着替えのとき、侍女にしか見られていない部分だ。恥ずかしくてたまらない。けれど彼の視線を浴びながらくりかえし大胆に揉みしだかれると、甘い溜息がこぼれた。
「ん……ぁ……」
五感が徐々に官能に支配され、拒む力も失われてゆく。
(こんな感覚……異常だわ……)
抗えないなにかにとらわれ、ロッティはもがいた。やはり首飾りのせいでおかしくなっている。
「あん……っ」
ふくらみの先端をくすぐられ、声が洩れた。そこは感度がよくて、みるみる硬くなってゆく。
「敏感だな、ここも」
指先で弾かれた尖りは、衣越しでもますます感度を増して凝ってゆく。
「見せて?」
レンが肌着をずらし、手を差し入れてきた。
「いや。恥ずかしいわ」
しかもこんな朝から、明るい場所で。
「あ……」
じかにふくらみにふれられ、どきりとした。あわてて隠そうと胸元をかきあわせるが、彼の手にやんわりと拒まれる。
レンの視線はすでに乳房にある。彼の視線を意識するとなぜかいっそう身体が熱くなって、見せたい衝動にかられた。
それでも抵抗があってじっと手で押さえ隠していると、
「少しだけでいいから」
なだめるようなやわらかな声で囁かれ、暗示でもかけられたみたいに甘い気持ちになった。そのままつい、手の力を緩めてしまう。
やがて肌着を退けられ、みずみずしい乳房のふくらみがあらわになった。
「きれいだな、まばゆいくらいの肌だ……」
朝陽を受けて白々と輝く素肌に、彼が口づけを落とした。鎖骨のあたりから乳房へと。
「ん……」
やわらかな唇の感触がくすぐったかった。
はじめは宝物でも扱うかのごとく控えめで優しい仕草だった。だからあえなく流されてしまったけれど、だんだん口づけというには淫らで荒々しいやり方になってきて、ロッティは少なからずうろたえた。
「………っ、ん……ぁ……っ」
熱い舌が素肌をなぞる。そのたびに背筋が甘く痺れ、溜息が洩れる。
「や……」
しまいには頂ごと口にされ、舌先で淫らに弄ばれた。
「あっ、あっ……、ん……っ」
敏感な乳頭に濡れた舌が絡みついてくる。はじめての淫靡な感覚に、ロッティはびくびくと肩を揺らして悶える。
そのまま尖りを甘く吸いたて、舌でいやらしく転がされる。
なぜか下肢の奥のほうまでがじりじりと熱くなっている。
「あ……あ……、もう……舐めちゃだめ……」
ロッティははぁはぁと吐息をこぼし、断続的に与えられる快感に喘ぐ。
「気持ちいいのに、だめなの?」
レンはわざとちゅっと音などたてて官能を煽ってくる。
「ん………っ」
ふれられているのは乳房なのに、やはり快感は下肢の奥にまで響いて、まるで刺激を求めているみたいに熱く疼く。
この話題はおしまいとばかりに、レンがロッティの首元の首飾りに手を伸ばしてきた。
「あ」
彼の指先が素肌にふれて、ロッティはどきりとした。
「月が満ちるにつれて、性欲も増すというのは本当だった?」
鎖骨のあたりを思わせぶりになぞられ、身体が一気に熱く火照ってきた。
「やめて……」
ロッティは拒んだが、なぜか消え入るような、はかない声しか出なかった。素肌が妙に敏感になっていて、彼の指先の動きに意識を奪われるのだ。
「まさか、もう淫らな気持ちになったの? 僕が隣にいるだけなのに?」
「し、知らないわ」
否定はできなかった。たしかに妙な気分なのだ。距離を縮められたあたりからおかしくなっていた。
「キスしてみようよ、本当に首飾りに催淫の力があるのかどうか知りたい」
レンが囁きながら肩を抱いてくる。
「いや」
「僕を見て、ロッティ」
さらに美貌をよせてせがんでくる。いまにもキスしそうな距離で。
「いやよ。……やめて、レン。どきどきするからこっち見ないで」
ロッティは真っ赤になりながら、顔をそむける。こんなに胸が高鳴るのは絶対に首飾りのせいなのだ。
「かわいすぎてひくんだけど」
ふっと彼が笑った。
「……も、もう、帰りたいわ」
距離が近すぎるのだ。このままでは心臓が高鳴りすぎておかしくなってしまいそうだ。
「紅茶を一杯飲み終えるまでの約束だ。もちろん飲ませないけどね」
「え……」
「キスするから」
目をみはった瞬間だった。顎をすくわれ、レンに唇を塞がれた。
「………っ」
わかりきっていた。逃げたって強引に奪うと。目が獲物を見定めた狩人みたいに艶やかで、たぶんそれに魅せられていた。
「ん……」
互いの唇が密にかさなりあう。その慣れない感触におののきながらも、なぜか、身体の芯はじんと熱くなった。
レンはくりかえし唇をかさね合わせてくる。ロッティを逃さないように捕らえたまま、なにかを伝えるみたいに。
なにを……?
言葉にはできない、快いなにかだ。この男には、裏があるかもしれないというのに。
やがて考えるのさえも忘れ、ロッティは甘い口づけに酔いしれる。
「今どんな感じ?」
レンがいったん唇をはなし、うっとりと視線を絡めてきた。
ロッティは気恥ずかしくて目を逸らした。
「変な気持ちよ。もうしないで……」
つれなく返したつもりが、なぜか甘く掠れた声が出た。
本当にやめてほしかった。ただでさえ首飾りのせいで感情が高ぶりやすいのだから。
「いやだ。きみが欲しいから」
言うなりまたキスされ、続けざまに舌まで入れられた。
「ふ……」
ぬっと押し入ってきたものに、ロッティは一瞬、目をむいた。はじめ、なにかわからなかった。彼の舌だと理解したとたん、じんと身体の芯が熱くなった。
「んぅ……」
レンは退こうとしないから、受け入れるしかない。淫らな動きで口内を蹂躙され、未知の感覚を次々に呼び覚まされる。
ずっと昔から知っている相手と、こんな淫らな口づけをかわしているのが信じられなかった。
でも、決して不快ではなかった。むしろ、快くて夢中にさせられた。
(首飾りのせい……?)
わからない。あまりにも自然に導かれるから――。
「興奮するね」
口づけの合間に、甘い声でつぶやかれる。
「……レンがそうさせているのでしょ」
首飾りのせいか、理性や貞操観念が確実に薄らいでいる。いつもの自分ならとっくに拒んで押し返しているのに、今日はできない。彼にされるがままなのだ。
逆らわないのをいいことに、今度は胸元に手を這わせてきた。
「や……」
ロッティは思わずその手を押さえて咎めた。
「なにするの?」
「キスの続きだけど?」
続きがあるらしい。
「やめて。今はお茶の時間よ」
「ロッティは僕が嫌いなの?」
ふと彼が真顔になった。
「き……嫌いってわけじゃないわ。でもこんなことをするほど好きでもなかったわ」
実に正直な答えだった。自分でも深く納得してしまうほどに。
するとレンがくすっと笑った。
「でも頬は真っ赤だよ? 今のキスの反応といい、僕に気があるとしか思えないんだけどな?」
「く、首飾りのせいにすぎないのよ」
ロッティはますます赤くなりながら返す。
「べつにそれでかまわないよ。きみにどれだけ嫌われようが、僕の気持ちは変わらない。きみを妻にして、愛したいだけ愛するつもりだ」
「……そんなにわたしと結婚したい理由はなんなの?」
毎度、疑問はここに行きつく。
「知りたい? どうして僕が急にきみを口説きだしたのか」
レンのほうも、今の態度に疑問を抱かれるのは心得ているふうだ。
「知りたいわ」
「きっと驚くよ。僕もかなり驚いたからね」
含みのある笑みを浮かべて言う。
その笑みを見て、ロッティは急に不安になった。
「……やっぱり聞きたくない」
世の中には知らないほうがよかったことというのが存在する。レンの意味深な笑みはそれを暗示しているような気がした。
「あっ……」
レンがふたたび乳房を愛撫しだした。
ロッティが恥じらいに頬を染めてうろたえているうちに、彼は飾りリボンを避け、ホックをはずしてしまう。その手際のいいこと。
「レン……、やめて……。だれかに見られたらどうするの……?」
こんなはしたない姿をどう言い訳しろというのだ。
「だれも来ないし、見られないよ。ローレンの命令は絶対だから」
ロッティはレンの申し出に安易に応じた兄を恨んだ。
彼はコルセットも緩めてしまうと、肌着の上からおもむろに乳房に手を這わせてきた。
「や……」
着替えのとき、侍女にしか見られていない部分だ。恥ずかしくてたまらない。けれど彼の視線を浴びながらくりかえし大胆に揉みしだかれると、甘い溜息がこぼれた。
「ん……ぁ……」
五感が徐々に官能に支配され、拒む力も失われてゆく。
(こんな感覚……異常だわ……)
抗えないなにかにとらわれ、ロッティはもがいた。やはり首飾りのせいでおかしくなっている。
「あん……っ」
ふくらみの先端をくすぐられ、声が洩れた。そこは感度がよくて、みるみる硬くなってゆく。
「敏感だな、ここも」
指先で弾かれた尖りは、衣越しでもますます感度を増して凝ってゆく。
「見せて?」
レンが肌着をずらし、手を差し入れてきた。
「いや。恥ずかしいわ」
しかもこんな朝から、明るい場所で。
「あ……」
じかにふくらみにふれられ、どきりとした。あわてて隠そうと胸元をかきあわせるが、彼の手にやんわりと拒まれる。
レンの視線はすでに乳房にある。彼の視線を意識するとなぜかいっそう身体が熱くなって、見せたい衝動にかられた。
それでも抵抗があってじっと手で押さえ隠していると、
「少しだけでいいから」
なだめるようなやわらかな声で囁かれ、暗示でもかけられたみたいに甘い気持ちになった。そのままつい、手の力を緩めてしまう。
やがて肌着を退けられ、みずみずしい乳房のふくらみがあらわになった。
「きれいだな、まばゆいくらいの肌だ……」
朝陽を受けて白々と輝く素肌に、彼が口づけを落とした。鎖骨のあたりから乳房へと。
「ん……」
やわらかな唇の感触がくすぐったかった。
はじめは宝物でも扱うかのごとく控えめで優しい仕草だった。だからあえなく流されてしまったけれど、だんだん口づけというには淫らで荒々しいやり方になってきて、ロッティは少なからずうろたえた。
「………っ、ん……ぁ……っ」
熱い舌が素肌をなぞる。そのたびに背筋が甘く痺れ、溜息が洩れる。
「や……」
しまいには頂ごと口にされ、舌先で淫らに弄ばれた。
「あっ、あっ……、ん……っ」
敏感な乳頭に濡れた舌が絡みついてくる。はじめての淫靡な感覚に、ロッティはびくびくと肩を揺らして悶える。
そのまま尖りを甘く吸いたて、舌でいやらしく転がされる。
なぜか下肢の奥のほうまでがじりじりと熱くなっている。
「あ……あ……、もう……舐めちゃだめ……」
ロッティははぁはぁと吐息をこぼし、断続的に与えられる快感に喘ぐ。
「気持ちいいのに、だめなの?」
レンはわざとちゅっと音などたてて官能を煽ってくる。
「ん………っ」
ふれられているのは乳房なのに、やはり快感は下肢の奥にまで響いて、まるで刺激を求めているみたいに熱く疼く。